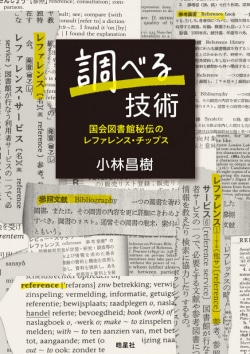『調べる技術』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
発売前に増刷決定! 調べもののコツを「見える化」
[レビュアー] 倉本さおり(書評家、ライター)
誰もが「ググる」(=インターネットで検索する)ことで一定の答えを得られるようになった反面、答えに辿り着くまでの過程はどんどん見えづらくなっている――。そんな「調べもの」をめぐるブラックボックスを見事に解き明かしてくれるのが小林昌樹『調べる技術』だ。情報公開されるや大きな話題となり、今年十二月九日の発売前に増刷が決定。書店に出回る頃には三刷が決定(入荷は二十六日頃を予定)したものの、各所で品切れが相次ぎ、あっというまに四刷が決定。Twitter上では「#調べる技術の在庫を調べる」というハッシュタグが誕生するほど盛り上がっている。
著者は国会図書館で十五年にわたりレファレンスサービス(利用者の調べもの相談)に従事した人物。サブタイトルにある「チップス」とはちょっとしたコツのことだ。例えば、各々の調べものに「最適の雑誌記事索引を選ぶ」際のポイントや、「見たことも、聞いたこともない本を見つけるワザ」……それら大小さまざまなコツを、動線を確認しながら整理しつつわかりやすく解説していく本書は、普段私たちが手探りのまま行っている「調べる」という作業の内実を「見える化」してくれるものでもある。
「小林さんは長年現場で利用者の“探しもの”に付き添ってきた実務経験に加え、個々の知識を体系立ててくれる理論の両輪がある。だからこそ本書は頼れるマニュアルとして機能するんだと思います」(担当編集者)
造本の面では、実際に調べものをする際に「お供」として使ってもらえるよう持ち運べるサイズ感とめくりやすさにも注意を払った。ヨコ組みを採用したのも、読みながらインターネットで検索するシーンを想定してのことだ。「器はコンパクトに、でも中身は発見に満ちた体験になるような本を目指しました」(同)
版元の皓星社は出版業と同時に「ざっさくプラス」というデータベースを運営してきた会社だ。戦前期の雑誌記事や地方の雑誌記事まで詳細に検索できる貴重なデータベースの存在は、これまで“知りたい”と願う人びとの拠り処になってきた。その営為を言祝ぐようなベストセラーの誕生だ。