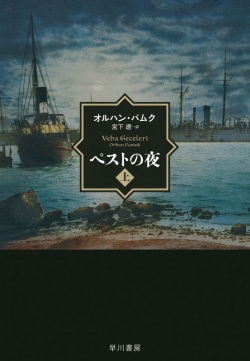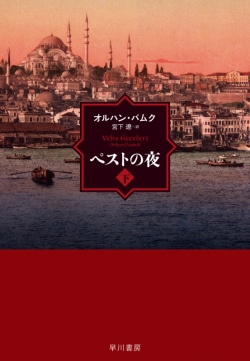『ペストの夜 上』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『ペストの夜 下』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『ペストの夜(上)(下)』オルハン・パムク 著
[レビュアー] いとうせいこう
◆ユーモアと皮肉で魅惑的に
トルコを代表するノーベル文学賞受賞者、私もその深いユーモアと鋭い皮肉と物語のロマンティックさを敬愛してやまないオルハン・パムク。新作は二〇二一年に出版された長編で、舞台は一九〇一年、つまりオスマン帝国末期におけるミンゲル島という美しい場所である。
その地図で見つけにくい島に、ある日ペストが発生し、蔓延(まんえん)する。噂(うわさ)を聞きつけた皇帝アブデュルハミト二世は有名な疫学者を船で秘密裏に派遣するのだが、彼は何者かに殺されてしまう。
そこで学者の任務を引き継ぐことになるのが若き医師ヌーリーとその妻である皇帝の姪(めい)パーキーゼ姫なのだが、彼らは当然暗殺の謎も解くよう期待される。果たして…?
と、筋書きは読者のために極力はしょったが、すでに物語の魅力が我々を引き込んで離さないのがわかるだろう。
さらにトルコは今に至るまできわめて複雑な歴史を持つ。パムクが知悉(ちしつ)しているミンゲル島にもイスラム教徒がおり、ギリシア正教徒がおり、行き交う言葉もトルコ語、ギリシア語、フランス語、ミンゲル語など多数に分かれている。ゆえにペスト対策も決して一筋縄ではいかない。
その模様をパムクは微に入り細をうがつように書くのだが、語り手は歴史家と設定され、数々の逸話が筆まめなパーキーゼ姫の手紙からとられたり、聞いたこともない書物から引用されたりと愉快な仕掛けに満ちている。
そこに当のパムクも意図しなかった「世界の読者自身が疫病に苦しみながら読む」という“仕掛け”が加わってしまうのだから、作品というものは存在の仕方を予想出来ない。本作を書き始めたのはコロナの前だった。にもかかわらず、疫病への民衆の無知、宗教や政治によって邪魔される隔離、思わぬ別離の連続などなど、出来事はあまりに似る。昂揚(こうよう)するナショナリズムの描写など今の我々そのものだ。
だが、ありがたいことにその残酷な状況をパムクは「深いユーモアと鋭い皮肉と物語のロマンティックさ」で魅惑的に書く。小説の力で。
(宮下遼訳、早川書房・各2970円)
1952年生まれ。トルコの作家。2006年ノーベル文学賞。『無垢の博物館』など。
◆もう1冊
カミュ著『ペスト』(光文社古典新訳文庫)。中条省平訳。