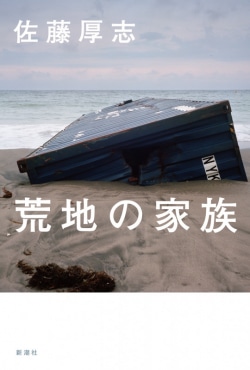『荒地の家族』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『荒地の家族』佐藤厚志 著
[レビュアー] いとうせいこう
◆あの日以後の人々の苦役
最も新しい芥川賞受賞作品『荒地の家族』を生み出した佐藤厚志は、二〇二〇年にも仙台短編文学賞において「境界の円居(まどい)」で大賞を獲得しており、宮城県気仙沼市や亘理町を舞台としている。つまり仙台市や、福島第一原発から少しだけ離れた場所を。
津波による甚大な被害を受けた土地の周辺には、長いこと機能を失ったことのある東北唯一の政令指定都市があり、また深刻な放射能事故の現場が存在し、海沿いには巨大な防潮堤が建設されて人と海をさえぎっているわけだ。
こうして多くの立場、問題を含み込んだまま、小説の舞台では今日も『荒地の家族』なら主人公の植木職人が、「境界の円居」なら新聞配達の青年が一日を働く。
短編で佐藤はこう書く。「あれ。あの時。大地震。3・11。東日本大震災……(中略)どの表現もしっくりこないとも感じた」
そしてついに『荒地の家族』ではそれらの呼び名が禁欲的なほどに現れない。ある時は「海からやってくるものの強大さ」と書かれ、またある時には「どうにもならない災厄が耐えがたいほどに多すぎて」と人が生きる上でたくさんある苦役のひとつがそれであるかのように記される。
実際佐藤厚志作品では誰もが重い荷をじっと低い姿勢を保ったまま抱え持っていて、作者は安易な希望をちらつかせることなく、あの日以後の人々をひたすら丁寧に等距離で描写する。
時にノンフィクションかと思うような厳密なリアリティ構築こそが、むしろ小説に可能な唯一の救いかもしれないと私は読みながら思った。
それがどんな憂いに満ちた設定であっても、書き手が対象を見つめ、並走し続けていなければ言葉は出てこない。また言葉になれば苦難は必ず次元をずらされざるを得ない。どちらの方向へであれ。
さてこうして描かれた『荒地の家族』が指す「家族」とはどこまでを言うのか。名指されない災厄のように、それはいつの間にか領域を広げ、我々にまで届いてこないか。
奇(く)しくもこの十三回忌に。
(新潮社・1870円)
1982年生まれ。作家。丸善仙台アエル店勤務。今年、本作で芥川賞を受賞。
◆もう1冊
石井麻木著『ただいま、おかえり。3.11からのあのこたち』(世界文化社)