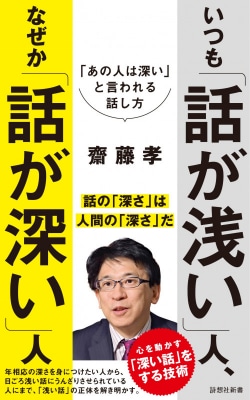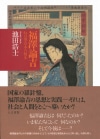『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
「浅い話」も工夫次第で「深くなる」。あの人は深いと言われる話し方のコツ
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
すでに知っていることや、当たり前のことばかりを述べる話、
大事なポイントを押さえていない掘り下げ方の甘い話、
具体性がなく、終始、漠然とした話、
思い込みが強くて視野の狭い話、
ものを知らない、知識のない人の話、
思いつきだけで、思考の形跡がない話、
人生観が感じられない話、
(「まえがき あなたのまわりの『浅い人』」より)
私たちのまわりにあふれるこういった話は、聞き手に「浅い」という印象を与えてしまうもの。『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』(齋藤 孝 著、詩想社新書)の著者はそう指摘しています。
そして、そういった「浅い話」をする人は、聞き手に「底の浅さ」を見透かされていたとしても、おかまいなしに滔々と話し続け、周囲から「浅い人」という評価を受けるようになってしまうのだとか。
なぜ、こういった人たちの話は、聞き手に「浅い」という印象を与えてしまうのでしょうか。「浅い話」にはいくつかのパターンがありますが、本書ではその共通の問題点を解き明かし、私たちが感じる「深さ」、「浅さ」とはいかなるものなのかを具体的に示します。
また、「深い話」とはどのようなもので、それを可能にするためには、どういった能力が必要なのか。また、その能力をどう伸ばせばいいのかも解説しました。(「まえがき あなたのまわりの『浅い人』」より)
そんな本書のなかから、きょうは“「深さ」を相手に強調するような話し方”を紹介している第4章「『あの人は深い』と言われる話し方の技術」に焦点を当ててみたいと思います。
「スリーステップ論法」が話を深くする
その道を究めた職人や、プロのアスリートたちなど、なんらかの「プロ」と呼ばれる人たちの発言には深さを感じやすいもの。それは、彼らのようなその道の専門家が深く思考し、探究しているという経緯が発言から垣間見られるからなのだろうと著者は推測しています。
「こんなところまで考えているのか」「そのような部分にこだわって技を究めているのか」「そのような探究を続けると、こんな世界が広がっているのか」というように感じさせる深さがあるからこそ、私たちの心を動かすということ。
なお、この点に関連して注目すべきことがあります。それは、「私たちが話す際にも、そういった話の展開を取り入れることができれば、深さを強調することができる」という著者の主張。
まず、「表面に見えているのはこうです」と提示してから、相手の知らないような事実を、「実は、その奥はこうなっています」、「さらに、奥はこうなっています」と展開するのです。
私はこれを「スリーステップ論法」と呼んでいます。(152〜153ページより)
たとえば感銘を受けた映画について、誰かに話そうとしている場合を考えてみましょう。
そんなときにはまず、表面に見えている部分として、「この映画はこういう内容で、とてもおもしろいですよ」と中身を紹介することになるはず。もちろんそれだけでもひとつの情報として話は成り立ちますが、深い話にはなりません。
そこで次に、「じつはこの映画、本来は〇〇になるはずだったのが、制作者のこだわりで△△になったんですよ」というように、聞き手の知らないような“奥の部分”の話を展開するのです。そして仕上げに、「さらにいえば、この映画がヒットしているのは××がポイントなんですよ」ともう一段深いところに踏み込むわけです。
まず、聞き手が興味をもってくれる題材を選ぶ能力も必要ですが、それを選んだら、聞き手に紹介するという段階が「ホップ」です。
そして紹介したあとに、「実は、その背景にはこういうことがあります」と堀り下げるのが「ステップ」。
そこから、「さらに、その奥はこうなっています」ともう一段深く入るのが「ジャンプ」です。(153〜154ページより)
このように「ホップ」「ステップ」「ジャンプ」の3段階で展開されると、聞いている方も「なるほどね」と感じやすいもの。したがって、この3ステップを「実はこう」「さらにこう」「そのまた奥がこう」とテンポよく短時間にまとめて話すことが大切だということです。(151ページより)
1分間で話せるようになる「15秒トレーニング」
しかし現実問題として、「テンポよく短時間にまとめて話すこと」はなかなか難しくもあります。それどころか、深い話をしようと意識しすぎるあまり、どんどん話が深掘りされて広がり、話が長時間に及んでしまうこともあるでしょう。しかしそうなると、聞き手から「深い」ではなく「くどい」という思われてしまうかもしれません。
だからこそ、せいぜい1分間で終わるくらいの話にすべきだと著者。基本的には30秒を想定して話し、聞き手が興味を持ってくれそうなら、そこから30秒伸ばして、1分間でやめるのがベストだというのです。
短時間でありながら中身の濃い1分間だからこそ、「深い!」と聞いている人の心を動かせるということのよう。なお、1分間は短すぎると思われるかもしれませんが、実は多くのことが語れるのだそうです。
ポイントは、“15秒の感覚”を身につけること。時間を計りながら話してみると、15秒でもある程度のことがいえることがわかるもの。無駄を削ぎ落とすコツがつかめるわけで、だからこそ1分間で話すスキルを身につけるためには、まず15秒の間隔を身につけることが近道だというわけです。
15秒で話す感覚が身についたら、それが4つ組み合わさって1分間になると考えるのです。
たとえば、何かの事件について解説するとしましょう。
パート①事件のあらまし 15秒
パート②事件の真相 15秒
パート③さらにその奥の真相 15秒
パート④この事件の本質 まとめ 15秒
(186ページより)
このように各15秒のパートを4つ合わせ、トータル1分間で話すということ。これを繰り返して話す際の時間感覚を身につければ、誰でも簡潔に中身の濃い1分間の話ができるようになるそうです。(184ページより)
話を通じて“伝えるべきこと”を相手に“深く”伝えるという行為は、ただでさえ簡単ではありません。そこで本書を参考にしつつ、「あの人は深いね」といわれるような話し方を目指してみるべきかもしれません。
Source: 詩想社新書