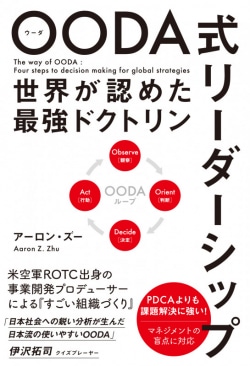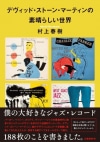『OODA式リーダーシップ 世界が認めた最強ドクトリン』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
PDCAより変化に柔軟に動ける。米海軍式フレームワークでリーダーシップが身につく
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
現実問題として、この国のITは他国よりも何周も遅れ、経済力も減少していくばかり。世界の国々の所得が高くなっているなか、日本だけが一人負けしている。その根本的な原因は、ひとりひとりのリーダーシップ力。
すなわち、リーダーシップを身につけることは、企業や個人の未来を大きく左右するーー。
アメリカ空軍予備役将校訓練部隊(United State Air Force Reserve Officer Training Corps/ROTC)出身の事業開発プロデューサーである『OODA式リーダーシップ 世界が認めた最強ドクトリン』(アーロン・ズー 著、秀和システム)の著者は、このように述べています。
そこで本書では、リーダーシップを身につけるために重要な意味を持つOODA(ウーダ)ループというフレームワークを紹介しているのです。
でも、それはどのようなものなのでしょうか?
元アメリカ空軍大佐で戦闘機のパイロットだったジョン・ボイド氏(John Boyd)が提唱した意思決定プロセスで、PDCAよりも環境変化に柔軟に対応でき、変化が激しい昨今のビジネスをハンドリングしていくリーダーに欠かせない概念だ。
「観察(Observe)」、「判断(Orient)」、決定(Decide)」、さらに「行動(Act)」の四つに分かれており、意思決定から行動までを網羅している。
さらに、OODAを「イシュー・セリング」という変革ツールと組み合わせることで、スピーディーな組織づくりにも活かすことができる。(「プロローグ」より)
こうした考え方に基づいて本書で解説されているのは、多様化するビジネスにおいてリーダーシップをどのように活かし、組織力を高めていくべきかということ。さらには事業開発の方法や、ビジネスでのクリエイティブ設計についても説明がなされています。
だとすれば、リーダーシップについてどのような論旨が展開されているのかを知りたいところ。そこできょうは第一章「科学的に考えるリーダーシップの定義」のなかから、OODA式リーダーシップについての基本的な考え方を確認してみたいと思います。
いまの時代こそ必要なOODA式リーダーシップ
OODAループに対する認識は、日本においてはまだまだ薄いかもしれません。しかしそれは、時々刻々と変化する環境で成果を得るためのフレームワークなのだと著者は強調しています。
PDCAよりも環境変化に柔軟に対応でき、変化が激しい昨今のビジネスをハンドリングしていくリーダーにとって、欠かせない考えと言っても過言ではない。(60ページより)
ちなみにOODAループ(以下、OODA)は4つのプロセスに分かれており、一周することで意思決定から行動までのプロセスがなされるそう。その点についてはPDCAと同じであるものの、各プロセスの内容が大きく異なるのだといいます。(60ページより)
PDCAのプロセス
計画(Plan)実行(Do)評価(Check)改善(Action)
OODAのプロセス
観察(Observe)判断(Orient)決定(Decide)行動(Act)
(以上61ページより)
OODAの4つのプロセス
次に、OODAでの各プロセスを確認してみましょう。
【観察】
まず、現状を把握して客観的な情報を集めるのが「観察」の段階。「〇〇と思われる」ではなく、「現状でなにが起きているか」「どのような状況にあるか」などをそのまま収集するわけです。
ここで注意すべきは、推測や判断はおこなわず、あくまで客観的に物事を観察すること。まだ判断する段階ではないので、どんなに不利な情報だったとしても事実を受け止め、自分なりのバイブスをかけてはいけないのです。
【判断】
収集した情報をベースに「判断」を下すプロセス。これまでの傾向や過去の経験などから判断するわけで、だからこそ重要なのがリーダーの経験値。
たくさん経営判断を経験しているリーダーはそれなりの場数を踏んでいますから、迅速な判断ができるのです。ところが年功序列の企業だと、若手は判断をする経験をなかなか積むことができなかったりもするもの。
【決定】
観察と判断をベースに具体的な行動を「決定」するということで、この決定こそがリーダーとしての能力が問われるところ。
エゴと謙虚のバランスが崩れた“弱すぎるリーダー”だと、「みんなで決めよう」などと無責任なことをいいだす可能性もありますが、そんなときは即座に対応策を考えたほうがいいそうです。なぜなら、そのとおりにした場合、プロジェクトは大いに失敗する可能性があるから。
【行動】
最後は決定事項を「行動」に移す段階。池に小石を投げると波紋が起きるのと同じように、行動に移すことでなんらかの状況変化は起こるもの。ここでふたたび「観察」に戻りながら、起きた変化に対して仮説を検証するのです。
そして、その作業を何度も繰り返すことで、不安定な環境下でも柔軟な対応ができるようになるということ。
PDCAと違って、OODAは高速で回さないといけない。(中略)このOODAを回すことで、小さな新規事業でも大きな既存事業をおびやかすことも夢ではないのだ。(64ページより)
なお前述したように、OODAは元アメリカ海軍のボイド大佐が提唱したものであるだけに、そこには根本的な軍事戦略の意図が存在します。とはいえ、当然のことながら政治的な意図は皆無。あくまでも軍事戦略および法執行学、さらには経営学の観点からの分析であるわけです。(61ページより)
軍事戦略をベースにしているだけあって、その視点は斬新。これからのビジネスの道筋を模索していくうえで、大きく役立ってくれることでしょう。
Source: 秀和システム