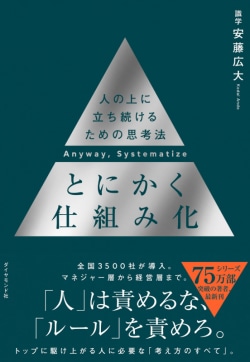『とにかく仕組み化』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
ひとつ上の視座を手に入れる思考法。組織で働くリーダーための「仕組み化」3つのコツ
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
『とにかく仕組み化 ── 人の上に立ち続けるための思考法』(安藤広大 著、ダイヤモンド社)の著者は、「識学」というマネジメント法を通じ、多くの組織の問題を解決してきた人物。「識学」においては、組織内の誤解や錯覚がどのように発生し、どうすれば解決できるか、その方法を明らかにしているのだそうです。
本書は、そんな識学のメソッドをもとにしながら、「人の上に立つべき人」に向け、仕事の型になる「仕組み化」の考え方を伝えているわけです。ただしそれはビジネスモデルの話ではなく、あくまで「人」をどう動かすかという本質的な問題。
どんなビジネスモデルであっても、最終的に重要になってくるのは「人」。「ひとりひとりがなにに集中するのか」「どういう改善に取り組むのか」ということについての考え方の差が積み重なることで、ビジネスはうまくいくというのです。
「仕組み化」とは、「ルールを決めて、ちゃんと運営する」こと。もしかしたら「仕組み」や「ルール」ということばには、ネガティブなイメージがあるかもしれません。しかし重要なのは、「なぜそのルールが生まれたのか」について想像力を働かせてみることなのだと著者は述べています。
そのルールは、過去になにか問題が起きたときにつくられたものであるはず。ただ、当時の「責任」を語るべき人が現存しないため、ルールが形骸化したままの状態で残っている可能性がある。だからこそ、誰かがその「責任」を引き受け、変えなくてはいけないということ。
本来、人の上に立つ人が、自らの責任で変えるべきです。
もしくは、「このルールがあることで、ある問題の発生を食い止めています」
ということを組織全体に浸透させなくてはいけない。
ルールを正しく取り扱う仕組みがないから、「理不尽なルール」と思われてしまうのです。
仕組みの考えは、そうやって使われるべきです。
過去に作られて形骸化したルールを、もっと大きな仕組みの枠組みによってアップデートしていく。
その責任をとるべき人が、人の上に立つべきなのです。(「はじめにーー人の上に立ち続けるための思考法」より)
きょうは、こうした考え方に基づく本書の第1章「正しく線を引くーー『責任と権限』のなかから、「仕組みに立ち返れば、どんどん『新しいこと』ができる」に焦点を当ててみましょう。
メリットがあるから「人とつながる」
ここでは、あるメーカー企業の営業の話が引き合いに出されています。
営業の場合、自分の部署の商品を扱うのは当然のことですが、その営業先で他部署が扱う商品が売れそうな状況が訪れることもあるでしょう。そんなときには、次のような2つの考えが頭に浮かぶはず。
「自分にはなんのメリットもないから、まあいいか」
「会社全体の売上につながるから、対応したほうがいいかもな」
ここに登場する営業マンは、必ず後者の考えを採用し、他部署に紹介してつなげているのだそうです。なぜなら、そののち商談が成立したら、最初に紹介した人にもポイントが与えられるから。
そのように、他部署にトスをあげる人がいたなら、それをポイント化して評価に組み入れるのです。
そういう仕組みがあると、社員はどのように日々を過ごすでしょうか。
自分の扱う商品だけでなく、自社の商品すべてに精通しようとするかもしれません。
仕組みがあるから、人は動き、部署を超えてつながるのです。(93〜94ページより)
それがもしも精神論だったとしたら、主体性がある一部の人だけしか動かないはず。しかし、仕組みがあり、そこにメリットがあれば、人は動くわけです。(92ページより)
属人化に甘える組織
なかには、部署に分かれている人を疑問視する人もいるでしょう。しかし仕事に集中できるのは、部署に分かれて自分の役割が明確になるから。だからこそ、タテ割りが基本だと著者は主張するのです。
そこでよくない問題が起こっているなら、横断する仕組みによって解決するしかありません。もちろん、部署を超えて新プロジェクトを起こす場合も同じ。そこでの責任者を新しく立て、新たなピラミッド組織の形をつくるべきだというのです。
構造は、同じです。
フラットな状態のほうがスピードが速くなりそうな錯覚がありますが、実際は違います。
うまく動ける一部の人にとって進めやすくなるだけです。
まさに「属人化」の状態です。
本当に大事なのは、どんな人も活かすことです。
そのために、組織としての仕組みを整え、動けるようにするのです。
「いい人」だからやるわけではない。
「積極性がある」からやるわけでもない。
その人の本来の性格に組織が頼ってしまうのは、いい状態ではありません。(95〜96ページより)
著者いわく、組織はつい属人化を放置してしまうもの。どこの職場にも「人がやらないような仕事を率先してやってくれる人」はいますが、つまりはその存在に甘えてしまっているわけです。
しかし、そんな状態が続いていれば、やがてそういう人は「自分だけ損をしている」と感じ、組織を去っていくかもしれません。したがって、そうなってしまうことを「仕組み」によって回避しなければいけないのです。
誰に責任があり、誰が何をするのか。
それを最初に仕組みとして決めます。
すると、どんどん新しいことができるようになります。(95ページより)
社内での新規事業や新プロジェクトは、そのようにして生み出されるべきだということです。
「任せる」の本質的な意味
「リーダーは部下に仕事を任せなさい」といわれることがありますが、それはただの「無責任」だと著者は断言しています。本来の「任せる」とは、明文化した責任と権限を与えること。
つまりは「なにをしなければいけないか」「そのために、なにをやっていいか」の線引きをすることが重要だという考え方。それを示さないまま、属人化させる意味で「あとは任せた」と丸投げするようでは、リーダーとして失格だということです。(97ページより)
著者が本書で伝えようとしているのは、社会人としての「生き方」にも通じること。そのため耳が痛い話もあるかもしれませんが、現状の「ひとつ上の視座」を手に入れるつもりで、その内容を真摯に受け止めるべきかもしれません。
Source: ダイヤモンド社