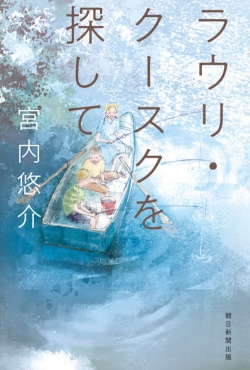『ラウリ・クースクを探して』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
光ある道を生きるのが難しい国でプログラミング言語に救われた少年
[レビュアー] 石井千湖(書評家)
宮内悠介の最新作『ラウリ・クースクを探して』は、ソビエト連邦時代のエストニアに生まれ〈何もなさなかった〉人物の伝記という体裁で書かれた小説だ。バルト海に面する小国エストニアが、ソ連から独立して、国民のほとんどがマイナンバーカード(eIDカード)を持ち、世界で初めてインターネットによる地方選挙を行うようなIT先進国になっていく過程も描いている。
一九七七年、ラウリは首都タリンの近郊にあるボフニャ村で生まれた。数字を数えるのが好きな子供だった。ある日、機械技師の父が家にコンピュータを持ち帰ったことが、ラウリにとって大きな転機になる。情報科学(インフォルマティカ)の時代を見据えたソ連は、КУВТ(日本のヤマハが作ったソビエト向けのMSXコンピュータ)を学校教育に導入するのだ。孤独だったラウリは、ゲームのプログラムを組むことで自分の居場所を得て、無二の親友とも出会うが……。
村はずれの教会の不良神父がラウリに〈この国で、光のある道を生きろとは言えない。だからせめて、おまえさんはまっすぐ、したたかに生きてくれよ〉と言うくだりは印象深い。当時のエストニアでは言論の自由が制限されていた。森にはパルチザンが殺された跡も残る。光のある道を生きるのは難しい国だったけれども、このときラウリの前にはまっすぐな道が見えていた。母語にしばられない機械の言語――プログラミング言語があったからだ。機械の言語に登場人物が抑圧から解放され、属性を超えた関係を育むところがいい。
ソ連の崩壊後、ラウリは自分の道を見失う。冒頭で語られているとおり、激動の歴史のなかで戦ったわけでも、逃げたわけでもない。そんなラウリの足跡を、語り手はなぜ追っていたのか。謎が解けたとき、ラウリは忘れがたい人になる。彼は大きなことは何もなさなかったかもしれないが、まっすぐしたたかに生きることには成功したのだ。