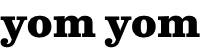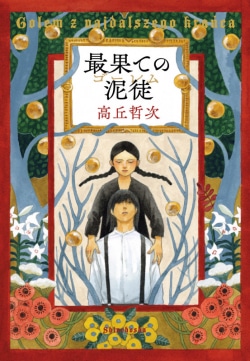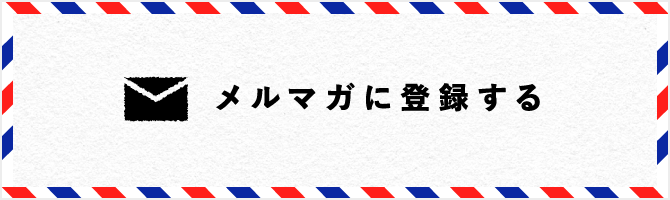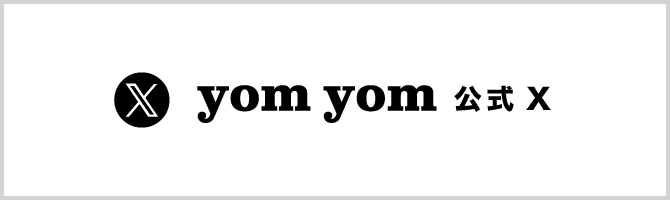「ポーランドには“ゴーレム”製造者が大勢いた」実際の文献を手掛かりに執筆!生命の誕生を問う物語
更新

昔からSFで描かれてきた、動く泥人形の「ゴーレム」。昨今はゲームや漫画でも用いられるモチーフですが、もしこのゴーレムが実在し、労働力として人間に使役されていたら――。現代のAIとも重なって見えるこのゴーレムを用い、「生命誕生」の根源を問うた最新小説『最果ての泥徒』(新潮社)を発表したのが、作家の高丘哲次さん。「日本ファンタジーノベル大賞2019」を受賞し小説家デビューした高丘さんは、作品の壮大なスケールとエモーショナルな筆致が評価されてきました。20世紀初頭、戦争に陥った日本を含む世界について、史実を元にしながらゴーレムの存在を基点に描いた最新作を、高丘さん自身に語っていただきました。
――本作は、前作『約束の果て 黒と紫の国』から約3年半の歳月を経て刊行されることになりました。本作の執筆、着想のきっかけは何だったのでしょうか?
私が日本ファンタジーノベル大賞を受賞した2019年に、娘が誕生しました。小説家としてのスタートは、親としてのスタートでもありました。
『最果ての泥徒』という小説の内容をひとくちで言えば、マヤという女性が自らの人生をかけ、ゴーレムという新たな生命を育む物語ですが、いま思えばそれは、どこか出産、育児の比喩のようでもあります。本作を描く直接的なきっかけとして、娘の誕生という人生で最も大きな出来事も少なからず影響していたのだと思います。
――とりわけ重要な役割を果たすのが「ゴーレム(泥徒)」です。かねてからSF・幻想・怪奇小説のジャンルにおいて描かれてきたモチーフではありますが、昨今ではゲームや漫画の文脈でも語られることが多いかと思います。今回、なぜゴーレムをモチーフに選んだのでしょうか?
一般的なゴーレムの創り方は〈土で作った人形に、魔術的な力がこめられた文字を書いた護符を埋め込む〉という方法です。つまり、文字によって生命を吹きこむという行為なわけです。生命の誕生というテーマで小説を書こうとした時、まっさきに思いついたモチーフがゴーレムでした。
ジャンルや、流行について特に意識したわけではありませんが、結果として、今この時代に書かれるべきものに仕上がったのではないかと、自分では思っています。
――ゴーレムという存在を基点に20世紀初頭の世界、そして日本がどのように変容していくのかが、史実をもとにしながら描かれてゆく、「歴史改変もの」としての魅力もあります。その結果、20世紀初頭の戦火の絶えない時代に労働力として使役される「ゴーレム」の存在は、読者によっては現代におけるAI社会と重なって見えてきます。なぜ史実をもとにした作品世界を構築されたのでしょうか?
ゴーレムにまつわる伝承は、わりと新しい時代のものが多く見られるのですが、資料の中をさまよううち、17世紀末の記録に、「ポーランドには粘土を材料にした口の利けない下僕を製造できる、すぐれた製作者が大勢いる」という内容の文献が見つかり、気がつけば19世紀末の東ヨーロッパという舞台に行き着いていました。
――作品内リアリティとディテールを追究する作業は大変な労力が要ったとも思いますが……。
ゴーレムは、ユダヤ教の信仰と密接に関係しています。それが、人々の信仰によって育まれた存在である以上、単に物語を盛り上げるためのアイテムとして使うことはできませんでした。
そのため、ゴーレムという存在が生み出された背景を踏まえたうえで、どのように小説として表現すべきか、自分なりに考え抜く必要がありました。小説の展開も、本当にこれで良いのかという葛藤があり、何度も書き直しています。そのため、執筆に3年半という歳月を必要としました。
執筆において最もたいへんな点といえばこのことになるのですが、必要な過程であったと捉えています。
……ただ、大々前提として『最果ての泥徒』という小説は、読者の皆さんに「面白い!」と言っていただくために書いたものです。
ファンタジー小説として、バディもの小説として、あるいは恋愛小説としても、楽しんでいただけるかと思います。あえて自分で言いますが、ものすごく面白い小説です。ぜひ、お手にとってご覧ください。
高丘 哲次(タカオカ テツジ)
北海道函館市生まれ。国際基督教大学教養学部人文科学科卒業。同大学院博士前期課程比較文化研究科修了。2019年『約束の果て 黒と紫の国』で日本ファンタジーノベル大賞2019を受賞。本作は2作目にあたる。