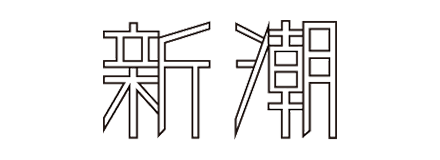養老孟司さん
大きな問題が起きた際に、いわゆる専門家、評論家の意見とは別に「あの人はどう見ているだろうか」と気になる人物がいるのではなかろうか。そうした人として養老孟司さんの名を挙げる人も多いはず。そこで、コロナ禍を受けて養老先生が文芸誌「新潮」に寄せた原稿(「コロナの認識論」第1回2020年7月号より)を全文ご紹介しよう。コロナの視点から人を見れば――という導入からして、ちょっと他の論考とは一線を画すものになっている。
ウィルスの大きさでヒトを見てみたら?
テレビ放送では、ニュースの初めにコロナウィルスの電子顕微鏡写真が映されることが多い。多くの人がその映像を見慣れたと思う。では訊くが、ウィルスがあの大きさで見える顕微鏡で、アナウンサーを見たら、どのくらいの大きさになるだろうか。
私の概算だが、百万メートル、千キロの桁に達する。とうていテレビの画面にウィルスと一緒に映せたものではない。ところが画面では、ウィルスとアナウンサーが当然のように同居している。大げさなようだが、現代人の盲点の一つがここに示されている。両者を同一の画面で扱って、当然だと思っているらしいからである。
ウィルスの側から世界を見てみよう。ウィルスにとって一個の細胞は自分の百倍以上の大きさになる。ウィルスをヒトと考えれば、細胞は一辺が百メートルの桁の立体に相当する。しかもヒトは十兆の桁数の細胞からできている。なんとも巨大な世界ではないか。ウィルスにとっての人体は、ヒトにとっての地球以上になるのではないか。
現代科学はウィルスの構造を確定する。写真すら撮ることができる。でも問題はそこではない。ウィルスが取り付く相手はヒトの細胞だからである。そこにサイズの問題あるいは関係性の問題が表れる。ウィルスの構造はわかったとして、ヒトの細胞はどうか。ウィルスを見る精度でヒトの細胞を見たら、どうなるか。さらにはヒト個人、挙句にヒト社会まで見ようとしたらどうなるか。
ウィルスを調べるのと同じ目線では、とても無理に決まっている。ウィルスを基準にすれば、細胞ですら大き過ぎて、情報処理が完全にはできない。そんなややこしいものを研究者も見たくないに違いない。しかもその細胞は、常時生きて動き続けている。見ている傍から、変化してしまう。そんなものは見ることができない。だから解剖学は死んだものしか見ないのである。ウィルス自体は代謝しない、つまり止まっているから、それを調べるのは細胞よりはずいぶん楽である。
結論はじつは初めから明らかだと思う。世界をできるだけ正確に、つまり「科学的に」見ようとすることはできる。しかしそれは常に部分に留まる。なぜなら部分を正確に把握すると、全体はいわばその分だけ、膨張するからである。ウィルスを百万倍の拡大で見ることはできる。それをやると、じつは世界が百万倍になってしまう。ウィルスの人体への影響をその精確さで見ようとするなら、それが取り付く細胞も百万倍の桁で見なければならない。その意味で、なにかが精確にわかるということは、関連する事象がその分だけボケることを意味する。ウィルスがわかった分だけ、細胞がボケる。これを私は認識における不確定性原理と呼んだことがある(『形を読む』講談社学術文庫)。いまではこの表現は間違っていると思うが、内容は変わらない。ではどう呼べばいいか。エントロピーは増大する、かもしれない。
もちろんウィルスとヒトとを「関係」させなければいい。ウィルスを見るなら、ウィルスだけ見ればいい。なにもヒトを見る必要はない。だからウィルスの専門家なのである。こうして科学は専門化する。ウィルス学者は同じ目線でヒトを見ない。すでに述べたように、ウィルス目線では、ヒトは大きすぎて見えないからである。コロナ問題で専門家会議が始終開かれる。その遠因はここにある。私はそう思う。
そこで当然ながら、問題が生じる。専門家と官僚と政治家が集まった時、そうした人々の共通のプラットホームとはなにか。主題はコロナに決まっているけれど、目線はどうなのか。数学でも熱力学でも情報理論でもあるまい。それなら専門家会議こそが旧約聖書にいうところの「バベルの塔」ではないのか。じつは全員が別な言葉を語っているのかもしれないのである。中東は人類史上最も古くから都市化した場所である。都市化とは脳化すなわち意識化である。そこでは情報の相互関係の問題が発生する。目線の共有が不可能なのである。
私は解剖学を専攻した。解剖学は構造を扱う。機能を扱うのは生理学である。構造から機能は推察可能か、可能なこともあるし、不可能なこともある。不可能の典型は胸腺だった。私自身が学生だった頃は胸腺の機能的な意味ははっきりしていなかった。それがはっきりしたのは免疫学が進んだからである。胸腺は免疫細胞の教育機関であることが判明した。胸腺自体をいくら見ても、免疫という枠組みを知らなければ存在意義がわからない。カブトムシの角をいくら分析しても、角の機能的な意味は不明である。食料あるいは♀をめぐる縄張り争いを想定しなければ、角の機能は不明でしかない。ウィルスの動きはヒト細胞の動きを理解しなければ、わからない。
シャノンの情報理論と熱力学とは、同じ形をしている。だからエントロピーという言葉が情報理論に導入された。ボルツマンの方程式と情報の方程式はいわば同じ形になる。それなら情報の法則と熱力学の法則は並行しているはずである。私はどちらの分野も半わかりである。きちんとわかっていれば、情報理論の専門家か、熱力学の専門家になっている。残念ながら、私は虫と解剖しかわからない。それもたぶん半わかり、一知半解である。
だからここからは乱暴に行こう。熱力学で私にとって興味深い部分は、いわゆる第二法則である。エントロピーは増大する。これではほとんどの人がなんのことやら、直観的にもわからないはずである。だから乱暴に行こう、と述べた。この法則の系といってもいいし、言い換えと言ってもいいが、重要だと私が思うのは、自然界に秩序が発生したなら、同量の無秩序がどこかに発生する、ということである。それが正しいかと訊かれたら、わからん、というしかない。そもそもそんなこと、どう実証すればいいか、わからない。そんなことがちゃんとわかったら、私は偉い学者になっている。だからここでは、それが成り立つという前提で考える。いずれにせよ、なにかを前提にしなければ、議論は成り立たない。意識自体は秩序活動である。意識にはランダムなことはできない。だから乱数表は機械に作らせる。宝くじの当選番号の決定は、ダーツに頼るしかない。
情報にもそれが該当するとすれば、現代の混迷がよくわかる。なにかがわかったということは、別なことが同じくらいに、わからなくなったということだからである。二十世紀末に『科学の終焉』(徳間文庫)という本が出た。アメリカの科学ジャーナリスト、ジョン・ホーガンが「科学は世界を最終的に解明すると思いますか」という質問を、著名な科学者たちに尋ねた結果の報告である。大多数の答は「解明しない」というものだった。ただしその理由として、科学者たちが私のように思っていた可能性はある。でもそう言わない理由なら、複数考えられる。面倒くさいからそれは書かない。
ヒトとウィルスの大きさの比較が、どういう意味を持つと私が考えているか、ご理解いただけたであろうか。現代人は過去に比較して、はるかに人知が進んだと考えている。考えていると思う。それなら現にこれまで行われてきたコロナ対策を考えてみよう。まず stay at home.ヒトに会うな。やたらに外に出るな。もちろん病気を移し、移されるからである。難しいことはどこにもない。部屋を換気せよ、むやみに集まるな。これも理解が困難なことではない。
ハテ、「進歩した」のは、どこなのか。二百年前でも似たような対策を採ったのではなかろうか。当時との違いを言い立てればいくらでもあろうが、予防の基本は変わらない。手を洗って、あれこれ清潔にして、不要な人に会うことをしない。おそらく日本人なら以前からやっていたかもしれない。アマゾンの密林には、いまだに外部との接触を断って放浪している部族がいるという。疫病を避けるためだという。参考になりますね。
私はヒトが集中するから都市を作るなとか、わからないことを増やすだけだから、研究なんかするなと言うつもりはない。どちらにしても限度がありますよ、と述べているだけである。そこを見切ってますか、と言いたい。原発のゴミ問題は片付かない。理由は明瞭で、原発エネルギーから得た東京の秩序活動は、原発のゴミという形の無秩序で放出されているからである。それを石油に変えたところで、原理的には問題は片付かない。石油が燃えて、炭酸ガスと水になり、それが無秩序に動きだす。温暖化とはそのことじゃないか、と思ったりする。とりあえずは化石燃料の使用量が問題視されているが。
根本問題は大都会に代表されるヒトの秩序志向、あるいは秩序嗜好にある。その根源はヒトの意識という秩序活動にある。じゃあどうするか。秩序を高めなければいい。それが真の省エネである。合理的、効率的、経済的にものごとを進行させる。それ自体の非合理性、非効率性、非経済性は、コロナ騒動でよくわかったのではないか。
養老孟司(ようろう・たけし)
1937(昭和12)年、鎌倉生れ。解剖学者。東京大学医学部卒。東京大学名誉教授。心の問題や社会現象を、脳科学や解剖学などの知識を交えながら解説し、多くの読者を得た。1989(平成元)年『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞。新潮新書『バカの壁』は大ヒットし2003年のベストセラー第1位、また新語・流行語大賞、毎日出版文化賞特別賞を受賞した。大の虫好きとして知られ、昆虫採集・標本作成を続けている。『唯脳論』『身体の文学史』『手入れという思想』『遺言。』『半分生きて、半分死んでいる』など著書多数。
養老孟司
株式会社新潮社「新潮」のご案内
http://www.shinchosha.co.jp/shincho/
デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。
【購読のお申し込みは】
https://www.shinchosha.co.jp/magazines/teiki.html
関連ニュース
-
池上彰とパックンが選ぶ名演説15選 日本からは玉音放送と安倍元首相の「希望の同盟へ」を選出 新書『世界を動かした名演説』に注目[新書ベストセラー]
[ニュース](外交・国際関係)
2023/10/21 -
「アルスラーン戦記」ついに完結でベストセラー1位! 読者からは31年に及ぶ刊行を人生に重ねた感激の声
[ニュース](日本の小説・詩集/日本史/タレント本/SF・ホラー・ファンタジー/ステージ・ダンス)
2017/12/23 -
「世界一受けたい授業」で話題 川村元気初翻訳の大人向け絵本『ぼく モグラ キツネ 馬』がベストセラー1位
[ニュース](絵本/家事・生活/家庭医学・健康)
2021/09/25 -
「ガラクタ」は人生の宝物である 五木寛之が提唱する「捨てない生活」[新書ベストセラー]
[ニュース](自己啓発/家庭医学・健康)
2022/02/05 -
養老孟司、愛猫との別れから一年 「まる」への想いを語る
[ニュース](哲学・思想)
2022/02/21