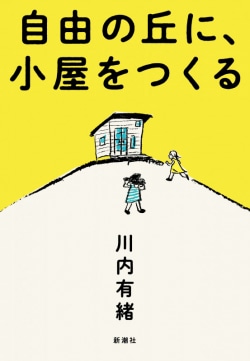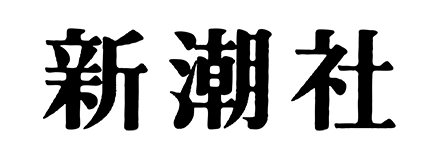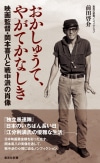様様々な紆余曲折を経て完成した小屋でくつろぐ著者
Yahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞受賞者・川内有緒が執筆したエッセイ『自由の丘に、小屋をつくる』(新潮社)が刊行された。
40代で母親になって、「この子に残せるのは、“何かを自分で作り出せる実感”だけかも」と考えた著者。コップに水をいれるだけでこぼしてしまうほどの不器用にもかかわらず小屋作りを始める。
コスパ・タイパはフル度外視。規格外の仲間たちと手を動かすほどに「世界」はみるみるその姿を変えていき……。
著者と、夫のイオ君と、幼い娘・ナナの三人にとって、人生で一度きりの“不確かな未来を生きるための旅”を記した、読む者の心と価値観を揺さぶるドキュメント。その一部を試し読みとして紹介する。
***
イオ君は「俺の一〇年をこの子に捧げる」宣言を着実に実践した。飲み会に行くことはなくなり、夜半にナナがふにゃふにゃと泣き始めるとガバッと飛び起きた。週末にはベビーカーを押して公園に行き、日向ぼっこをさせ、家に戻ると適温のミルクを用意した。彼は生来、酷寒の日に半袖で出かけて風邪をひいて帰ってくるような人間だが、ことナナの世話に関しては、小さな赤いポツポツを見つけた瞬間に薬を取りに走るような丁寧で繊細な男だった。なんとこんなに子育てに向いている人だったのか、とわたしは日々是驚愕。さなぎから蝶に変わるようにメタモルフォーゼしたのかと思ったが、繊細さを発揮できるのは、ナナに関連することに限定されているようだった。
平日の昼間の子育てと家事はわたしが担当だ。社会のリズムなどおかまいなしに、いまや赤ちゃんとともに寝て赤ちゃんとともに起きる生活である。授乳をして、着替えさせる。ナナを抱いて公園に行き、家に帰るとお昼寝をさせる。ナナからはいつも甘酸っぱい良い香りがした。
一見すると平穏な時間なのだが、ゲップをさせ忘れただけで命が脅かされるかもしれない赤ちゃんとの生活というのは、実はなかなかの緊張感がある。気が休まるのは、家にいてナナがスヤスヤと昼寝をしているときくらいだ。さらに家事の量が以前の五倍くらいになった。服についたシミをこすり、洗濯機を回して大量の服を干し、大量のオムツを捨て、買い物をして、掃除機をかけ、洗濯物を取り込み、夕飯を作って食べる。それらをナナが寝ている間、もしくは機嫌よく過ごしているときにしないといけないのだ。
なんとまあ忙しいことか。
娘が生まれるまで、家事は仕事の合間に行う息抜き的な活動だったが、いまや無数の細々したタスクがざぶーん、ざぶーんと寄せては返す波のよう。波間で溺れそうだ。
一方、ナナはまいにち驚くべき変化を遂げていた。この間まで視点が定まっていなかったのに、わたしを見ると、にこっと笑いかけてくれる。「すごいねえ! すごいねえ!」とわたしたちは大いに感動した。
あまり話し相手もいない静かな生活の中で、わたしはなんでもかんでもナナに話しかけた。自分が感じていること、今日やりたいこと。電車の中だろうとスーパーの中だろうとおかまいなしに。
「今日は行ったことのない公園に行こうか。それともおばあちゃんちに行くのもいいかもね。おばあちゃんが、ナナのために服を作ってくれたって」
そんなときナナは、あーあーとかむにゃむにゃとか言葉の原型のようなものを発した。なかなかの聞き上手のようだ。
ずっと一緒にいよう。ずっと、ずっと。
当たり前にそう思っていたのだが、現実には「ずっと」は続かなかった。
ある日、子育てしながらばりばり働く先輩ライターが言った。
「フリーランスの夫婦には子供が〇歳のときしか保育園に入れるチャンスはない。最悪、四歳まで待つ覚悟がないなら、いまこそ全速力で保活に向かって直進あるのみ!」
ほえー、なるほど、そういうものなんですねえ。
ということで、ナナが生まれてたった一ヶ月半後、保育園への入園を申しこみ、競争社会へ復帰することを決意した。
無事に区立保育園への入園を許可する通知が届いた夜、わたしはメソメソと泣いた。あれだけ、家事も育児も大変だとか言っていたわりに、ナナと離れた時間を想像するだけで猛烈に寂しかった。そこで、保活成功の祝杯をあげるかわりに、勤め人時代の一〇歳年下の後輩に電話をかけた。彼女も子どもを保育園に預けて仕事に復帰したばかりなので、「寂しいよねえ、一緒に泣こう、うわあんん!」とお互いの傷を舐め合おうと思ったのだが、逆に「なにセンチなことを言ってるんですか! 世の女性たちは保活がうまくいかなくて仕事が続けられず泣いてるんですよっ! その人たちの分までしっかり働いてくださいっ!」とお叱りを受ける結果になった。はいっ、すみません……。
その保育園は、高いビルの谷間にあり、日の当たらない狭い園庭と年季の入った建物がわたしのイメージとは違っていたけど、先生たちはプロフェッショナルで、不満はなかった。
最初の一週間は保育園に娘を送りに行った帰りにまたくよくよと泣いていた。そんな自分が自分でも気持ち悪かった。わたしは自他共に認めるドライな女で、恋人にも友だちにもベタベタするのが苦手だった……はずである。その分、多くの人と付き合える間口の広さだけはあり、年齢、国籍、人種、職業、趣味、性的指向問わずいろんな友人がいた。ずっと自分自身のために時間とお金を使い、友人と遊び回り、いつでも思い立ったときに旅に出たり、そこら辺で知り合った人と酔い潰れるという生き方しか知らなかった。そんなわたしだから、ナナが生まれるまで、特定の誰かに愛を注げるのか、そもそもそれだけの愛情の泉が自分のなかにあるのかすらも、わからないでいた。
しかし、娘が人生に登場して以来、何かが不可逆的に変わった。時間とお金のほとんどを娘のために使い、これまで誰にも感じたことのない激烈な愛情を覚えていた。ナナ、大好きだよー、生まれてきてくれてありがとおおおお! と飽きずに話しかけた。そんなべタついたスライムみたいな愛情剥き出しのわたしをよそに、ナナのほうはあっさり新生活に順応した。保育園に着くなり笑顔で保育士さんたちのところに高速でハイハイしていく。そして、一〇ヶ月になる頃には「バイバイ」という言葉まで覚え、手を振ってくれた。
ああ、娘は〇歳にしてもう個人としての社会生活を始めているんだなあ。
今日も元気でね……とわたしも手を振って家路に就く。
ナナがいなくなった部屋は静かで落ち着きがあり、心の平穏を取り戻して仕事に集中できた。これはこれでほっとする。人間とはかくも複雑に入り組んだ感情を持つ生き物なのだと身をもって知った。
*
ナナを保育園に送ったあと、わたしとイオ君はよく近所のドトールでコーヒーを飲んだ。共働きの我々にとっては、貴重なコミュニケーションタイムでもある。
その日わたしは、イオ君に提案したいことがあった。
「ねえねえ、自分たちで小屋を作るってどう思う?」
「え、小屋? 今度は田舎に引っ越したくなったの?」
彼はカフェラテを飲みながら首をかしげた。
わたしは以前から「そのうち家族でアラスカに行こう」など、思いつきで物事を提案してきた。それに対して彼はわりときちんと話を聞いてくれた。
「そうじゃないの」と答えた。
―自分たちで小屋を建てたい。
理由は、分かりやすいものと、分かりにくいものの両方があったので、まずは分かりやすいものから。
「だって、ナナには田舎がないんだよ。自然の風景も田舎の生活も知らないで育つなんて、ちょっとかわいそうじゃない?」
「そりゃ、そうだ、俺も小さい頃は北海道のおばあちゃんちに行って楽しかったな」
「でしょう。わたしも福井のおばあちゃんちに毎年泳ぎに行ってた。いとこたちと遊ぶのも楽しかった。でもナナにはそういう場所がいまのところないでしょう」
わたしの母は渋谷区の繁華街に、イオ君の両親は千葉の住宅街に住んでいる。そして、わたしたち家族が住んでいるのは目黒駅近くにある築四〇年の賃貸マンションである。メインの遊び場は、謎の白い泡が浮かんだ川に沿った緑道か、小さな児童公園だった。
一歳になったナナは早くも言葉を操るようになり、「あっち、しゃんぽ」、「ママ、ちちご(イチゴ)」、「あんよ、かゆい」などと自分の意思を伝えてくる。行きたい方向に一歩ずつ歩みを進め、食べたいものを手掴みで食べた。彼女はすでに赤ちゃんではなく、ひとりの人として周囲にある全てを吸収しようとしていた。このまま都会のど真ん中だけしか知らずに育っていって良いのだろうか?
「あれ、でもさあ、キャンピングカーで地方を巡るんじゃなかったっけ?」
イオ君は首をかしげた。そういや、そうだった。
「あー、それね。やめた」
妊娠中は、「キャンピングカーを買って日本中をめぐりながらノマドライフしたい」などと言っていた。
しかし、二四時間フルサポートが必要な小さな生き物と一緒に生活をしてみると、狭いキャンピングカーで移動し続けるなんて無理がある。ああ、あの頃のわたしは子育てについてなにひとつわかってなかった。キャンピングカー、やめやめ!
それよりも、思ったのだ。旅という断片的な風景ではなく、いつまでもぶれることのない原風景──体の中心にどんと据えられた柱のようなもの──が、まずは必要なんじゃないだろうか。ふと思い出すだけで濃い自然の香りとそよ風を感じて、気分が良くなるような心の風景。わたしにとってそれは、父の実家があった福井の海辺の集落であった。もう行くことがほとんどなくても、あの海の風景を思うだけで、いまも穏やかな気持ちになる。
別荘を買うのではダメなのかと聞かれたら、それはダメだった。あくまでも「自分たちで作る」という部分もまた重要なポイントだった。
「あのね、机がきっかけなんだよ」とわたしは言った。
こちらが、わかりにくい方の理由である。
話は少し前に遡る。
この頃のナナは、高さ一〇センチくらいのミニサイズの椅子に座ってご飯を食べたり、絵っぽいものを描いたりするようになっていた。そろそろ娘用の机を買わなければと思った。
即座に「子ども用 机」とネット検索を始めると、画面にはたくさんの机がずらっと並んだ。
木のぬくもり、いいかも。
高さ調整はできた方がいいよね。
引き出しはなくてもいいか。
何度目かのクリックのとき、ふっとひとつの考えがよぎった。
そうだ、自分で作るってどうだろう? 板と足を組み合わせるだけだから、そんなに難しくないのかも。しかし、次の瞬間にはこう考えた。え、マジで作る? いや、むり、むり。簡単そうとはいえ、具体的な作り方は想像すらつかないし。
わたしは自分でも信じられないくらい手先が不器用で、洗濯物を畳むことすら苦手だった。中学校の家庭科は堂々たる「一」で、エプロンでもパジャマでもわたしが作ると、シャキッとしないものができあがった。手を抜いていたならまだしも、一生懸命やっても「一」なんだから絶望的である。こんな人間なので、これまで何か欲しいときには「買う」以外の選択肢はなかった。
再びパソコンの画面に目を移した。画面には夥しい数の机の画像が並んでいた。まあ長く使うわけでもないし、なんでもいいか。
いや、本当になんでもいいのだろうか?
実は、もう何年も前から、自分の暮らしに対して漠然とした不安を覚えていた。たくさんの物に囲まれ、それらを買うために懸命に働く、そんな暮らしである。
一九七二年生まれのわたしが子どもから大人になったのは、大量消費が日本全国で礼賛された八〇年代から九〇年代で、その仕上げのように二〇代の六年間をアメリカという大量消費の総本山で過ごした。アメリカでは週末になると、フライドポテト専用の揚げ機やチェス盤に早変わりするテーブルなど、人生で五回くらいしか使わないものを買い求める人々でショッピングモールは混雑していた。懸命に働き、何かを買い求め、不必要な物をガレージに溜め込む。それが幸せへの近道だとばかりに。
そんな価値観に強烈な待ったをかけたのが、東日本大震災だった。
あのとき、自分の無力さをはっきりと自覚した。わたしは何も生み出すことができず、消費者としての生き方しかしらない。服も縫えないし、トマトの育て方も知らないし、テントすら張れない。大学院まで出て海外で仕事をしてきたわりに、何か大切な能力を身につけないままに生きてきてしまったのではないかと思うと心底怖くなった。
ナナは、どんな生き方をするのだろう。目の前でニコニコしながら指をしゃぶる小さな子。まだ大きくなった姿なんてまったく想像がつかないけれど、ああ、なにはともあれ、幸せになってほしい、もう絶対的になってほしい。そう強く願えば願うほど、最初は小さな点にすぎなかった「暮らしの不安」というシミは、大きく、黒く広がっていった。
そんな事を考えながらも、わたしはまた別の机の画像をクリックした。
まったく子育てって、本当にいろいろなものが必要でうんざりするなあ。やっぱりメルカリで買った方がいいのかも……。別の机の画像をクリック。
テレビでは、毎日のように不穏なニュースが流れている。集団的自衛権の行使容認、景気後退、テロ、相次ぐ地震、漂流するプラスチックゴミ、温暖化、そして収束を見せない福島第一原発事故の放射能問題。
わたしたちは、どうやって彼女を守り、なにを彼女に授けてあげられるだろう? どうすれば彼女はこの時代を生き抜いて、幸せになれるのだろう。机が映った画面をスクロールする手はいつの間にか止まっていた。
-
- 自由の丘に、小屋をつくる
- 価格:2,420円(税込)
やっぱり机を作ろう。
奇妙な論理の飛躍なのはわかっている。しかし、わたしがいま望むのは、「ものを買う」以外の選択肢を持つことだ。わたしが娘にしてあげられるのは、そういう種類のことのような気がした。別に「丁寧な暮らしを」という話でもなかった。ただ、わたしたちは自分で何かを生み出すことができると信じたかった。
いいじゃん、不器用上等だ。やってみようじゃないか。作り方がわからなければ、習えばいい。
わたしは机を作る。
そう想像するだけで、ずっと気になっている人に会いに行くようなときめきがあった。机の後は椅子やベンチも作ってみたい。妄想はどんどん飛躍していき、その数分後には、そうだ、いつかは小屋を作ろうと思いついた。
もし、この不器用で面倒くさがりのわたしが「小さな家」という暮らしの基盤を手作りすることができたなら、どこかに置き忘れてきた生活の知恵と技術を学ぶことができるかもしれない。完成の暁には、娘はやればなんでもできるという精神になってくれるかもしれない。それは、この困難な時代に、生きる力として彼女に寄り添ってくれる気がした。
すべては「かもしれない」に過ぎないが、その考えは突如としてわたしをとらえて離さなくなった。
「……というわけで、セルフビルド、つまりは自分たちで小屋が作りたいの」と長い話を締めくくった。わたしのカフェラテのカップは空っぽになっていた。
なるほどー、とイオ君は頷いて即座に答えた。
「それ、いいね! 楽しそうだ。やろうよ!」
川内有緒
ノンフィクション作家。1972年東京都生まれ。映画監督を目指して日本大学芸術学部へ進学したものの、あっさりとその道を断念。行き当たりばったりに渡米したあと、中南米のカルチャーに魅せられ、米国ジョージタウン大学大学院で中南米地域研究学修士号を取得。米国企業、日本のシンクタンク、仏のユネスコ本部などに勤務し、国際協力分野で12年間働く。2010年以降は東京を拠点に評伝、旅行記、エッセイなどの執筆を行う。『バウルを探して 地球の片隅に伝わる秘密の歌』(幻冬舎)で新田次郎文学賞、『空をゆく巨人』(集英社)で開高健ノンフィクション賞、『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』(集英社インターナショナル)でYahoo!ニュース│本屋大賞 ノンフィクション本大賞を受賞。その他の著書に『パリでメシを食う。』『パリの国連で夢を食う。』(以上幻冬舎文庫)、『晴れたら空に骨まいて』(講談社文庫)、『バウルを探して〈完全版〉』(三輪舎)など。ドキュメンタリー映画『目の見えない白鳥さん、アートを見にいく』共同監督も務める。
株式会社新潮社のご案内
1896年(明治29年)創立。『斜陽』(太宰治)や『金閣寺』(三島由紀夫)、『さくらえび』(さくらももこ)、『1Q84』(村上春樹)、近年では『大家さんと僕』(矢部太郎)などのベストセラー作品を刊行している総合出版社。「新潮文庫の100冊」でお馴染みの新潮文庫や新潮新書、新潮クレスト・ブックス、とんぼの本などを刊行しているほか、「新潮」「芸術新潮」「週刊新潮」「ENGINE」「nicola」「月刊コミックバンチ」などの雑誌も手掛けている。
▼新潮社の平成ベストセラー100
https://www.shinchosha.co.jp/heisei100/
関連ニュース
-
第21回女による女のためのR-18文学賞 「最終候補」全5作品を若手男性社員が読んでみた
[特集/特集・インタビュー](日本の小説・詩集)
2022/06/01 -
井上荒野×斎藤由香×井上都「父と私――井上光晴、北杜夫、井上ひさし」 『ごはんの時間 井上ひさしがいた風景』(井上都著)刊行記念トーク
[イベント/関東](エッセー・随筆)
2017/01/12 -
『日本・破綻寸前』藤巻健史氏の「お金の守り方」に注目集まる
[ニュース](一般・投資読み物/タレント写真集/金融・ファイナンス/教育学)
2020/03/28 -
原田マハ×高橋明也「オルセー美術館、私だけの楽しみ方 ~印象派からナビ派まで~」
[イベント/関東](建築)
2017/04/03 -
中川淳一郎×おときた駿「音喜多さん、東京都議会どうなってるの!?」 『バカざんまい』(中川淳一郎著)刊行記念特別公開対談
[イベント/関東](ノンフィクション)
2016/09/13