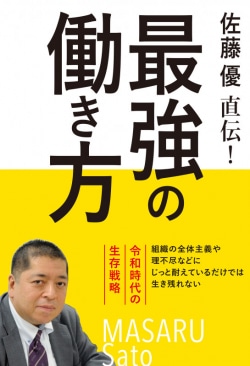『佐藤優直伝! 最強の働き方』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
いまの会社を辞めて転職したい? やめたほうがいい、と佐藤優が言う理由
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
20年ほど前なら、真面目に働いていさえすれば、現在の生活も将来の展望もなんとかなるという見通しが立ちました。
しかし、非正規労働者の増加、少子高齢化、年金制度に対する不安感などを引き合いに出すまでもなく、現在の状況が楽観視できるものでないことは火を見るより明らかです。
だとすれば必然的に、「働き方」について改めて考えてみることが必要となるはず。働き方をめぐる問題を現実的にとらえ、解決の方策を見出す目を養わなければならないわけです。
そこで参考にしたいのが、『佐藤優直伝! 最強の働き方』(佐藤 優 著、自由国民社)。
元外務省主任分析官という実績を持つ作家である著者が、豊富な知識と経験をもとに働き方についてのさまざまな考え方を明らかにした書籍。
きょうはそのなかから、転職について触れた第4章「会社を辞めてはいけない」に焦点を当ててみたいと思います。
ここで著者は、いまの仕事を辞めて転職しようと思っている人に対してショッキングな主張をしています。「やめたほうがいい」と。
果たしてその理由とは、どのようなものなのでしょうか?
自己都合で転職した場合、賃金が3割下がることも
転職は、収入が3割下がるのが現実。著者は、そう見ているのだといいます。つまり2回転職をすると、約半分になってしまうということ。
しかも給与は同じでも、労働強度はそれだけ強まることに。
3回目以降は、それからそんなに下がらない。だから1回目、2回目っていうのは、3割ずつ下がるっていうことを経験則で見ておいた方がいい。そういう訳で転職するときは、よーく考えないといけない。(121ページより)
もちろん、いまより条件がよくなることも「例外的には」あると認めてはいます。
ただしそれは、転職先の会社幹部が能力を評価してくれて、「こういう条件で」というかたちで引っぱってくるときの話。
そういう場合はチャンスだと考えることができるでしょうが、自分のほうから自己都合で転職したのであれば、労働強度が強まって同じ賃金か、労働強度が強まって賃金が若干下がるか、労働強度は同じで賃金が3割下がるかのいずれかになるはず。
著者の見たところでは、それが実態だというのです。(121ページより)
尊敬できる先輩が1人もいなければ、その会社からは逃げるべき?
自分の会社がブラック企業だと思う人は、決して少なくないかもしれません。
しかし若いうちは、ブラック企業なのか、それとも単に教育が厳しい企業なのか、わかりにくいものでもあります。
そのときの判断基準の1つになるのは、自分より上の人を、5年ずつ輪切りにしていく。5年、10年、15年、20年、25年まで。(122ページより)
つまり、もしもいま25歳だったとしたら50歳までの人、30歳だったら55歳までの人と、輪切りにしたなかで考えるべきだというのです。
そして、そのなかに尊敬できる先輩は1人もいなかったとしたら、その会社はブラック企業だと考えていいのだとか。
逆に、そのなかで何人か尊敬できる人がいたなら、その会社にいる意味があると考えたほうがいいそうです。(122ページより)
相談できる“ななめ上の人”をつくったほうがいい
社会に出て企業に勤めると、セクハラやパワハラなどいろいろな問題が起こるものです。だとすれば、そんなときはどうやって問題を解決すればいいのでしょうか?
この問題に関して著者は、直属の上司に相談すべきではないと主張しています。
直属の上司っていうのは、相談されたら困る場合があるわけです。いくらその人の身になりたいとしても、問題にされたくないから。
できれば同じ会社、そうじゃなければその会社を辞めた人でもいい。かつて上司だった人に相談するといい。ななめ上の人で相談できる人をつくった方がいい。(140~141ページより)
“ななめ上の人”であれば直接の利害関係者ではないため、人事の査定や責任に関わらないということ。
また、そういう人は親身になって相談に乗ってくれるし、客観的なアドバイスをもらえる可能性も高いというのです。(140ページより)
見返りを求めずに、助けてもらった経験を持っているか?
これからは右肩下がりの時代であり、経済状況も実感としてなかなかよくなりません。
勤務評定が厳しくなる時代においては、自分だけで問題を抱え込んでいると、メンタル面をやられてしまう危険性すらあります。
そうしないようにするために、一番重要なのは、話ができる友だち、できればななめ上のところで、信頼できる友だちを持っていることだ。(146ページより)
ポイントは、友だちの選び方。
20代、30代の前半くらいまでに、なにか見返りを求めることなく、他の人から助けてもらった、応援してもらったという経験を持っている人であることが重要だというのです。
なぜならそういう人は、自分の受けた経験を他の人に返すことができるから。
逆にそうした経験があまりない人は、なかなか他人に対しても、なにかをしてあげることができないわけです。(146ページより)
自分の能力だと勘違いしていたらいけない
問題を解決しなければならない場合、その方法はいろいろあるでしょう。
とはいえ、かつてのような労働運動や社会主義運動では、問題解決の処方箋を提示できないという現実もあるわけです。
私は超越的なるもの、宗教っていわなくてもいいが、合理性を超えたところに対する感覚が重要になってくると思う。 聖書の『使徒言行録』の中ではパウロが、「受けることよりも与える方が幸いである」とイエスがいったので「あなたたちも、そのようにしてください」という説明をしている。
受けるより、与える方が幸いだ。与えることができるようになるためには、自分が何か受けているものがあるわけだよね。その受けたものっていうのは、自分の能力で勝ちとったと勘違いしたらいけない。(148ページより)
つまり、いろいろな人たちに助けられているわけです。
そして、その根源が、人間の命の力だということ。そういう感覚を磨く機会をつかめるかどうかが、非常に重要になってくると著者は記しています。(147ページより)
テーマがテーマであるだけに、シビアな話も少なくありませんが、著者の経験が豊富に盛り込まれているため読み応えも抜群(ドキッとするようなトピックも)。
各項目がコンパクトにまとめられているところも魅力のひとつです。これからの働き方について考えてみるために、ぜひとも読んでおきたい一冊だといえるでしょう。
Photo: 印南敦史
Source: 自由国民社