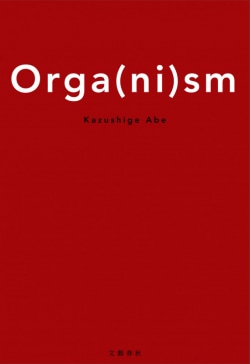『オーガ(ニ)ズム』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
現実への対抗措置の発動
[レビュアー] フィクショナガシン(ライター)
著者初の三部作だ。
『シンセミア』『ピストルズ』に続く最終作。もっとも、一冊ごとに完成した作品である。私らしくありきたりな言い方をすれば本作だけを読んでも全く問題ない。本書から読み始める令和の阿部和重読者もいるだろうがおそらく驚くほどスイスイ読めるのではないか。伏線の回収にだけ奔走するのではなく作品単位で面白く、初見さん歓迎の小説だからだ。あまりに快適な読書であるため何者かによって操られているのではと不安になるかもしれないほどである。巨大な風呂敷が鮮やかに広がるプロセスとも呼び得る前二作との濃密な連携ぶりが、本書ではさらに四次元的に拡張する驚きを体感する機会となるだろう。
古株の平成の阿部和重読者にとっては、著者の最新型を目の当たりにするわけだが、同時に初期の作品群、あのテンションを久々に感じとるにちがいないとも思う。私見では著者はその最初から、小説を一種の装置と見なし、様々な工夫を自作に仕込んできた。主人公の主体が途中で入れ替わり複数であるかのように分裂したり、また全体を宙吊りにする強烈なオチを仕掛けることで読者を幻惑したりした。ルールに満ちた言葉の世界、二次元でしかない小説の世界を巧妙に操ることで、「読者」という三次元の現実に対し、果敢に働きかけをしてきた。むろん言うまでもなく小説は言語で構築されたフィクションの世界であり、絶対に現実ではありえないことが保証されている。現実はいつも著者名を境界とした本の外側にあり、あくまで小説はその現実へ間接的に働きかけるだけだった。
しかしながらある時点から、「実際に起こり得るのではないか」と思える世界を著者は書くようになってきた。初めての連載小説『プラスティック・ソウル』(1997-2000)において登場人物達が大仙陵古墳(仁徳天皇陵)に忍び込もうとしたあたりだろうか。三部作に召喚されもする今世紀初の作品『ニッポニアニッポン』(2001)では、佐渡島のトキ保護センターに忍び込む「理論」と「実践」が描かれたし、同様に三部作に寄与する初めてのケータイ小説『ミステリアスセッティング』(2006)にはすでにスーツケース型核爆弾が持ち込まれていた。そして絵空事のようでありながら、現実に十分、起こり得るこのような事態は三部作の世界観に引き継がれている。実在の町、山形県は東根市神町の戦後史にフィクションを練り込み、膨らました作品が三部作の第一作『シンセミア』(1999-2003)である。二作目『ピストルズ』(2006-2009)は、著者の生まれた昭和四十年代半ばからの時代を、やはり神町で暗躍する菖蒲家の一子相伝のメソッドにまつわるエピソードを中心に据え、長大な手記の中に流し込むことで、昭和後期の象徴天皇制の暗喩と共に特殊な角度から描き出した。最終三作目である本作(2016-2019)も同じ線上にあり、かつ前作の菖蒲家の存在感をさらに世界規模に拡大した。加えて国賓来日などの重要な政治的舞台でのスーツケース型核爆弾によるテロの可能性という、やはり今となっては十分あり得る悪夢をも描き出す。フィクションの世界に「極端だがあり得るかもしれない」現実を参入させるのが、『プラスティック・ソウル』以降、もしくは三部作及びそこに取り込まれ、共有された数々の作品群の特徴だと思われる。あるいは同じことだが著者が三部作に着手して以降、現実のこの世界は荒唐無稽なフェイクニュースが飛び交う、それこそ悪夢に似た世界に変貌しつつあり、もはや何を書こうが「極端だがあり得るかもしれない」という説得力を持ってしまっているとも言える。そう、我々はこの二十一世紀に、滑稽世界をいつの間にか実現してしまったのである。本作が初期の阿部和重的な悪ノリ、笑いに満ちたやんちゃな発想を遠慮なく再導入したのも、現実世界の滑稽化に即応するためではないか。CIAのスパイと阿部和重との珍問答は本当に最高である。
「CIA」「阿部和重」と書いたが、現実に存在する固有名の反復が、本作を極めて賑やかなものにしている。中でも「阿部和重」は家族構成から職業、作品歴、生年、またその言動などが読者に本人を想起するよう積極的に促している別格の存在だ。もっとも本作から突如として出現したわけではなく、布石はすでに第一作で打ってあり、「阿部和重」という固有名は何度となく登場している。しかしその時点ではメールや別人の「なりすまし」によってであり、本格参入というよりも物語に不吉な印象を与え、痕跡を残す程度にとどまっていた。本作ではそんな洒落たことはせず、出ずっぱりだが、むろん私小説とは異なるし(メインの舞台は新首都となった神町でさらに極端に仮構されている)、完全なフィクションである。にもかかわらず、錯覚にすぎぬとわかっていても、本の外側の現実がもはやこんな世の中である以上、「あり得るかもしれない」という思いを読者は捨てきれず、その固有名は本の外側へと越境し、現実の阿部和重とどこかで繫がっていると思い続けるだろう。そもそも、錯覚とわかっていても信じることができるのが小説のフシギさであろう。
本作では、阿部和重の自宅にCIAのスパイが転がり込んでくることから玉突きのようにストーリーが動き出し、東京から神町へと途中から場所を移す。前二作の聖地巡りをしながらも、すでに述べたようにそこは新首都になっている。主な現在時は二〇一四年のオバマ米大統領来日に合わせてあるが、時に大きくその時間枠を逸脱する。オバマの来日時にスーツケース型小型核爆弾の実際の使用を阻止するために繰り出されるCIAのほとんど屁理屈のような様々な「読み」に阿部和重は翻弄され続けるが、最後までそのアメリカ人のスパイと付き合う。スパイ達は、ほとんど阿部作品の理想の「読者」と言えるかもしれぬほどであり、刻々と変貌する事態を「読む」ことに熱心である。
バラク・オバマ米大統領はその登場こそ本作まで待たねばならなかったが、第一作の最重要ワードでもある「若木山」にまで繫がっていることが明かされる。彼自身その名をつぶやくほどである。神町ファミリーの一員と呼んでもはや構わないほどだ。初期の阿部和重作品は、ひたすら純度百パーセントのフィクション人間達がストーキングしたり、卑猥な行動をしたり、忍び込んだりしていたが、指摘したようにある時点から忍び込むことよりも(いや、本作でもいつもながら忍び込んでいるが)、作品内に現実の人物や実在する固有名を遠慮なく誘い込み、純度百パーセントのフィクション人間達と見事に共演させてしまう。日々、報道で目にする世界的固有名や政治経済的ニュースの数々は、阿部和重のために素材を提供し続けているのではないかと錯覚したくなるほどである。もっとも、著者は受け身では全くなく、現実(未来)を変容させるための、極めて詳細な芸術文書としてこれを書き残したと私は思う。現実への積極的な加担の姿勢は、本作のラスト付近、八百五十一頁での衝撃的な「予言」をさらにリアルなものにしている。