『一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリート』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
「天才語」を紐解いた稀有な作品 『一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリート』
[レビュアー] 柳川悠二(ノンフィクションライター)
文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(解説:柳川 悠二 / ノンフィクションライター)
夏のオリンピックを私が取材するようになったのは、二〇〇〇年のシドニーからだからちょうど二〇年になる。その頃すでに、本書の主人公で、陸上・やり投げの第一人者だった溝口和洋は表舞台から消えていた。彼がパチプロとして、生計を立てていた時代である。
二〇〇四年のアテネ五輪の金メダリストであるハンマー投げ・室伏広治の登場以前に、体格とパワーで勝る欧米人に絶対的な利がある投擲種目で、世界を凌駕する日本人がいた。その史実は知っていても、溝口の人となりに関しては、スポーツ取材をメインとしてきた私もまるで知らなかった。
その理由は、溝口自身が大のマスコミ嫌いで、やり投げに賭けた人生を積極的に語ろうとしなかったことにある。同時に、アフロヘアで競技場に現れたり、タバコを吹かしながら試技前のストレッチをしたりするようなアスリートを、大手新聞やTV局の記者も敬遠したのだろう。
日本選手権の前夜に女を抱き、寝不足のまま競技場に現れたというエピソードなど、今の時代なら週刊誌のかっこうの餌食となろうが、不勉強な質問でもしようものなら鉄拳が飛んでくる取材対象がいたら、私も物怖じしてしまって簡単には近づけなかったかもしれない。
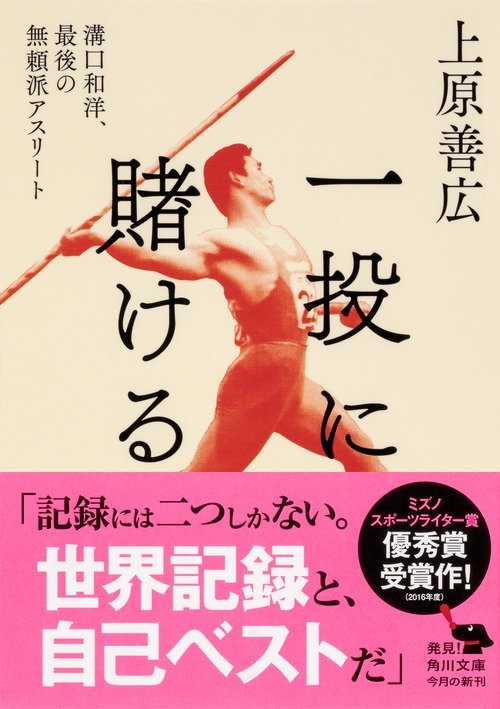
「天才語」を紐解いた稀有な作品 『一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アス…
溝口はロサンゼルスとソウルの両五輪に出場したあと、一九八九年に日本人として初めて賞金レースである「ワールド・グランプリ」(WGP)シリーズに参戦。その初戦「ブルース・ジェンナー・クラシック」(八九年五月二七日)において、世界記録にあと六cmと迫る「八七m六〇」の自己新をマークする。これは、三〇年以上が経過した現在も破られることのない日本記録である。
八九年のWGPシリーズは総合優勝こそかなわなかったものの、溝口は二位に輝き、この快挙によって溝口の挑戦に懐疑的だった国内では、手のひらを返したように世界記録更新へ期待の声が高まっていく。
日本人として未知の世界に飛び込んでいくアスリートというのは、いつの時代も孤高な存在だ。メジャーリーグに挑戦した野球の野茂英雄やイチローしかり、サッカーの中田英寿しかり。私がここ数年、取材に力を入れてきたゴルフの松山英樹にしても、知ったかぶった質問には露骨に嫌悪感を示すため、彼をインタビューする際は、いつも以上に準備に力を入れて、緊張感を持ちながら臨まなければならない。
聞きかじった情報だけで記事にする記者に、人生を賭けた競技に対する想いや細かな技術論を語ったところで理解できるはずがないし、核心に迫れるはずがない。そうした不信感が次第に開拓者の口を貝にさせるのだろう。
ノンフィクション作家の上原善広は一八年という、実にオリンピック四回分以上の歳月をかけて、無頼派で、孤高のアスリートの先駆者である溝口とつかず離れずの関係を築く。胸襟を開かせ、溝口の世界一の投擲技術と、その生き様を『一投に賭ける』では活写してゆく。
溝口の一人称で綴られていく本書は、体裁としてはゴーストライターが聞き書きをする即物的な自叙伝に近いのかもしれないが、数時間あまりのやりとりで溝口の哲学を理解できるはずもない。上原は溝口が話す「天才語」を紐解き、まさしく上原に溝口が憑依したかのように描いていく……そんなステレオタイプな比喩も、決して大げさではないほど、本書は上原しか描けないノンフィクション作品として完成している。
それゆえ、ライバルである先輩アスリートを中傷するような表現も散見されるし、国内の陸上競技を管轄する日本陸上競技連盟(JAAF)への批判も飛び出す。愚っ直なアスリートを、愚っ直な作家が描くからこそ、そこに他者への配慮や組織への忖度などはゼロなのだ。
和歌山県白浜町に育った溝口は、生来、負けず嫌いで、自尊心も人一倍強かった。やり投げを始める以前、中学生の頃に、校内でも評判の可愛らしい女子と付き合うことになったが、なぜかすぐに振られてしまった。それが悔しくて猛烈に追いかけてよりを戻せたかと思うと、今度は自ら振ってしまったという。
そして、熊野高校入学と同時に、いよいよやり投げを開始する。もともと身体が頑丈で、肩が誰よりも強かった溝口にとって、やり投げは天性を活かせる競技といえた。高校卒業後もやり投げを続けることを決意し、競技を「極める」ことに注力していく。
本書には次の一節がある。
「私はやり投げを始めたときから、正確には大学生になってやり投げのために生きることを決意したときから、日常生活も含め、全てをやり投げに結び付けてきた。箸の上げ下ろしから歩き方まで、極端にいえばセックスしている最中でも、この動きをやり投げに応用できないかと考え続けてきた」
やり投げは、「全長二・六m、重さ八〇〇gの細長い物体をより遠くに飛ばす」競技だ。しかし、日々の練習においては、やりをひたすらに投げ続けるわけではない。練習の大半は、その土台となる体作りだ。
とりわけ溝口が力を入れたのは、ウエイト・トレーニングだった。地獄のようなトレーニングメニューを自身に課し、骨格で勝る外国人にもひけをとらない肉体を築こうとしていく。
溝口にとって、最初の大舞台は八二年のロサンゼルス五輪だった。満員のスタジアムで残した記録は七四m八二。予選落ちに終わる。
競技場を引き揚げようとしたその時、コーチから罵声を浴び、プライドを傷つけられた溝口は、怒りに震えながら日の丸のついたユニフォームを大会ボランティアにくれてやり、日本選手団が着用するブレザーも、解散式が終わって拠点の京都へ戻る新幹線のゴミ箱に捨てたという。
先述した中学校での短い恋の逸話もそうだが、こうした細かなエピソードこそ、孤高で無頼派のアスリートの人間らしい一面が垣間見える瞬間であり、だからこそ上原も大切に描こうとしたのではないだろうか。
また、第二章「確立」では、溝口のやり投げを構築する投擲の技術と、溝口が自身に課したウエイト・トレーニングの詳細が記されている。体作りの専門書のようにひたすらメニューを列記することで、いかに溝口が自身の肉体を追い込んでいたかが際立つものになっている。
本書を手にする(アスリートではない)一般読者にとって興味の薄い話題にも丁寧に触れているのは、上原自身が元円盤投げの選手で、高校時代に府大会で優勝、大学も大阪体育大学にスポーツ推薦で入学したことが背景にあるのだろう。溝口の理論を後世に残す役割として上原も紙幅を割いたのではないか。
八八年のソウル五輪を前に、やりの規格が変更となり、いわゆる「飛ばないやり」となった。重心が前方へと移り、やりが頂点に達したあと、急激に失速して芝に突き刺さってしまう。要はパワー頼みで記録が出るやり投げから、パワーと共に技術も問われるやり投げへと競技の本質が変貌を遂げた。これが溝口には幸いしたと回想する。
ソウル五輪後、今一度、やり投げの技術を見直し、フォームの微修正に着手する。肩をカチッとキメた状態から全力で助走し、スピードをできるだけキープしたままガニ股の状態でクロス・ステップし、フィニッシュはテコの原理でやりを空中に直線的に放り出していく。身体への負担は大きいものの、それまで培ってきた鋼の肉体が下支えした。
八九年に溝口は自己記録を二年ぶりに更新、そして冒頭のWGPシリーズの「八七m六〇」に続いていく。この記録は、一度は、当時の世界記録である「八七m六八」とアナウンスされ、その後、安物のビニール製のメジャーで再計測となり、記録は改められた。「幻の世界記録」と呼ばれる所以である。
アジア人に対する露骨な差別行為に、誰よりも恨み節をぶちまけたいはずの溝口は、意外にも冷静に受け止めている。その一瞬に、一投にすべてを賭けてきた男には、それが世界記録だろうが、自己記録だろうが、投げ終えてしまえば既に過去の足跡でしかなく、記録となった時には既に歩を前へ進めている、ということなのだろう。
この頃すでに、溝口の身体は限界点に達していた。九〇年のシーズンを前に、右肩の靱帯を損傷し、全力の投擲ができない身体となってゆく。それでも主要大会には出場し続けていたが、七〇m台の低調な記録に終始した。身体はもはやボロボロだった。
溝口は言う。
「やり投げを好きだと思ったことは一度もない。
しかし、やり投げが私の全てだったことは確かだ」
太く短く生きることを信念にしてきた男も、九六年に三四歳で現役を引退する。パチプロに転身し、俗世を離れるように陸上界から忽然と姿を消した……ように思われていた。
実は現役時代の晩年(九四年)から、中京大学でハンマー投げの室伏広治を実質的に指導し、とりわけウエイト・トレーニングを徹底的に叩き込み、室伏の投擲技術を世界一と称されるまで共に磨き上げた。こうした世間の耳目を引く溝口の功績も、本書では実にさらりと描かれているのが、溝口を誰より理解する上原らしい。
それにしても、単行本の刊行までに一八年、文庫化までの時間を含めれば二二年という歳月をかけ、ひとりのアスリートを追うことなど、簡単ではない。もちろん、営利を期待した歳月ではない。上原にあるのは、同じ投擲の選手だった時代からあった、溝口に向ける憧憬の目だけだろう。
最後に個人的な話をするのをお許しいただきたい。私にも二〇年近く追い続けるアスリート(柔道家)がいる。彼は私より二歳下だが、彼の出身地である宮崎で、同じように柔道に励んでいた私にとってはアイドルであり、彼を追うためにスポーツ取材を開始した。シドニー五輪で金メダルを獲得した彼も、今では全日本男子の監督である。溝口とはまったくタイプの異なる、日向を歩き、脚光を浴び続けてきた人物である。
しかしながら、彼を追ってきた二〇年の歳月の果てに何を残せるのか。東京五輪が延期と決まったいま、改めてそうした命題を私に与えてくれたのが、上原善広の『一投に賭ける』である。
二〇二〇年三月
▼上原善広『一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリート』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321909000201/



































