『長く高い壁 The Great Wall』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
浅田次郎が語る、戦争と作家
[文] カドブン
浅田次郎『長く高い壁 The Great Wall』の角川文庫化と火野葦平『麦と兵隊・土と兵隊』の復刊を記念して、浅田次郎さんのインタビューをお届けします。
*「小説 野性時代」2016年9月号に掲載した、「長く高い壁」連載開始時のインタビューを再編集しました。肩書等は当時のものです。
◆ ◆ ◆
『日輪の遺産』や『終わらざる夏』など、戦争をテーマにした小説を多数発表されてきた浅田次郎さん。
待望の新連載は、日中戦争という苛烈な時代を生きた従軍作家の物語です。
作家にとって、また浅田さんにとって、戦争とはなにか?
戦時中の日本文学について多くの論文を発表されている若手研究者の五味渕典嗣さんに、戦争という時代を生きた作家たち、戦争文学、さらには新連載の意気込みまで、余すところなく聞いていただきました。
■戦争小説はライフワーク
五味渕:浅田さんの作品には、『終わらざる夏』や『帰郷』などの戦争を真正面から描いたものはもちろん、『霧笛荘夜話』の園部幸吉、「天切り松」シリーズの寅弥など、戦争に深く心を傷つけられた人々が多く登場します。まず、浅田さんにとって戦争を描くことはどんな意味があるのでしょうか?
浅田:「戦争のことを書こう」とはっきりと思ったのは自衛隊にいたころです。僕自身は1951年生まれで全く戦争を知らない。ただ、両親には戦争体験がある世代ですから、「戦争の手触り」のようなものはあるんですね。その一方で高度成長期の申し子でもあって、戦争とは全然違う幸せな時代を生きてきました。誰だってそうであるように、僕も戦争は好きではありません。それでも「書かなければいけない」という使命感のようなものはずっとあったし、戦争小説を書くことはこれからもライフワークだと思っています。五味渕さんはなぜ戦中文学のご研究を?
五味渕:私は1973年生まれで父親は団塊の世代です。祖父も早く亡くしたので、家族の戦争体験さえ聞いたことがない世代ですが、日本に数多くある戦争の物語、教育の場で様々に語られる定型的な語りにどこか違和感を抱いていました。ふと気づいたのは、日本の文学は「中国との戦争」をほとんど描いてこなかった、ということです。もしかすると現代の日本人の多くが、「先の大戦」とは、アメリカに敗けた戦争とだけ思っているのではないでしょうか。日本社会のこの記憶の欠落は異様だと思い、日中戦争を舞台に書かれた文学、あるいは日中戦争期に書かれた文学を多く読み、研究するようになりました。
浅田:論文を拝読しましたが、最近の若い学者の方はいいですね。僕は人見知りなので体験者に取材するのは苦手なんです。心情的に流される怖さもありますしね。だから主に活字で勉強するんですが、前の世代の先生方は戦争体験者ですから、自分自身を批判したり、許容することからどうしても離れられない。これがお弟子さんの代になると、がらりと客観性を持つようになる。
五味渕:世代間のことといえば、浅田さんはしばしば「戦争を書くことは怖い」「死者の目を意識せざるを得ないから」と仰っていますね。
浅田:「死者に対して責任をとれるか」とくり返し考えます。そこが他の分野の小説を書く時との大きな違いでしょうか。体験者の方から頂く批判のお言葉は、ありがたいことですが、「怖い」という感覚はない。ですが、それを言えない人の声は、「怖い」です。
■浅田文学を貫く「問題意識」
五味渕:浅田さんのこれまでの戦争文学はある特徴を備えていると思います。たとえば、『帰郷』の登場人物の言葉を借りると、この「悪い戦」をどう終わらせるか、ということです。『日輪の遺産』『終わらざる夏』には、全面的に敗北した先の大戦をどう終わらせるかを懸命に考え、行動する人物が多く登場します。『帰郷』もまさに戦争で生き残った人たちが、自分にとっての戦争をいかに終わらせるかの物語とも言えます。これは戦争文学における大切な問題提起だと思います。一度動き始めた戦争を止めるのは非常に難しい。体面や体裁を守るためではなく、より望ましい未来に繋げるためにいかに止め、いかに敗けるか。その問題意識が浅田さんの戦争文学を貫いている。その意味で言うと、日中戦争に従軍した作家をテーマとする今回の連載は、これまでにない作品世界ではないかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
浅田:日中戦争はとっかかりの満州事変(1931年)からなし崩し的に戦争が始まった。日本はいつでも終わらせることができると考えていたけれども、相手が思いがけず手ごわくて、1945年8月15日の敗戦まで戦局が泥沼化していく。五味渕さんの論文(「曖昧な戦場:日中戦争期戦記テクストと他者の表象」*1)で目から鱗が落ちる思いだったのは、開戦時のスローガンが、「暴支膺懲」だったことです。平たく言えば、出来の悪い弟を懲らしめる、というほどの意味だと思うのですが。日本の仮想敵国は日露戦争以来、一貫して旧ソ連であって、もともと中国と本気で戦う意思はなかったんじゃないでしょうか。日中戦争によって日本の政治を引きずり回したエリート軍人たちは純粋培養されていました。例えば、軍人の政治不関与を定めた「軍人勅諭」の精神に則って、陸軍士官学校や陸軍大学校では「政治学」という科目がなかった。だから教養としての社会や政治に全く疎いものだから、中国との講和の機会も逸してしまった。非常に性質の悪い、大義のない戦でした。
五味渕:従軍作家たちにとって、そこが難しいところですね。要するにプロパガンダが書けないんです。1941年12月8日の真珠湾攻撃を作家たちが晴れやかな思いで迎えた、という話があります(*2)が、それは言葉を発する側からすると対立の構図が明確になったからです。敵の顔がはっきりして、「鬼畜米英」「東洋対西洋」と言える。しかし中国は同文同種と言い続けてきた相手ですから、作家たちは非常に書きづらい。最近の研究でわかってきたことですが、中国側も日本のメディアをよく見ていて、日本の戦争遂行能力をかなり調べていた。情報戦です。そのことを意識した当局が言論統制を強めていくと、当然書けることが減っていくわけですね。
浅田:当時、日本には膨大な数の中国人留学生がいました。3万人くらいはいたのではないでしょうか。いま書店街になっている神保町のすずらん通りは中華街でしたし。日本語と専門知識に習熟して帰国した人が各地に大勢いるのだから、日本語で書かれたものがすぐに翻訳されて出回るのは確か。日本は中国の実力を舐めきっていたと思うんです。
五味渕:火野葦平の『土と兵隊』に、捕虜の国民党軍兵士が今度上陸する日本人兵士は年寄りだから弱いはずだ、と言う場面があります。なぜその捕虜がそんなことを知っているか。日本は現役の兵士をソ連との戦いに備えて温存し、年配の補充兵などを新たに師団に組んで戦場に送ったんですが、それを日本の新聞が書き、それが中国で翻訳されるからなんです。日中戦争が悪い戦になった大きな理由のひとつは、浅田さんが仰るように、この戦争を戦う相手のことを、軍も政府も一般国民も正確には理解していなかったからだと思います。
■戦争の「贄」となった火野葦平
五味渕:日中戦争というのは情報戦だと先ほど申し上げました。陸軍は「中央公論」に掲載された石川達三の『生きている兵隊』を弾圧する一方で、「改造」に火野の『麦と兵隊』を渡した。さらに当時、文藝春秋社の社長だった菊池寛にペン部隊を組ませるなど、非常に上手くメディアを使っている。なかでも上手くやったのは、火野葦平という人を「兵隊作家」として使ったことでしょう。
浅田:僕はやはり、ナチスのプロパガンダ戦略の影響があると思うんです。これは、多分それまでの世界にはなかった、とっても特殊な、しかも的を射たものだった。あの頃のエリート軍人はドイツ留学組が多いでしょう。これが国家総動員法というものとミックスされると、従軍のペン部隊なんてものが生まれてくる。そのなかで、火野さんはひとつの戦力になってしまった。当時、ご本人はそこまで深くは考えていなかったと思うんです。一兵卒とは違って下士官ですし。職業軍人としての自覚もあったろうし、ものを書くという自分の才能で軍に貢献することを実は歓迎していたと推察します。でも結果的に戦後、自死された。戦後の火野さんにとっては、それが非常に重い意味を持ってしまったのかもしれません。
実は今日、特別なものを持ってきたんです。懇意にしていた料亭の女将から、「火野先生から亡くなる前の年に頂いたのだけれど、いずれ店を閉めるので持っていてほしい」と渡された扇子です。その場でさらさらと書き付けたそうですが、この扇面を開いた途端、思わず溜め息が出ました(内容は下記)。本当に苦労された人生だったんだなあ、と。戦場で多くの戦友や部下を失っている。その現実や自分の身近なことまで、様々な意味が込められている。火野さんはやはり、兵士たちの悲劇を体現した人ですね。
山吹の賦
巷の垣にさりげなく
咲く山吹の美しき
かわたれどきに白雨来て
たたけど散らぬ花びらを
いづくのもののしぐさぞや
一ひら二ひら三ひらほど
土によごれてけさありぬ
散りて咲くてふもののふの
心ににたる黄のいろに
たわむる蝶のありつれど
なげきをきかんすべもなし
けふの思ひを忘れずば
いつか巷の山吹を
昔の色にかへしてむ
昔の色にかへしてむ
あしへい
五味渕:陸軍報道部に配属されて『麦と兵隊』を命令で書くわけですけれども、その前に徹底的に新聞検閲の訓練をさせられ、中国人向けの伝単(宣伝ビラ)の原稿を書くんです。軍の目線から書いてほしいこと、書いてはならないことを徹底的に叩き込まれる。しかしそれでも、いま我々が読むと「あれ?」と思わせる表現が刻まれている。作家の性なのか、戦場で見てしまったものがどこかで記憶に残り、言葉に滲み出てしまうのかもしれません。
浅田:それに加えて当時の検閲官や軍人は、文学的素養に欠けていたから、作家の技術で検閲をすり抜けていたんじゃないかな。検閲のマニュアルがあるでしょう?
五味渕:ええ。当時の内務省と軍が戦争報道のガイドラインを作っていました。従軍ペン部隊が参加した武漢作戦のときには、そのガイドラインを明記した「従軍記者ノ栞」が作られ、配られています。
浅田:このマニュアルを迂回して書くこともあり得ると思う。検閲をギリギリのところですり抜けて書いていくのが作家の技術で、それがいちばん良い原稿なんです。その意味で感心したのは、『コレクション 戦争と文学7 日中戦争』(編集部注:現在は文庫版あり。『セレクション戦争と文学 5 日中戦争』)に収録した日比野士朗さんの「呉淞クリーク」。この作品が発表されたのは日中戦争中の1939年だけれど、戦場の有様がかなり露骨に書かれていて、これは“反戦小説”だと思った。でも当時の検閲担当者はそうとは気付かなかった。日比野さんのテクニックです。
「コレクション 戦争と文学」(全20巻+別巻、集英社)の編集をしたときに日本の戦争文学とはなにか、を考えました。僕は日本独特の自然主義文学に関わりがあるように思うんです。明治期の日本に入ってきたのは、ディケンズなどに代表される、キリスト教の呪縛から解き放たれ、ありのままの人間を書こうとした自然主義文学でした。でも日本にはもともと呪縛する宗教がないから、真似しようとしてもできない。結果、自分自身の苦悩を書くのが自然主義文学となり、それが純文学となった。ただ、作家の個人的な苦悩を皆が理解できるわけじゃない。そんな時代の文学がぶつかったのが戦争だった。私的苦悩ではなく、戦争を背景とした命のやり取りという普遍的な苦悩を共有することで突然、素晴らしい戦争文学の地平が拓けたと、僕は思うんです。これは西洋にはない、特殊で面白いジャンルですね。
五味渕:日中戦争という表現しにくい戦争をどう書くか。そのことへの答えが戦場での苦労を共有する、共に乗り越えていく物語だったのかもしれません。
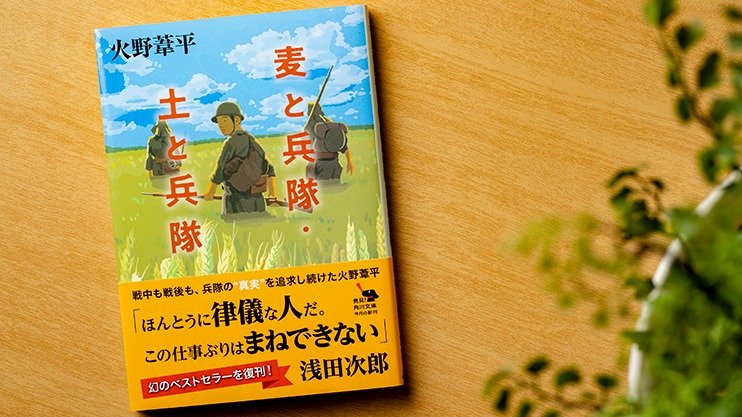
火野葦平は、いかなるときも「人間」を書く。幻のベストセラーを復刊! 『麦…
■いま日中戦争を問う意味
浅田:ところで、従軍ペン部隊に関する五味渕さんの論文(「文学・メディア・思想戦:〈従軍ペン部隊〉の歴史的意義」*3)を読んで驚いたのは、ペン部隊の作家に支度金として七百円もの大金が支払われていたことなんです。当時の公務員給与と単純比較して、現在の貨幣価値に換算すると二百万円くらいでしょうか。これは僕の実感でもありますが、小説家は経済的な不安定さに恐怖感がありますから、この七百円は魅力的だったと思う。時代の空気もあるから、岸田國士のように対中政策を批判した(*4)人は特別だったと思う。僕はその空気の中で自分の良識を発揮できる自信はないです(笑)。だからこそ、そういう世界にしないことを考えなくてはならない。きっと当時の空気になったら抵抗できない。人間ってそんなに強いものじゃないから。
五味渕:特に生活がかかってくると。
浅田:自衛隊時代、東富士の広大な演習場で1万から2万人の隊員が集まっての大規模な師団演習があったんです。その時って、僕たち隊員は全員が自分の位置を分かっていないんです。自分がどこでどの作戦に参加していて、何をやらされているのかは全く分からない。考えているのは早く終わらないかということだけ。あと腹が減ったとか疲れたとか眠いとかいうことだけで。そんな戦場で人間ができることは、撃ってきたら撃ち返すくらいのことなんですよ。山本七平さんが言うところの「集団ヒステリー」というやつです。当時は、社会全体がその状態にあったと思います。
五味渕:私はいまこそ、日本人は日中戦争を知らなくてはならないと考えています。日中戦争時は、銃後の人々は普通に生活して娯楽も楽しんでいる。身内が戦争に行っていない人にとっては、いわば他人事の戦争だったでしょう。いまの日本人の戦争に対するイメージは、先の戦争末期の特に空襲以後のものですが、次に日本が関わる戦争は、日常が全く変わらない戦争だと思います。そうした他人事の戦争が起こったとき、果たして日本の社会で反戦の声を上げられるのか。だからこそいま、戦争と日常が並立していた時代だった日中戦争、特に前期に注目して研究していきたいと考えています。
浅田:いま僕が会長をしている日本ペンクラブの上部組織の国際ペンクラブは、第一次世界大戦が終わったときに、戦争は言論表現の抑圧から始まるのだから、その自由を守り抜こう、との考えのもとに文学者が結集して日本もすぐに加入しました。しかしその後の歴史はご存じの通りです。このような政治状況下でもありますから、些細なことにもペンクラブで声明文を出すようにはしていますが、危機感は常にあります。いずれこんなことも見過ごす世の中になってしまうのかな、と。でも、できるだけの努力はしていきたいです。
五味渕:『蒼穹の昴』をはじめ、浅田さんの中国近代史シリーズを愛読していますが、いちばん感じ入るのは、中国の文明と大地、そこに生きる人々への深い敬意です。西太后、李鴻章、張作霖など、日本での一般的なイメージを心地よく裏切っておられる。そんな浅田さんが日中戦争をどう描かれるのか。読者としてわくわくして待っています。
浅田:現段階ではまだなにも書いていないのですが(笑)。単に戦争小説というだけでなく、ミステリー仕立てにはするつもりです。主人公は探偵小説家かなあ。まだ分かりません。でも、必ず良いものにしますから。楽しみにしていてください。
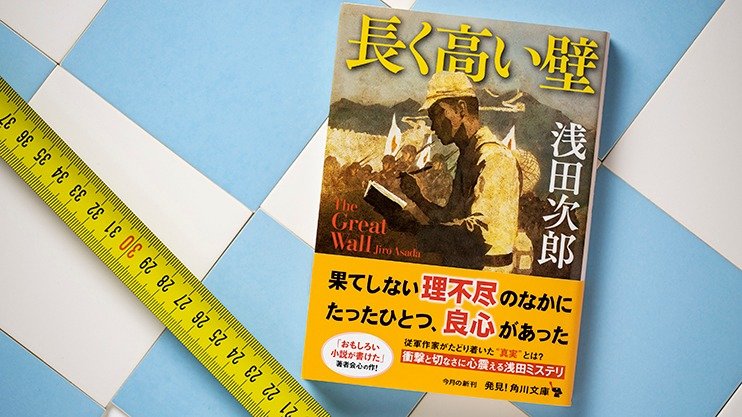
軍の論理では割り切れぬ、人の心を従軍作家が解き明かす。戦場の人間ドラマ …
▼浅田次郎『長く高い壁 The Great Wall』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322005000360/
火野 葦平(ひの・あしへい)
1907年福岡県生まれ。本名は玉井勝則。日中戦争出征前に書いた『糞尿譚』で芥川賞を受賞。“戦地の芥川賞作家”が誕生した(受賞当時の階級は伍長)。その後、陸軍の報道部員として従軍し、軍の要請を受けて『麦と兵隊』を執筆。大ベストセラーとなり、たちまち国民作家となった。しかし、戦後は一転して“戦犯”として厳しく糾弾される。自身の戦争責任について記した『革命前後』を脱稿した60年に睡眠薬自殺。火野のノートには「死にます。芥川龍之介とはちがふかも知れないが、或る漠然とした不安のために。すみません。おゆるし下さい。さやうなら。」とあった。
■海を渡った主な従軍作家たち
石川達三、尾崎士郎、菊池寛、岸田國士、久米正雄、佐藤春夫、丹羽文雄、林芙美子、火野葦平、横光利一、吉川英治、吉屋信子(五十音順)
■日中戦争関連年表
1928(昭和3)年 張作霖爆殺事件
1931(昭和6)年 柳条湖事件をきっかけに中国軍への攻撃が開始される(満州事変)
1932(昭和7)年 満州国建国が宣言される
1933(昭和8)年 日本、国際連盟を脱退
1937(昭和12)年 盧溝橋事件に端を発した日中戦争が始まる
1938(昭和13)年 石川達三、『生きてゐる兵隊』を発表。掲載誌「中央公論」は即日発売禁止に
火野、『麦と兵隊』を発表、ベストセラーに
ペン部隊が結成される
1939(昭和14)年 ノモンハン事件
1940(昭和15)年 日独伊三国同盟を締結
1941(昭和16)年 真珠湾攻撃、太平洋戦争が始まる
1942(昭和17)年 日本文学報国会が結成される
日本軍、ミッドウェー海戦に敗北
1943(昭和18)年 日本軍、ガダルカナル島から撤退
1945(昭和20)年 東京大空襲
硫黄島陥落
広島、長崎に原子爆弾が投下される
ソ連、日ソ中立条約を破棄
日本、ポツダム宣言を受諾
[*1] 掲載誌:昭和文学研究第69号(2014年9月)
[*2] 当時の作家たちが太平洋戦争開戦日(12月8日)をどのように受け止めたのかは、小田切進(編)の『十二月八日の記録』に詳しい。それによると、開戦後の文芸各誌などには、石川達三や小林秀雄、斎藤茂吉、高村光太郎、火野葦平、横光利一ら多数の作家による開戦の高揚を記した文章が掲載された。なかでも武者小路実篤は、「大東亜戦争の使命と言ふものが実にはつ切りし、現代の大日本程、光輝ある時代ではないと言ふことをはつ切り自覚出来たから」と開戦後に明るい気持ちになった理由を語り、「東亜の人達が心を一つにして英米の支配下のものを救ひ、独立して立派に生けるやうに協力することが如何に大事なことであるかを知らせる点にある」と文学者の使命を説いた。
[*3] 掲載誌:大妻国文第45号(2014年3月)
[*4] 「従軍作家」のひとりとして中国戦線を視察した岸田國士は、従軍での印象を綴った『従軍五十日』のなかで、「今度の事変で、日本が支那に何を要求してゐるかといふと、たゞ「抗日を止めて親日たれ」といふことである。こんな戦争といふものは世界歴史はじまつて以来、まつたく前例がないのである」「支那側に云はせると、日本のいふ親善とは、自分の方にばかり都合のいゝことを指し、支那にとつては、不利乃至屈辱を意味するのだから、さういふ親善ならごめん蒙りたいし、それよりも、かゝる美名のもとに行はれる日本の侵略を民族の血をもつて防ぎ止めようといふわけなのである。実際、これくらゐの喰ひ違ひがなければ戦争などは起らぬ」と日本の対中政策を批判した。



































