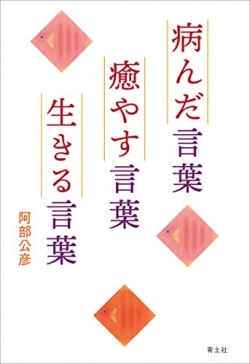『病んだ言葉 癒やす言葉 生きる言葉』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
伝わらないのはあたりまえ!? 身体を通して言葉の奥行きを探る
[レビュアー] 大竹昭子(作家)
大胆な本である。著者は英文学者だが、一時期「入試制度について文句を言う人」になり、メディアで盛んに発言をした。かつて『週刊新潮』にも会話力に重きを置いた英語教育を疑問視する文章を寄せたことがあり、それも本書に入っている。ならば語学教育の問題点を指摘した内容かといえば、そうではない。中盤以降では文学の話が展開される。森鴎外へ、ワーズワスへ、夏目漱石へと横断的に語りながら言葉とは何かを考えていく。
「この数年、暇さえあれば、私は作家と胃弱について考えてきた」。胃弱の代表と言えば夏目漱石だが、あれほど作品に描いたのも、自分の存在根拠をそこに求めたからだ。
武田百合子は食べ物の話をよく書くのに、味覚についての記述が少ない。彼女の関心が食物の味ではなく、食べるという行為に向かっているためだろう。
太宰治の小説は二人称で呼びかけるスタイルが多く、ジェスチャー過剰だが、それは読者を意識したものではなく、太宰が語りの推進力を得るのに他者を設定する必要があったためではないか。カズオ・イシグロは作品に文体を持ち込まず、小説臭を消すことでつねに別の場所を暗示しようとしているなど、頷かせられる指摘がたくさんある。
読むうちに「文は身体なり」というフレーズが浮かんできた。昨今は言葉が情報を収集拡散するための機器と化しており、入試制度や語学教育もそれを反映しつつある。だが、よく考えてみれば言葉の出所は身体なのだ。だれもが持って生まれた体を根拠にその人なりの言葉を紡ぐのであり、当たり前だが、漱石が健啖家の体で書くことは不可能だ。
そういう視点を忘れて、ただ効率よく情報を伝えることだけが目指されるなら、言葉はやせ細る一方だろう。身体を核に作品世界を想像してみれば、言葉の奥行きはもっと深まっていくはずだ。