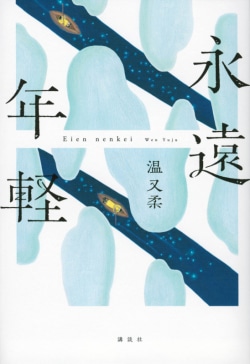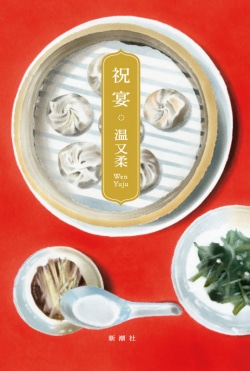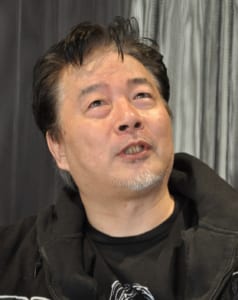『永遠年軽』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『祝宴』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
汽水域
[レビュアー] 千種創一(歌人)
河口のカフェでこれを書いている。遠くに不思議な波が見える。河を下る淡水と、海からの海水がぶつかるところだ。あの光の下にも魚がいるのだろう。汽水魚という呼吸の上手な魚たちが。
***
温又柔の『永遠年軽』にも『祝宴』にも、台湾にルーツを持つ人々が出てくる。『永遠年軽』には、林圭一、林由起子、林美怜という三人の登場人物が出てくる。圭一と由起子は「はやし」なのに対し、美怜の苗字は「リン」と読む。日本と隣国のイメージが近接する。一昔前ならば、はやしとリンを「普通の林」と「普通でない林」と区別して呼んだ人もいたかもしれない。この「普通」という価値観は、台湾系の一家をめぐる物語『祝宴』においては、鉤括弧のない、登場人物のセリフのように、同時に語り部のセリフのように、繰り返し言及される。敢えて文脈は隠しつつ数か所を引用する。
「どんなにがんばってもわたしは日本人にはなれない。日本では、日本人だけが正常でそれ以外は不正常なの……」(『祝宴』)
「ちがうんです。瑜瑜は、ふつうの娘じゃないんです……」(『祝宴』)
「長女に同性の恋人がいるという事実を受けとめきれずにいる自分を、妻や次女に知られたくないとも感じている。」(『祝宴』)
『永遠年軽』も『祝宴』も、国籍が日本か非日本か、言語が日本語か非日本語か、異性愛か同性愛か、出産するかしないか、本省人か外省人か、中国語か台湾語か、などいくつもの軸で、物語が組み上がり、建築物のようになっている。『祝宴』においては、時系列が、二〇一七年の、同性婚を認めないことを違憲とする台湾司法院大法官会議の解釈布告、二〇一九年の、台湾立法院による同性婚を合法化する法案可決とほぼ一致していることを踏まえると、登場人物たちの苦悩や葛藤は、そのまま台湾国民のそれらであると読むことも可能かもしれない。
自分たちが単一民族であると誤認しがちで、同調圧力が強い「ムラ」的な日本社会においては、普通である/普通でない、の二項対立の価値観が押し付けられることが未だに多い。しかし、温又柔の作品は、物事が単純な二項対立でないことを、教えてくれる。それは、河口には海水・淡水の二種類だけではなく、汽水も流れているということと似ている。温又柔の作品は、そこに生きる魚の靭(つよ)さを、その苦しさを、教えてくれる。硬直しがちな価値観を相対化するのも文学の役割の一つであると信じている。
***
カフェの窓から再び河に目をやると、淡水と海水がぶつかり不思議な波の立つ水域が、さっきよりこちらに近づいている。その力強いうねりを見ていると、夕光の中で一匹の鰡(ぼら)が跳ねたのが見えた。