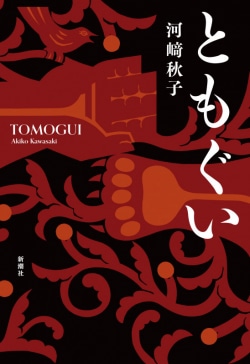『ともぐい』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
熊と人間、その狭間で

角幡唯介(左)×河崎秋子(右)
北海道の壮大な自然を文字の世界にうつしとり、唯一無二の物語を紡ぐ作家・河崎秋子。新刊「ともぐい」で描かれるのは、明治後期、北海道道東の山奥でひとり生きた男・熊爪の生き様だ。己は熊なのか、人間なのか。その狭間に揺れた生涯を、探検家・角幡唯介はどう読んだのか。同じ北海道に生まれ、自然の残酷さ、生命の儚さを知る二人の創作論を訊く。
狩りは有限を無限にする
角幡 『ともぐい』、とても面白く読みました。特に主人公の熊爪が魅力的だった。人里と山の境界に小屋をもち動物を獲りながら生きる彼の暮らしは、僕の理想の一つです。
河崎 ありがとうございます。私もあの生活には憧れます。山の中でのひとり時間、いいですよね。
角幡 熊爪というキャラクターに、モデルはいるんですか。
河崎 具体的にこのひと、というのはいませんね。明治期の熊撃ちの方々の手記を読みながら、そこにすら描かれない山男を想像して書きました。「山の中で一人生活し、犬を何匹も連れていた」といった、漠然とした記述や言い伝えを形にするイメージです。
角幡 現代で言えば、熊撃ちで作家の久保俊治さんとかに近いのかな。
河崎 ジョン・クラカワー氏の『荒野へ』(集英社文庫)などにも影響を受けました。アメリカの裕福な家庭で育った青年が、アラスカの荒野に一人旅立ち命を落とした事件を追うノンフィクションです。自給自足のスキルを持たない青年を、荒野へ掻き立てたものはなんなのか。それを考えることは、熊爪の人生を描くうえで役に立った気がします。
角幡 熊の習性なども非常にリアルに描かれていますよね。動き一つとっても、手負いの熊が反撃する様子や、山のなかを上り下りする挙動のひとつひとつに、とても説得力がある。実際に狩猟をしていると、そういう場面がありますから。
河崎 そもそも角幡さんはどうして狩猟を始められたんですか。
角幡 僕の場合は、旅や冒険への興味が先にありました。極地に赴くようになったのは「生きる経験」をしたいという思いがベースにあります。当初は極限空間で生き延びることが最重要課題だったから、フリーズドライ食品など機能性の高い食料を都市部から持って行って食べていました。だけどそのうち、最も根源的な活動である食を工業製品や産業製品に委ねていることに、違和感を覚えるようになって……。
河崎 食も自らで調達したい! となったわけですね。
角幡 実際に狩猟をしてみると、本当にいろんなことを学びます。僕は今、グリーンランドのシオラパルクに毎年通っていますが、何度も行くうちに、「今年はここに海豹(アザラシ)がいっぱいいる」「今年はあっちに麝香牛(ジャコウウシ)がいる」と猟場の変化が見えてくるんです。おかげで行くたびに新鮮な感覚を味わえる。
河崎 そこで生活をするからこそ見えてくるものってありますよね。
角幡 そうなんです。自由に動けるようになり、土地がどんどん自分のものになっていく。有限の土地が無限の世界にかわっていく感覚は、狩猟の大きな魅力だと思います。
河崎 土地で獲ったものが自らの血肉となるわけですからね。
角幡 ただ……北極で出会う生物の多く、麝香牛や海豹、白熊などは、実際に対峙すると、肉体的にも知能的にも人間と変わらない、あるいはより優れた存在だと気付いたりもします。どうして自分より立派な生物を獲って生きるのだろう? と生の矛盾を感じるんです。
河崎 狩りをするうえで大事にされていることはあるんですか?
角幡 まずは、自分も殺される可能性を担保しながら狩りをすること。犬橇(いぬぞり)で何十日も人気のない荒野を旅するのはそれだけで危険なことですが、その危険性を受け入れることが僕にとっては大事なことです。あとは、旅をするまでの労力を惜しまないこと。
河崎 準備を人任せにしない、ということでしょうか。
角幡 そうですね。出発までの何十日ものプロセスを、可能な限り自分一人で行いたいんです。だから橇も衣服も、できるだけ自分で作る。資金も人からもらわない。そうすることで自分の行為に関わる割合が増え、狩りの権利が生じる気がします。そういう意味でも、熊爪のあり方は理想的ですね。
河崎 彼は小屋すら作っていますしね(笑)。
角幡 そういえば昨年、狩猟免許を取って初めて日本で鹿撃ちをしたんですよ。それも、北海道の白糠(しらぬか)で。
河崎 本作の舞台の土地ですね! 確かに、あのあたりは鹿が多くいますから。
角幡 初めて森の中で狩りに挑んだら、どこにも獲物が見えなくて驚きました。鹿の身体は完全な保護色で、たとえすぐそばにいたとしても、素人にはどこにいるのか見つけられないんです。極地との違いに悪戦苦闘するうち、鹿と同じ動きをしないと彼らを捕らえられないことを学びました。彼らのいそうなところでは鹿の歩きを真似しながら、ゆっくり歩く。森の中で不自然ではない存在になることが重要。そうして、自然と調和できてようやく、鹿を撃つことができました。僕が森の一部になったときに鹿が死ぬというのは、未だにとても不思議な感覚です。
河崎 角幡さんが森の生物環に入ったということでしょうか。
角幡 森では、生と死が同じ地平にあります。そこに溶け込み、自然への同化や調和を感じて生きる。僕にとって、それは狩猟における最大の喜びです。生きることの根底に触れられている気持ちになる。「自分は人間なのか熊なのか」という熊爪の悩みは、自然と調和した人間だけが辿り着く究極の問いなのかもしれません。