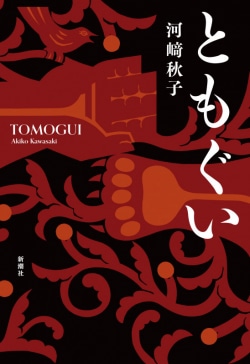ホスト売掛金問題や電通の過労自殺、東京五輪の汚職、大阪万博の建設費増額を彷彿させる事件を描いた物語【新年おすすめ本7冊】
レビュー
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
ニューエンタメ書評
[レビュアー] 末國善己(文芸評論家)
二〇二四年の最初なので、新人の紹介から始めたい。
東圭一『奥州狼狩奉行始末』(角川春樹事務所)は、第一五回角川春樹小説賞の受賞作である。奥州にある小藩では馬産が大きな収入源だったが、大きく賢い狼・黒絞り率いる群れに馬が襲われ損害が出ていた。郷目付役を務める岩泉家の次男・亮介は、父の急死で後を継ぐが病で寝ついた兄に代わり狼狩奉行に任じられた。前半は、猟師も藩士を動員した巻狩でも倒せなかった黒絞りに、山にも狼にも詳しくない亮介と相棒で弓の名手の竜二がどのように挑むのかがメインの冒険小説になる。黒絞りを追ううちに亮介は父が殺された疑惑を知り、その真相を追う後半はミステリ色が濃い。終盤の伏線回収は鮮やかであり、一種のマンハントなので狩猟というモチーフで統一されていた。
河崎秋子『ともぐい』(新潮社)は、狩猟を題材にした『肉弾』などのテーマを深化させており、熊の被害が増え駆除か保護かで対立が起きている現状があるのでタイムリーな作品となっている。明治後期。北海道東部の山奥で一人で暮らす熊爪は、村田銃で鹿や熊を狩って内臓や毛皮を取り、山菜を摘み、それを近くの白糠の町で売って米、塩、弾丸などを買っていた。ある冬、冬眠できなかった熊・穴持たずを追って熊爪の山に入った阿寒の猟師が、その熊に傷を負わせてしまう。穴持たずに挑発された熊爪が、持てる技術を総動員して追跡する中盤は、自然の、野性動物の残酷さが活写され圧倒的な緊迫感があった。自然と動物しか知らない熊爪は、文明開化と近付くロシアとの戦争が町も人の価値観も変えていく中で、異物として排除されようとしていた。視覚に障害がある少女と山奥で暮らし始めた熊爪(二人の関係は、坂口安吾の名作「桜の森の満開の下」を思わせる)の葛藤は、自然から切り離された人間は、家畜を食べ、害獣を駆除しなければ生きていけない弱い生物になった現実を突き付けているのである。
月村了衛『半暮刻』(双葉社)は、社会問題になっているホストクラブの高額売掛金を思わせるエピソードから始まる。城有が結成したカタラグループは、経営する会員制クラブで女性に大金を使わせ風俗に沈めていた。カタラの新宿店に、児童養護施設出身で定時制高校中退の山科翔太、裕福な家庭に育ち有名大学に通う辻井海斗が参加する。城有の作ったマニュアルを信奉する二人はコンビを組んで成績を上げ、トップテンになった。やがて読書好きの女性と知り合い海外文学を読むことで自分の罪と向き合う翔太に対し、大手広告代理店に入社した海斗は、世界的なイベントの担当に抜擢され、部下の女性に平然とパワハラを行うなどカタラのマニュアルと勤務先の社訓を洗練させた手法で出世していく。月村は、ホストクラブの売掛金だけでなく、電通の過労自殺、先の東京五輪の汚職、現在進行形の大阪万博の建設費増額などを彷彿させる事件を描くことで、人間をモノとして扱う現代日本の社会構造とその奥に潜む闇を暴いてみせる。終盤には、カタラよりも効率的に金を集め、人間を使い捨てにし、裁かれないよう巧妙に立ち回る巨悪の存在が浮かび上がり、日本の真の問題点に気付かせてくれる。
同じく日本の病理に切り込んでいる天祢涼『少女が最後に見た蛍』(文藝春秋)は、神奈川県警の仲田蛍が活躍するシリーズの第四弾で初の連作集である。高校生がひったくりを目撃、クラスメイトが犯人と気付く「十七歳の目撃」は、証言を拒む理由に仲田が迫る。仲田が小学校の同級生の集まりで、ある男子が好きだった女子を当てる推理合戦を行う「初恋の彼は、あの日あのとき」は、恋愛話が思わぬ真相にリンクする意外性があった。「言の葉」は、SNSにおけるエコーチェンバーとフィルターバブルを謎解きにからめた秀作。ゲームのキャラクターに似ている仲田に会いたいという理由で私立校の生徒が万引きする「生活安全課における仲田先輩の日常」は、真の動機とその先に置かれた家族の問題に驚かされた。偶然、中学時代のいじめっ子と再会した仲田が、いじめられていた蛍子に何か起きたのかを推理していく表題作は、仲田が警察官になった理由も語られるので、シリーズの重要なポイントとなっていた。いずれの作品も伏線回収が見事で、探偵役の仲田は、子供のいじめ、虐待などは想像力の欠如が原因で起こると繰り返す。それだけに、大人が想像力を磨き、想像力の重要性を子供に伝えるには何が必要かを考えさせられる。
続いては、紫式部を主人公にしたNHKの大河ドラマ「光る君へ」の予習に使える作品を見ていきたい。
楠木誠一郎『チーム紫式部!』(静山社)は、児童向けではあるが、平安時代の社会制度、紫式部の生涯、『源氏物語』のあらすじなど必要な情報がまとめられ、古典が苦手な大人の入門書にもなるだろう。著者は、雲上人の藤原道長に初めての恋をするも、別の男と結婚し賢子を産み夫と死別した香子(後の紫式部)が、初恋の決算のために書いたのが『源氏物語』だったとしている。一条天皇の中宮になった道長の娘・彰子の家庭教師を頼まれた香子は、藤式部の女房名を与えられ宮中に入る。宮中での同僚たちとの軋轢が、学校や会社での人間関係になぞらえられているなど親しみ易くなっている。
さらに詳しく紫式部について知りたいなら、紫式部の人生、影響を受けた芸術作品や仏典が詳しく紹介され、『源氏物語』の現代語訳もある帚木蓬生『香子(一)紫式部物語』(PHP研究所)をお勧めしたい。一巻は紫式部が「若紫」を書いたところで終わり、どの順番で『源氏物語』の各帖が書かれたかについても独自の解釈があるので、今後の展開も楽しみである。
『源氏物語』の宇治十帖を大胆にアレンジした『女たち三百人の裏切りの書』を発表した古川日出男が、彰子の出産前後を記録した『紫式部日記』を題材にしたのが『紫式部本人による現代語訳「紫式部日記」』(新潮社)である。時空を超越して現代の事情にも通じる紫式部が語り手になり、平安時代の役職、建物の構造、文化などを英語まじりで解説してくれるので分かり易い。悪霊退散の加持祈祷が続く中で彰子が出産するまでは、伝奇小説のテイストがある。日記に女房たちの批判を書いた紫式部は、高慢とされることもあった。本書にも紫式部による女房の評価が出てくるが、これは批判ではなく、同僚の人となりを知るために必要だったとされている。男性優位の社会で同じ女房たちと連帯を深めようとした紫式部に、働く女性は共感できるのではないかと思えた。
新しい年になり、今まで読んでこなかった作家の本を読んでみたいと考えている方もいると思うので、それに最適なアンソロジーを紹介したい。
同じ書き出しで始まる講談社編『嘘をついたのは、初めてだった』(講談社)は、『黒猫を飼い始めた』に続くシリーズ第二弾。嘘をつかないという“僕”との約束を守りクラスで孤立した女子高生が屋上から転落死した事件の裁判で“僕”が証言する五十嵐律人「偽証の誓約」は、最初の一文が効果的に使われていた。母親の胎内にいる胎児が語り手の西尾維新「生まれる前から倦まれてた」は、出産時に女性が受けるプレッシャーを取り上げテーマ性も高い。夫に嘘をついて姉の婚約者と旅行に行く女を主人公にした小野寺史宜「エミリン」は、設定や展開にインパクトがあり最後の一行はさらに衝撃的だ。歴史は嘘の集積だと断じる古代史ものの高田崇史「女帝の憂鬱」。小学生が書き始めた嘘日記が、ある真実を暴いてしまう真下みこと「嘘日記」など、新鋭からベテランまで全二九作が収録されている。同じ書き出しだからこそ、物語の広げ方やオチのつけ方に作家ごとの個性が際立ち、自分好みの文体や作風を見つけることができる。
小学館文庫編集部編『超短編! 大どんでん返し Special』(小学館文庫)も、ショートショートでどんでん返しを作るシリーズの第二弾。カンダタが罪人たちを見捨てず共に極楽へたどり着いてから一〇〇年後を描く森見登美彦「新釈『蜘蛛の糸』」は、純文学のパロディ集『新釈?走れメロス 他四篇』を刊行している著者らしい一編。ヴィルヘルム二世のオランダ亡命の秘話になっている野崎まど「皇帝」は、カイゼル髭がヴィルへルム二世に由来していることと、『空手バカ一代』の眉毛のエピソードを知っているとより味わい深い。ある男を殺そうとしたことがあるという新人賞の受賞の挨拶が、最後の一行でゆらぐ伊吹亜門「或る告白」。バラバラ殺人、死体の隠滅に新たな光を当てた北山猛邦「計算上正確に分解された屍体」など、ミステリ、ホラー、歴史小説などバラエティ豊かな三四編が収録されている。個人的なお気に入りは、「彼氏に餓えていた」という一文の意味がラストに反転する一穂ミチ「恋に落ちたら」、ラストを読むと、それまでの何気ない会話の意味が変わる蝉谷めぐ実「飯の種」である。
全六章から成り読む順番で世界観が変わる『N』などを刊行している道尾秀介の『きこえる』(講談社)は、スマホなどで作中に挿入されたQRコードを読み取ると音声が聞こえ、音と文章の相乗効果で楽しむ仕掛け本だ。家出同然で上京し面倒を見ていた女性歌手を殺されたライブハウスの女性経営者が、CD音源の中に聞こえるはずのない被害者の声を聞く「聞こえる」、女子生徒に盗聴器入りのUSBアダプタを渡した塾講師が、女子生徒と義父の関係が悪いと気付くが盗聴器が原因で誰にも知らせられないジレンマに陥る「ハリガネムシ」の二作は、特に音声との融合が活かされていた。これから小説と他メディアとの連携がどのように進むのかは分からないが、本書が新しく面白い試みなのは間違いない。