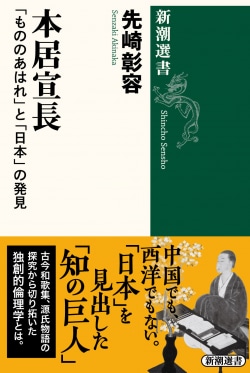エロスいっぱいの宣長
[レビュアー] 片山杜秀(慶應義塾大学教授)

『國文学名家肖像集』に描かれた本居宣長
本居宣長といえば、「漢意(からごころ)」を批判し、「大和魂(やまとだましい)」を称揚した厳めしい日本主義者というイメージを持っている人もいるかもしれない。しかし、先崎彰容さんの新刊『本居宣長 「もののあはれ」と「日本」の発見』によれば、宣長が日本の特長としてもっとも重要だと考えていたのは「色好み」、つまりエロスだったという。日本思想史研究者の片山杜秀さんが本書の読みどころを紹介する。
片山杜秀・評「エロスいっぱいの宣長」
西と東の相剋。古代から現代に至る日本史はそれで読み解ける。本書の大前提だろう。かと言って、西日本と東日本という国内地理の話ではない。荻生徂徠や賀茂真淵が江戸に居て、本居宣長は伊勢の松坂だから、東と西というわけでもない。西とは隋や唐や近代西洋だ。外圧は西からかかる。日本は常に東側。しかもこの国に西を圧倒する力は昔も今もなかなか備わらない。ゆえに東が西に文明として対抗しようとすると、日本の内側に西の理屈を入り込ませて「文明化」してみせるというかたちをとらざるを得ない。こうして我らの内なる西が生まれる。我らの内なる東と、争ったり、軋んだり、棲み分けようとしたりする。西が東を露骨に下位に置くこともとても多い。因果応報の仏教に大義名分の儒教に合理と科学の西洋文明。東はいつもその前に這いつくばるのか。今日の日本を含めて。
そうはさせじ。本書の主人公は我らの内なる東の側に立つ大思想家だ。国学者である。一七三〇(享保一五)年に生まれ、一八〇一(享和元)年に逝った。田沼意次や松平定信の時代に自らの思想を展開した。世には確かに矛盾や不安も満ちる。が、前後の時代に比べれば、外圧をかなり忘れられ、「鎖国」の稔りを得られた頃合い。言わば江戸期の頂点。経済は殷賑。学芸は爛熟。政治や社会の差し迫った課題も少なめ。かくて宣長は嘯く。「上古の時、君と民と皆な其の自然の神道を奉じて之れに依り、身は修めずして修まり、天下は治めずして治まる矣」。儒仏や蘭学に頼らずとも我が国は自ずから回る。国学者の自信であろう。
すると宣長とは、おめでたい江戸中期の産んだ、単なる楽天家だったのか。そんなことはあるまい。著者は大野晋の説を引きつつ若き宣長の苦悩と決断に注目する。宣長の思いびとは材木商に嫁に行き、彼は人妻への恋情に身を焦がしつつも、意に染まぬ結婚をした。ところが思いびとは材木商と死別。それを知った宣長は歌を詠む。「くらへ見んいつれか色のふかみ草 花にそめぬる人の心と」。思いびとの名が詠み込まれている。草深民という。民さんだ。近代の歌人、伊藤左千夫の小説『野菊の墓』のヒロインも民さん。左千夫は言った。人はなぜ歌を詠むか。合理的な思考や選択から心かはみ出すと、人は叫び、それが歌になる。宣長は草深民を思って叫んだ。妻を棄てた。未亡人の民さんを後妻に迎えた。そんな粗筋が断片的な証拠から組み立てられる。それが人間宣長と弁えれば、『あしわけをぶね』の次の一節の生々しさはまた格別だ。「人の妻を犯すなどと云事は」子供でも悪いと知っているけれど、「すまじき事とあくまで心得ながらも、やむにしのびぬふかき情欲のあるものなれば」やめられないし、止まらないという。
本書が思い入れるのはそんな宣長だ。エロスの権化だ。「西側」の与えるあらゆる文明的道徳律をぶち破って、エロスにひた走るのが、西に抑圧されてきた東の本性、そう主張してやまぬ宣長だ。だから宣長は、合理に回収されぬ余剰を引き受けるために存在する和歌という分野にこだわり、色欲に否定的な儒仏の教えを退け、善悪の弁別に熱心なあらゆるリゴリズムを非難して、日本の日本たる所以を「色好み」に求めてゆく。西と異なる東の独自性を「色好み」のもたらす多産的豊饒さに求める折口信夫の『源氏物語』論が引かれるのも、とても利いている。
エロティックな宣長。人妻に懸想する宣長。でも、ドン・ファンもびっくりの唯我独尊的享楽主義者と思ってはまったく違う。本書の描く宣長は、あくまで和歌があっての日本的エロスを生きている。そもそも性愛とは相手のあること。和歌も詠ませる相手が居てこそ。常に間柄の問題。しかも和歌だからやまと言葉。宣長のキイワードたる「もののあはれ」はそこに登場する。「あはれ」とは「深く思いつつ嘆息する」ことで、その詠嘆の微妙な質を、歌詠みのみならず、歌の受け手も襞の奥まで感受そせるべく、日本の風土を踏まえつつ、高度な含蓄を持って、儚く曖昧に流動的なかたちになるように、修辞法を蓄えてきたのが和歌なのだ。それを極めれば、西の漢心の単純な善悪二分法の理屈を超えた、森羅万象の「あはれ」が感受しうる。やまと言葉のみが世界に冠たる精妙さで描けると宣長の考えた、不断に揺れ動き続ける関係の中に漂うだけが人生なのだ。そう言えば本書は和辻哲郎やその門下の相良享の宣長論を大きな導きの杖としているが、それは和辻倫理学が個々の人間の主体よりも複数の人のあいだの微妙な感情の往来に目を配り、儚い関係性に思いを致しているからであろう。しかもこの筋書きは、やまと言葉と和歌なくして成り立たぬのだから、外国には通じまい。やはりウルトラ日本主義である。しかし、平和な江戸中期の生んだ、儚くも美しく燃えるエロスの綾しか認めない日本主義でもある。戦闘的ナショナリズムとは本来的に結びつきようがない。かくて著者は宣長を近代的自我とも合理主義ともファシズムとも繋がらぬ思想家として見事に救済する。そういう思想のかたちは著者の求める日本的保守主義の精髄ときっと重なる。先崎さんの多くの仕事の中でも、これは極め付きである。