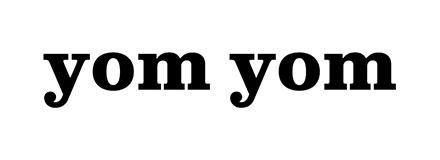『誓願』マーガレット・アトウッド[著]鴻巣友季子[翻訳]早川書房
境界線に置くことば―今ここに迫る危機としてのディストピア アトウッド文学における解釈の転換―
2020年ノーベル文学賞の最有力候補となるほか、近年ディストピア文学がブームになるなか再評価されているカナダの作家・マーガレット・アトウッド。過去にはフェミニズム文学の旗手として注目された彼女の作品の魅力や作家性について、翻訳家で文芸評論家としても活動する鴻巣友季子さんが解説する。
※本記事は雑誌「yom yom vol.65」(2020年12月号)に掲載された評論です
***
英語コミュニケーション学科H川先生
11/03 22:35
向寒の砌、ご健勝のことと拝察します。このたびは先生の英語圏文学特講Ⅱにて、マーガレット・アトウッドの拙訳『誓願』を教材にお使い頂けるとのことのご連絡、まことにありがとうございます。
『誓願』の前作にあたる『侍女の物語』はご存じのとおり、アメリカ合衆国に誕生した独裁神権国家「ギレアデ共和国」を舞台にした小説です。過激な男女隔離政策をとるこの国では、女性が「侍女」という名の「産む道具」にさせられますね。『侍女の物語』はその出口の見えない閉塞的な状況を闇の内側から語りましたが、続編となる『誓願』はその闇を出ていく物語なのです。
これを、アトウッドの作風の変化ととらえる読者もいますが、変わったのは読み手という受容の側だとわたくしは小考しております。
アトウッドが1984年(そう、オーウェルの「一九八四年」の年です)に『侍女の物語』を書き、1985年に出版した当時、アメリカ人もヨーロッパ人も、米国でこんなことが起きるなんて、だれひとり、まーーーったく(と、アトウッドは強調します)信じようとしなかった、と言います。
それは、日本でも同じです。読者はこの物語を空想的な寓話かダークファンタジーのように読んでいました。当時の、とくに日本では、まだ「ディストピア」という言葉も概念も普及していなかったからです。だから、アトウッドは「そこにあるのにみんなの目に見えていない世界」として、『侍女の物語』を書くことができたのです。
今、世界的な右傾化傾向、とくに米国のトランプ政権のあり方を見るに、『侍女』の世界は思ったよりそばにあることに人々は気がつきました。恐怖がリアルになったこの時代に、アトウッドはこれ以上出口のない闇の物語を書くことに意義を覚えなかったのだろうと存じます。分断と抑圧の重苦しい空気に耐えかねた読者の呻きに応えたのが、2019年に発表したThe Testaments(『誓願』)であるとも言えるのではないか。学生たちがこの作品の脅威と受容の変化をどう受けとめるか、反応を鶴首してお待ちしております。
お礼のつもりが長くなり、失礼いたしました。時節柄、ご自愛なさいますよう。
—
鴻巣友季子
1994年2月28日 朝日新聞東京夕刊文化面
芥川賞作家の生き方 大江健三郎:(文芸時評)
選ばれた芥川賞作品の載っている「文芸春秋」は、あいかわらず多くの読者を集めるようだ。しかし、この十年ほどの間もわが国の純文学とエンターテインメントのジャーナリズムの様変わりは続き、芥川賞をかちえた作家たちの迎えられ方、生きのび方にも変化がきざまれていると感じられる。
〈中略〉
こういう時、いったん芥川賞をえた作家があらためて文芸ジャーナリズムに登録しなおすような覚悟で、時間をかけた力作を発表する勢いが見られる。辻原登『森林書』(文芸春秋)、小川洋子『密やかな結晶』(講談社)。
ここで後者をとりあげるのは、小川氏が受賞作の短編にあざやかだった個性を、長編の展開のなかで再確認しようとする意図があきらかなこと、しかもそれがファンタジーへの新しい試みとしてなされていて、芥川賞作家のひとつの生き方をそこに示しているからである。
〈中略〉
小さな事物のこまやかな存在感や、そのズレをクールな静物画のように描くのが、小川氏の短編の持ち味だった。その個性を確保しつつ長編へと歩み出た小川氏の姿勢は賢明だし、誠実でもある。しかしその長編の全域に「消滅」が広がると、彼女はそれらをよく統御できない。そこでファンタジーの終局への展開は自閉的となり、読者は没入を妨げられる。そこにこそ物語をつくる能力は意味を持つはずであり、様ざまな大切なものの「消滅」は、われわれの文明の課題ともなりうるのに。
〈中略〉
『密やかな結晶』には最初にファンタジーの仕掛けをつくる時よく考えられていないところがあり、読者にはそこに入りこむ際に違和感が残り、現実世界と対等の手ごたえを受けとめるにはいたらない。したがって作者の方でも、娘がファンタジーの世界においてすら生き続けえぬという、絶対的な「消滅」によって小説を結ぶしかない。それは長編の構想というより、やはり短編のものであろう。しかし小川洋子がファンタジーを再度試みることがなければ、惜しいことだ。
(作家)
株式会社新潮社「yom yom」のご案内
https://www.bookbang.jp/yomyom/
新潮社の雑誌「yom yom(ヨムヨム)」は2006年に創刊され、朱野帰子『わたし定時で帰ります。』、重松清『一人っ子同盟』、辻村深月『ツナグ』、畠中恵「しゃばけ」シリーズなど大ヒット作を数多く掲載してきた文芸誌です。「いま読みたい作家」による「いま読みたい物語」を掲載する――という創刊時からの編集方針はそのままに、WEBマガジンに舞台を変え、読者の皆さまにより近い場所で、「いま」の欲望に忠実な新しい物語を紹介していきます。
関連ニュース
-
【スマホ依存度チェック】5つ以上はかなり危険! 「世界一受けたい授業」で話題の『スマホ脳』
[ニュース](情報学/ビジネス実用/倫理学・道徳/家事・生活)
2021/03/20 -
日本史の教科書がつまらない理由とは 古市憲寿が提案する『絶対に挫折しない日本史』
[ニュース](歴史学/日本史/社会学)
2020/10/03 -
横山秀夫 6年ぶりの長編小説 刊行から1年もベストセラーランキング入
[ニュース](日本の小説・詩集/ライトノベル/歴史・時代小説/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)
2020/02/29 -
曽野綾子の新刊がランクイン 「納得して死ぬ」ためにはどうればよいのか?
[ニュース](哲学・思想/倫理学・道徳/介護/エッセー・随筆)
2018/06/09 -
現役書店員作家が芥川賞を受賞 自分の作品を出版社から持ち帰り書店で販売![文芸書ベストセラー]
[ニュース](日本の小説・詩集/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)
2023/02/04