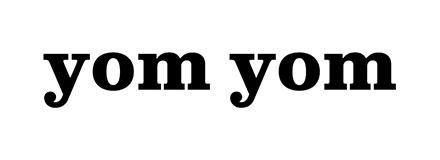三島事件。バルコニーで演説 写真:ANP scans 8ANP 222), CC BY-SA 3.0 NL,
制服人生
エッセイストの酒井順子さんと三島由紀夫の共通点は、制服好き。「服装は強いられるところに喜びがある」と記し、最後は自分が作った制服を着て自決した三島の憧れと望みに、数々の名言をたどりながら光を当てる。
※本記事は雑誌「yom yom vol.65」(2020年12月号)に掲載されたエッセイです
***
大変おこがましい話ではありますが、もしも三島由紀夫と自分との間に共通点があるとしたら、それは「制服好き」という部分だと思っています。
三島由紀夫が自決した時、私は四歳。「仮面の告白」(1)における三島のように、産湯をつかった時のタライの縁のきらめきを覚えているような神の子ではありませんので、自決事件の記憶はありません。楯の会の制服姿の三島の画像を大人になってから見た時、「この人は……、制服を愛している」との確信を得たのです。
制服を着たことがないせいか、制服姿にグッとくる性癖を持つ私。今もって制服を着たくてたまらないのですが、楯の会の制服からは、自分と似たような嗜好の匂いが漂ってきました。
三島の場合は、子供の頃から制服を着慣れています。学習院は日本で最初に制服を導入した学校とされ、男子は海軍士官の制服をモデルにした蛇腹の学生服を着用するのです。海軍士官タイプの制服を小学生から着続け、最後は自身がつくった民兵組織の制服を着て死ぬという、制服に彩られた人生を三島は歩んだことになりましょう。
「若きサムライのための精神講話」(2)には、彼の服装に対する思いが記されます。
「服装は、強いられるところに喜びがあるのである。強制されるところに美があるのである」
と。さらに、
「これを最も端的にあらわすのが、軍人の軍服であるが、それと同時にタキシードひとつでも、それを着なければならないということから着るところに、まずその着方の巧拙、あるいは着こなしの上手下手があらわれる」
と続く文章を読めば、楯の会の制服に対する三島の思い入れが、理解できようというものです。
ウェストが絞られ、肩幅が強調された上着と、細身のズボンからなる、楯の会の制服は、男のボディ・コンシャス。肉体に対して自覚的であり、肉体を見てほしいと周囲にアピールするようなデザインです。
-
- 仮面の告白
- 価格:693円(税込)
「仮面の告白」を若き日の自伝として捉えるならば、三島はその幼少期から、男のボディ・コンシャスに鋭く反応していました。少年時代の彼は汚穢屋(おわいや)、すなわち糞尿汲取人を注視し、『私が彼になりたい』『私が彼でありたい』との欲求を抱いたわけですが、その時に少年の視線を強く惹きつけたのは、汚穢屋が身につけていた「紺の股引」でした。
「紺の股引は彼の下半身を明瞭に輪廓づけていた。それはしなやかに動き、私に向って歩いてくるように思われた。いわん方ない傾倒が、その股引に対して私に起った」
のであり、彼の職業にまとわりつく悲劇的な空気を、その「下半身を明瞭に輪廓づけていた」股引から感じとるのです。
三島少年はまた、「殺される王子」の幻影をも追っています。七度死んでは生き返る王子が描かれたハンガリーの童話を彼は愛読していたのですが、その時に重要だったのは、王子がぴったりとしたタイツをはいていることでした。
「王子たちのあのタイツを穿(は)いた露わな身装(みなり)と、彼らの残酷な死とを、結びつけて空想することが、どうしてそのように快いのか、誰が私に説明してくれることができよう」
と思う彼は、悲劇の中でもとりわけ死に対する陶酔を、ボディ・コンシャスな衣服から得るようになります。
大学を卒業した頃には、筋肉質な肉体を持つチンピラが腹に晒(さらし)を巻く様子から、目が離せなくなりました。そこで想起するのは、
「彼が真夏の街へあの半裸のまま出て行って与太仲間と戦うこと」
そして、
「鋭利な匕首(あいくち)があの腹巻をとおして彼の胴体(トルソオ)に突き刺さること」
三島にとってボディ・コンシャスは、このように血への期待と結びついています。皮膚と一体化し、切ったらすぐに血がほとばしると思わせてくれる巨峰の皮のような衣服を、彼は求めていたのです。
ですから楯の会の制服がボディ・コンシャスなデザインとなったのは、当然だったのでしょう。西武百貨店の当時の社長、堤清二の協力を仰ぎ、フランスのド・ゴール大統領の服をつくったこともある名テーラー・五十嵐九十九(つくも)によってデザインされた、かの制服。エッセイ「軍服を着る男の条件」(3)によると、三島本人も相当、デザインの細部に関わっていたようです。
切ったらすぐに血がほとばしる予感を漂わせるには、制服と肉体との間に隙間があってはなりません。同エッセイには、軍服を着る条件とは、
「仕立のよい軍服のなかにギッチリ詰つた、鍛へぬいた筋肉質の肉体であり、それを着る覚悟とは、まさかのときは命を捨てる覚悟である」
とあります。制服それ自体が肉体にフィットしているのみならず、制服という皮の中に肉体が「ギッチリ」詰まっていなくてはならなかったのです。
充分にパンプアップされた筋肉がぴったりとした制服によって拘束され、その制服が何者かによって刺し抜かれることを待つ。それが三島にとって制服を着る意味だったのではないでしょうか。
彼は、「縛られたい」「拘束されたい」との願望は強く持っていたけれど、「縛りたい」「拘束したい」とは思っていなかったようです。女性が制服等で縛られる様に特別な興味を掻き立てられていた様子も、見られない。せいぜい「婦人公論」一九六七年九月号における「三島由紀夫氏との50問50答」(4)において、
「どんな女性用水着が好きですか」
との問いに対して、
「セパレーツは好きぢやない。ほら、YWCAで使つてゐる、黒のワンピースのものがいいね」
と答えるところに、その片鱗を見るくらいか。女性性を誇示するビキニよりも、スクール水着のようなものの方が良いということなのですが、それは制服好きからすれば、特に珍しくはない嗜好です。
縛られて美しいのは、そして縛られて死んで美しいのは、あくまで男でした。その志向は「仮面の告白」にも見られ、三島少年は白銀の鎧(よろい)を身につけたジャンヌ・ダルクが女であることを知って、
「この美しい騎士が男でなくて女だとあっては、何になろう」
と、いたく落胆しています。
心身が柔弱な女を縛ったとて、そこに美は生まれない。縄なり制服なり、縛る側に拮抗するだけの強さと硬さが、縛られる側には必要だったのです。
少年時代のタイツ姿で殺される王子への憧憬から始まり、楯の会の制服で自決して人生を終えるまで、三島の「縛られて死ぬこと」に対する望みは、貫かれているように見えます。十五歳の時に書いた「凶(まが)ごと」(5)という詩は、
わたくしは夕な夕な
窓に立ち椿事(ちんじ)を待つた、
凶変のだう悪な砂塵が
夜の虹のやうに町並の
むかうからおしよせてくるのを。
と始まります。人生を攪拌するかのような椿事を窓辺で待つ、というのは彼の作品に度々出てくるイメージですが、この時の「わたくし」を拘束していたのは、ただ彼が身を置いていた家ばかりではないのでしょう。この頃の日本には、身分制度やら戦争やら、人を緊縛し、束縛するものがたくさんありました。十五歳の少年は様々なものに縛られることによって、「凶変」がもたらす物語への期待を醸成していたのではないか。
しかし戦争が終わると日本は民主化し、国が人を堂々と縛ることはできなくなります。三島自身も大人になって、少年の頃のように、縛られて当然の存在ではなくなってきました。そうして彼は、次第に自らの手で自らを縛る道を歩むようになるのです。
細江英公による写真集「薔薇刑」には、褌姿で荒縄に縛られている、三十代末の三島の姿が。また四十歳の時に映画化された「憂国」では自身が主演を務め、二・二六事件当時の近衛歩兵一連隊中尉の制服を着て、血まみれで死ぬシーンを演じています。
四十二歳の時は、陸上自衛隊富士学校に体験入隊。「三島由紀夫と自衛隊」(杉原裕介・剛介)によれば、体験を終えた後の昼食会に、三島は一等陸尉の階級章がついた制服を着て登場し、周囲を驚かせています。皆と同じ制服を着たかったということで、富士学校内の洋服店が見本として飾っていたものを買い取ったというのです。そして死の直前、篠山紀信によって撮られていたのは、縄で手首を縛られ、裸体を矢で射られている、あの有名な写真「聖(サン)セバスチャンの殉教」……。
死を迎えるまでの数年間、このように制服やら縄やらによって自ら進んで縛られ、理想とする死の予行演習の数々を行なっていた三島。とうとう昭和四十五年十一月、自らがつくった制服姿で、自刃しました。
しかし、
「服装は、強いられるところに喜びがあるのである。強制されるところに美があるのである」
との言葉を思い出すと、三島の最期が彼にとって理想的なものであったのかが、わからなくなります。数々の予行演習から自刃まで、彼は拘束衣を着続けたけれど、それは「強いられた」ものではなかった。縛られ、射られることを望み続けながらも誰も彼を縛ってはくれず、最後に自分で自分の制服をつくらざるを得なかったところに、彼の最大の不幸があったのではないかと私は思います。
***
【参考文献】
(1)『仮面の告白』(新潮文庫、一九五〇)
(2)『若きサムライのために』(文春文庫、一九九六)所収
(3)『決定版 三島由紀夫全集 第35巻』(新潮社、二〇〇三)所収
(4)『決定版 三島由紀夫全集 第34巻』(新潮社、二〇〇三)所収
(5)『決定版 三島由紀夫全集 第37巻』(新潮社、二〇〇四)所収
株式会社新潮社「yom yom」のご案内
https://www.bookbang.jp/yomyom/
新潮社の雑誌「yom yom(ヨムヨム)」は2006年に創刊され、朱野帰子『わたし定時で帰ります。』、重松清『一人っ子同盟』、辻村深月『ツナグ』、畠中恵「しゃばけ」シリーズなど大ヒット作を数多く掲載してきた文芸誌です。「いま読みたい作家」による「いま読みたい物語」を掲載する――という創刊時からの編集方針はそのままに、WEBマガジンに舞台を変え、読者の皆さまにより近い場所で、「いま」の欲望に忠実な新しい物語を紹介していきます。
関連ニュース
-
酒井順子×穂村弘 妄想で語れ、「源氏物語」!~酒井順子『源氏姉妹』刊行記念対談~
[イベント/関東](歴史・時代小説)
2017/02/01 -
あさのあつこ・神永学による人気シリーズが連載スタート 綾辻行人によるAnotherも連載再開
[リリース](日本の小説・詩集/歴史・時代小説/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド/SF・ホラー・ファンタジー)
2018/07/12 -
光浦靖子と酒井順子『子の無い人生』から見た「保育園落ちた日本死ね!!!」を語る
[ニュース/テレビ・ラジオで取り上げられた本](エッセー・随筆/古典)
2016/03/17 -
三島由紀夫の存在を誰よりも意識して育ったハリー杉山 その思いを語る
[特集/特集・インタビュー](日本の小説・詩集)
2020/12/03 -
三島由紀夫の未公開インタビューに触れた稲垣吾郎が衝撃の告白「夜家に帰ったら泣いてますよ」[ゴロウ・デラックス]
[ニュース/テレビ・ラジオで取り上げられた本](自伝・伝記)
2017/08/19