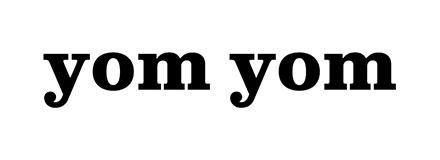会えない三島を追いかけて
「三島由紀夫」と聞くと、そりゃあやっぱりアンテナが動きます。命日になると思い出しますし、関連作品も欠かさずチェックします。それは三島さんへ人としての憧れを感じるとか、好きとかというより、純粋に会いたかった!と思う気持ちが一番強いですね。どんな人だったのか、実際に会って話してみたかった。三島さんの作品から僕の知らない父のことを知りたいと思って読んでいるところもあるので、父についても聞いてみたかった。それに父はよく「あと数年生きていたら三島さんも絶対にノーベル賞が獲れた」「なぜあのときは川端さんだったんだろう」と悔しそうに言っていましたから、今頃ノーベル賞作家になっていたかもしれない。そうしたらもやもやしている現代人に手を差し伸べてくれる存在になっていたかもしれませんよね。
しかし、三島さんがもし今生きていたら、現代の日本を反吐が出るほど嫌うと思うんです。父はよく三島さんのコンプレックスに関する話をしていました。それは、子供の時に病弱で身長が低かったことと、入隊検査に落ちて兵役に就けなかったことをかなり気にしていた、と。個人と国の運命がリンクしていた40~60年代、周囲の人たちが祖国を守るために美しくこの世を去ったのに、自分はできなかった。そのことが大きなコンプレックスになっていたのは作品を通しても明らかです。でも今の日本人の生き方の選択には当時の人ほど深く国や天皇が関係してこないし、トレンドに脳細胞を奪われて自分で物事を決める力すらない人も少なくない。僕自身だって、仕事を全うして自分と家族の幸せを追い求めるのが精一杯で、国レベルでの未来を真剣に追求するなんてことはできません。ヘンリーの息子である僕が三島さんにそんな「生きる情熱」に欠けることを言ったら、きっと顔を真っ赤にして怒られるんでしょうね。
満島真之介の森田必勝
昨年、テネシー・ウィリアムズが三島に捧げた「男が死ぬ日」という舞台への出演が決まり、三島に近づくために、僕は色々な三島関連の作品を見ました。普段から仲良くさせてもらっている満島真之介くんが初めて出演した映画「11・25 自決の日」を観たときに、汚れのない情熱を見事に宿した森田必勝の存在感に興奮し、強く印象に残っていたので、改めて演じた満島くんを呼び出し役作りについて質問しまくりました。彼は役をもらったとき、人柄を知るために何も知識のない状態で一人、森田の地元を歩き回り、自力で森田のお兄さんを探し当てたんです。そのお兄さんが、満島くんに会った瞬間、本当に自分の弟だと思ったと言ってくれたそうなんです。そこから彼はお兄さんの話や文献から徹底的に情報を吸収して、森田研究をした。映画の中の三島と森田が切腹するシーンでは、完全に森田になりきっている満島くんを見た映画スタッフたちが「満島くんは本当に死ぬ気なんじゃないか」と心配したらしいんですよ。それくらい役に自分を捧げたというのを聞いて心底感心しました。長く、難しく、生々しい作品ですが、とても印象に残っています。
最近のものでは「三島由紀夫VS東大全共闘」が面白かったです。はっきりものを言うのに相手を一切貶(けな)さない三島さんの物腰の柔らかさには驚きました。自分の半分くらいの年齢の若造たちがタメ口で食って掛かってきても穏やかに笑っていて、楽しんでいましたよね。相手が学生であろうと政治家であろうと関係なく、どんな人に対してでも真っ向勝負という三島さんの人柄が映っていました。また、現場に顔見知りの記者たちを呼んでおくなどメディアマネジメントの巧みさからも、父が言っていたように自信に満ちた、注目を浴びることを好む三島さんの性格がよく伝わりました。しかしながら、あの討論の場は三島さんにとって非常にエロティックな経験だったかもしれない、とも思いませんか。相手の知性をリスペクトする三島さんが、あれだけ大勢の、しかも挑発的なアカデミックたちに囲まれていたわけですから、一種の興奮状態か、少なくとも彼らから注目される快感を味わっていたのは確かでしょう。
「初体験」にふさわしいのは?
僕は日本で教育を受けた期間が短いので実感はありませんが、日本で育った人に訊くと、学校の教材で三島の作品を習うことはあまりないようですね。だから三島由紀夫は、太宰治のようにみんながみんな作品を知っている作家でないのかもしれません。
僕にとって小説を読むのは、現実逃避の一種です。失恋した女性が占いに頼ってしまうことがあるように、葛藤しているとき、自分の精神をうまくコントロールできないときに僕は文学に頼ることが多いです。でも僕の父はちょっとセンスがずれていて、誕生日プレゼントとして周りの友達が新しいMDプレーヤーとかミニ四駆とかをもらう年頃に、父が僕にくれたのはバルザック、モンテーニュ、エズラ・パウンド……。分厚い本をドカンと渡された当時は、勘弁してくれって感じでした。なので昔から本は身近なところにたくさんありましたが、根っからの文学好きというわけではなくて、父親がいなかったら三島さんの作品に触れる機会は一生なかったかもしれません。
これから三島を読む方にまっとうにお勧めしたいのはやはり『潮騒』になるんですけれども、きっと皆さんそう言うと思うんですよ。なので、今こそ読むべきという意味で、僕からは『仮面の告白』をお勧めしましょう。これは三島さん自身のセクシュアリティの悩みを扱っているというだけでなく、自分自身を知ることの大切さを教えてくれる作品でもあると思うので。人はみんないろいろな仮面を持っているし、その仮面の下に潜んでいる感情が例えばグレーのときも、黄色のときも、ピンクになっているときもある。でもその瞬間に自問自答して、冷静に感情を分析するところまではなかなかたどり着けないじゃないですか。そういう「いつも自分がつけている仮面はなんだろう?」という問いがある作品なので、誰が読んでも響くものがあると思います。
一方で『仮面の告白』こそ三島さんの一番厚い仮面、つまり三島さんは本当はヘテロセクシャル=異性愛者だけどゲイのパフォーマンスをしていたんだ、という人もいます。作品を読んで自分なりの解釈を続けていくことができるのも、文学の面白いところですよね。
ヘンリー・スコット゠ストークス(Henry Scott-Stokes)
1938年、英サマセット州グラストンベリー生まれ。オックスフォード大学修士課程修了後、62年フィナンシャル・タイムズに入社。64年『フィナンシャル・タイムズ』初代東京支局長として来日。67年より『タイムズ』、78年より『ニューヨーク・タイムズ』でそれぞれ東京支局長を歴任した。著作に三島の伝記『三島由紀夫 生と死』(徳岡孝夫訳、清流出版 原題 "The Life and Death of YUKIO MISHIMA")ほか多数。
ハリー杉山
1985年東京生まれ。所属=株式会社テイクオフ。英ウィンチェスターカレッジを卒業後帰国し、投資銀行勤務の傍らモデル活動を開始。その後ロンドン大学東洋アフリカ研究学院(中国語専攻)へ進学。現在モデル、タレント、俳優として幅広く活躍している。
スタイリング=前田順弘/ヘアメイク=豊田まさこ/撮影=坪田充晃(新潮社写真部)
株式会社新潮社「yom yom」のご案内
https://www.bookbang.jp/yomyom/
新潮社の雑誌「yom yom(ヨムヨム)」は2006年に創刊され、朱野帰子『わたし定時で帰ります。』、重松清『一人っ子同盟』、辻村深月『ツナグ』、畠中恵「しゃばけ」シリーズなど大ヒット作を数多く掲載してきた文芸誌です。「いま読みたい作家」による「いま読みたい物語」を掲載する――という創刊時からの編集方針はそのままに、WEBマガジンに舞台を変え、読者の皆さまにより近い場所で、「いま」の欲望に忠実な新しい物語を紹介していきます。
関連ニュース
-
男子11人、女子4人の大家族で愛人もいた貴族とは? 紅茶アールグレイの由来になった伯爵家のお家事情
[ニュース](世界史)
2024/04/15 -
村上春樹によるラジオ番組『村上RADIO』のプレスペシャルが放送
[ニュース/イベント/リリース]
2019/02/01 -
次の大統領もトランプなのか? 注目ルポルタージュの続編が刊行
[ニュース](タレント本/社会学/心理学/エッセー・随筆/演劇・舞台)
2019/10/05 -
日本史の教科書がつまらない理由とは 古市憲寿が提案する『絶対に挫折しない日本史』
[ニュース](歴史学/日本史/社会学)
2020/10/03 -
「世間の常識」とずれていると感じたとき、どう折り合いをつけるのか 養老孟司が『バカの壁』で書きたかったこと[新書ベストセラー]
[ニュース](自己啓発/社会学/家庭医学・健康)
2022/01/29