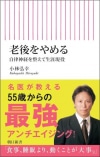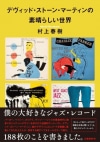ドラマ『VIVANT』の鍵となった「フローライト」もクリティカルミネラル(Image by photoAC)
昨今、世界各国が「クリティカルミネラル(稀少鉱物)」と呼ばれる資源に注目しています。
欧米と中ロを中心に分断された世界の下、すでにアメリカと中国では、その駆け引きが活発化。なぜ世界はクリティカルミネラルに熱い視線を注ぐのか。
日本エネルギー経済研究所専務理事・首席研究員である小山堅氏の著書『地政学から読み解く!戦略物資の未来地図』(あさ出版)から、その理由を紐解きます。
(※以下は『地政学から読み解く!戦略物資の未来地図』をもとに再構成しました)
***
■希少鉱物「クリティカルミネラル」とは
資源のなかで最も熱い視線を注がれているのが「クリティカルミネラル」という稀少鉱物です。
あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、クリティカルミネラルは私たちの生活になくてはならない、でも将来は需要と供給が逼迫するかもしれない希少鉱物の総称です。
代表的な物質にはリチウム、シリコン、ニッケル、コバルト、ネオジム、ジスプロシウムなどが挙げられ、半導体や蓄電池、リチウムイオン電池、電気機器のモーターや磁石などの製造に使われます。
上記の物質は、電気自動車や再生可能エネルギーを生み出す風力発電のタービン、太陽光パネルなどの生産に必要不可欠です。つまり、脱炭素化の取り組みに向けて大きな需要が見込まれているということがまず大切なポイントです。
ただし、これらは稀少鉱物という名の通り、将来的に需給逼迫が懸念されています。早いものでは2020年代半ばに需給が逼迫し始めることも予想され、今後、需給逼迫によってクリティカルミネラルの価格高騰が起これば、その物質の入手はそれまでと比べて難しくなるでしょう。
■持てる国と持たざる国
クリティカルミネラルの問題は、今後の需給の逼迫とそれに伴う価格上昇だけではありません。偏在性が高い物質が多い=供給国が一部に偏る特徴があるのです。言い換えれば、まさに「持てる国」と「持たざる国」に大きく分かれている物質というわけです。これがクリティカルミネラルの重要性を高めており、ほとんどの国ではどれだけリサイクル率を高めても自国内での確保は難しく輸入に頼らざるを得ません。
この事実は、あるクリティカルミネラルの需給が逼迫した場合、その物質を持っている国・地域の影響力が増大することを意味します。
例えば、電気自動車のモーター用磁石の材料となるネオジムやジスプロシウムは、いずれも生産量では中国が圧倒的なシェアを持っています。他にも、リチウムイオン電池に使われるニッケル鉱石などでは中国の生産シェアはそれほど多くないものの、製造コストが安いことから製品としての一次ニッケルのシェアで中国が多くを占めています。これは、世界で再生可能エネルギーの導入が進むほど中国の利益と影響力、存在感が増大することを意味します。とくにネオジムは、あと数年で需要が供給量を上回り、2050年までには現在の4倍以上の需要が発生するとの見通しがあります。
もし、脱炭素のために電気自動車の普及を図れば図るほど、ネオジムの需給は逼迫。それに伴って、ネオジムのシェアを持つ中国の市場支配力が強まり、価格支配権や生産調整で世界に影響を及ぼす“カード”となり得ます。
また、中国がこれらの原料などの供給に制限をかけるようなことがあれば、大きな問題となる恐れもあります。クリティカルミネラルは太陽光発電に使う太陽光パネルや風力発電用のタービンなどの分野にも使用されるため、大きな需要が見込まれる物質だからです。
株式会社あさ出版のご案内
あさ出版は、創業者がビジネス書の出版社出身であることから、1991年ビジネス書分野の出版からスタートしましたが、現在では一般書、語学書にまでジャンルを拡大しています。書籍の力を信じ、すべての働く皆様に、「わかりやすくて役に立つ」書籍を、かつ「生きる勇気・働く情熱」を生み出していただける書籍を発行していくこと、これが私たちの使命です。
関連ニュース
-
過労自殺はなぜ起こる?『「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由』がランクイン【ビジネス書ベストセラー】
[ニュース](自己啓発/一般・投資読み物/株式投資・投資信託/倫理学・道徳)
2017/05/20 -
【深刻】気温上昇で「高温」も「豪雨」も増えるのに…世界が「温暖化」を解決できない理由とは
[ニュース](科学)
2023/08/29 -
不良資産になっていた裏山の売却に5年……相続専門の税理士が父親を説得するまで
[ニュース](金融・ファイナンス)
2022/06/01 -
「日本はアピールが下手」でも自信を持っていい理由 外国人も共感する、あえてナンバーワンを主張しない日本のスタンス
[ニュース](外交・国際関係/社会学)
2021/12/25 -
「弊社に来てください」という会社とは仕事が成約しない説 依頼の仕方でわかる要注意な取引先
[ニュース](ビジネス実用)
2023/06/13