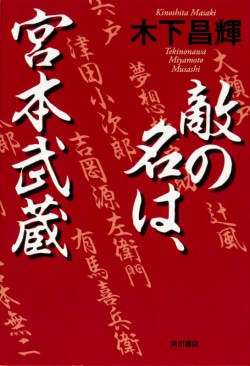『敵の名は、宮本武蔵』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
〈刊行記念インタビュー〉木下昌輝『敵の名は、宮本武蔵』
オール讀物新人賞で鮮烈なデビューを飾り、
2014年にはその受賞作を表題作とした
『宇喜多の捨て嫁』が直木賞候補に選ばれるなど、
一躍時の人となった木下昌輝さん。
満を持して、本誌インタビュー初登場です!

――まずは木下さんのデビューまでの歩みを教えてください。
木下 大学の建築学科を卒業後、ハウスメーカーに就職して五年ほど働いていました。高校生の時からいつかは小説家になりたいと思っていたのですが、同級生がアドバイスをしてくれて。「小説家になるには〝引き出し〟が必要や。でないとエロ小説しか書かれへんようになるぞ」と(笑)。それで理系に進むことにしたんです。今思えば有意義なアドバイスだったかもしれませんね。
――二十八歳で会社を辞め、フリーライターになられました。
木下 関西の情報誌を中心に、主に飲食店の取材をしていました。グルメライターになったのは、食べるのが好きという理由もありますが、一番取材に出られそうだと思ったので。ラーメン屋やお好み焼き屋の店主に会って、その人の人生について話を聞けるわけですから、小説家としての引き出しを増やすチャンスになるかな、と。頭の片隅には、やっぱり小説家になりたいという思いはありましたね。
――ライターから小説家に転向されたきっかけは何だったのでしょうか。
木下 小説家になりたいと思いながらも、当時はまだ実際に書いてはいませんでした。ご飯も食べていけていたし、「このままでもいいのかな……」と考えたりもしましたが、十年ほどすると仕事が来なくて食えなくなってきた(笑)。しかも、同じ時期にヘルニアになって動けなくなってしまって。それで小説を書こうと思い立ちました。
――創作活動はどのように進められたのでしょうか。
木下 最初に書いたのはファンタジーです。東村アキコさんの『ひまわりっ~健一レジェンド~』という漫画の中に、「学園☆三国志」という作品が出てくるんですが、それをヒントに織田信長が三国志の世界に行ったら……という設定の作品を書いた。すると、三百〜四百枚の長編が書けたんです。
ただ、それが面白いかどうかはわからないので、大阪文学学校というところに行ったんです。別の短編を読んでもらうと、「君なら直木賞を獲れる!」と言ってくださって。そこでの薦めに従って、「オール讀物」に出してみると、二次選考まで残れた。それを励みに一年間頑張って、「オール讀物」の新人賞をいただくことができました。それがデビュー作『宇喜多の捨て嫁』の冒頭作です。
「敵」の視点から、
新しい宮本武蔵を描く

――今回の作品は、剣豪・宮本武蔵の姿を対戦相手の視点から描く斬新なものです。このアイデアはどのように生まれたのですか?
木下 編集者との打ち合わせで「何か書きたいものはありますか?」と聞かれた時に、この作品にも登場する「吉岡憲法の話を書きたい」と言ったんです。吉岡憲法は、京都の吉岡流の四代目当主で、武蔵と戦って敗れ、晩年は染物業に専念したと伝えられている変わった経歴の剣術者です。
しかし、編集者から「長編にできますか?」と聞かれて、読者の身になって考えると、そんな長編なんか誰も読みたくないやろうなと思って(笑)。それでどうしようかと考え、ふと宮本武蔵の敵を主人公にした連作短編はどうかと提案したんです。
――宮本武蔵は日本人の誰もが知る、歴史上でも有名な人物です。
木下 武蔵が一人で武者修行の旅に出ていたというのは、実は講談によって広まった物語なんです。武蔵を題材にした作品は無数にありますが、どれも二次創作しかしていない。史実では大勢の弟子を引き連れていたことがわかっているのに、誰もそんな姿は書いていない。でも、それはエンターテインメントとして大正解なんです。だってたくさんの弟子に囲まれた武蔵が敵に勝っても、盛り上がりませんからね。
ただ、敵側の視点から見れば、武蔵と同じくらい強い奴が十数人いるところに一人で立ち向かっていくわけですから、十分にエンターテインメントになる。最初は思いつきでなんとなく言ったものの、話すうちにだんだんと乗ってきて、新しい形の宮本武蔵像を描けるかなと思ったんです。
――作中には吉岡憲法をはじめとする名だたる武芸者たちが登場します。
木下 武蔵に敗れた多くの人物のうち、誰を書くのかはとても迷いましたね。最初に登場する有馬喜兵衛は、締め切りが迫っていて切羽詰まってなんとか書いたんですが、完成して「やってしまった!」と後悔しました。宮本無二(武蔵の父親)を登場させたので、連作短編の中でこいつを絡ませないといけなくなった。めっちゃハードルを高くしてしまったなと思いましたね(笑)。
ところが調べてみると、実は巌流島での佐々木小次郎との決闘に、無二が関わっていたらしいことがわかった。それで、無二を絡めた方が面白くなるんじゃないかと考え方を変えて。結果的には、そうやって自分を追い込んだのが功を奏したのかもしれません。
勝者より敗者に光を当てたい
――宮本武蔵の敵ということは、つまり「敗者」が主人公になります。木下さんの作品には「敗者」をテーマにしたものが多いですが、どんな理由があるのでしょうか?
木下 確かに負けた人ばかりですが、書くのは楽しいですよ。大阪では、「負けてからどう立ち上がるかで男の価値は決まる」と言われることがあります。僕自身も実家が町工場をやっていたこともあって、取引先が手形の不渡りを出す場面などをたくさん見てきました。「不渡りを出してからが勝負」じゃないですけど、敗者に光を当てたいという気持ちは、僕の中に常にあるテーマです。
小説で竹内流武道を
体現してみたい

――武蔵に決闘を挑んだ武芸者たちが敗北していくシーンは、非常に読み応えがあります。
木下 それはもしかすると、僕がライターの頃に竹内流という武道を習っていたことと関係があるかもしれません。当時はよくわからなかったんですが、今になって気づいたことがあるんです。それは、「弱者に寄り添う」ということです。自分が弱いことを前提にして、すべての技がある。だから、仲間に裏切られた時にどう返すかとか、逆に相手をどう裏切るかとか、そんな技ばかりなんです。
――竹内流という武道が、本作の重要なモチーフの一つになっているのですね。
木下 竹内流はもともと美作国(岡山県東北部)が発祥です。戦国時代、美作では下克上が激しく、裏切り行為も頻繁に行われていました。他人を出し抜かなければ生きていけない。竹内流はそんな人たちに寄り添った武道なんです。だから、男性だけではなく女性もたくさん習っていました。女性には、「寝る時は必ず目つぶしを枕元に置いておけ」など、けっこう強烈なものもあります。それも弱い者の武道だからこそですよね。そういうことを僕は小説を通してやってみたい。
『宇喜多の捨て嫁』を書いた時に竹内流について調べていると、本当に悲惨な人がいっぱいいたんです。宇喜多直家の家臣の戸川平助(秀安)という人物のお母さんは、息子の平助とその妹の二人の赤ちゃんを連れて放浪するはめになり、両方は育てられないからと女の赤ちゃんを殺してしまう。僕はそういう人を単なる被害者や悪人で終わらせたくないんです。敗者に対する価値観を変えて勝者にすることで、いわば僕なりに小説で竹内流を体現しているつもりなんです。
――各編の主人公はみな負けてしまいますが、ある意味で心温まるラストが待ち受けます。敗れた人、弱い人への優しさや共感を覚えました。
木下 実家の町工場の話に戻りますと、幸いうちは不渡りを出さずに済みましたが、一歩間違えば取り立てられる側になって、追い込みをかけられていたかもしれない。そう考えると鬼にはなれません。祖父も一度、不渡手形をつかまされたことがあったけど、一切相手を責めなかったと父親が話してくれました。反対に、「自宅の名義は奥さんに変えときや」とアドバイスまでしたらしい。そういう経験をしているので、いつ立場が逆転するかわからない、次は自分が敗者になるかもしれないという感覚はよくわかるんですよね。
小説を通した「実験」

――前作『戦国24時 さいごの刻』では、ある人物が死ぬまでの最後の二十四時間だけを描くなど、木下さんは作品の中でさまざまな試みをされています。今回はいかがですか?
木下 一番大きかったのは、弟子を引き連れた武蔵を書くということです。それは軍事力で考えれば十万石の大名に匹敵する。そういう武蔵に対して読者が感情移入してくれるかどうか。史実ではあるんですが、「弟子をいっぱい連れていたなんて嘘だ」と言われないようにしなければと思っていました。
もう一つは後世の視点を入れることです。「こういう歴史的事実があった」という註釈的な記述を二箇所入れています。これまでの作品では徹底して排除してきたのですが、今回はその歴史的事実をわかった上で読んだ方が、絶対に読者は楽しめると感じたので、なんとかして入れたかったんです。
ただ、やり過ぎてもいけないので、インデント(字下げ)して雑誌のコラムのように見せる工夫もしています。歴史小説でのこういう試みには賛否両論あると思いますが、読み返してみても違和感がなかったので、いけるのではという手応えがあります。
――作品の中盤からは、「飛刀の間」という剣の間合いについてのやり取りが大きなテーマになります。剣の動きや人物の体感を文章で表現することにも苦労があったのでは。
木下 剣については、二天一流剣術免許皆伝の太田淳一師範に取材をさせてもらいました。太田先生の解釈では、二天一流とは「相手の剣をギリギリまで引き付ける武道」。ある点まで引き付けられたら剣の動きは変えられないから、後はそれを払ったり避けたりするだけでいい。思い切り叩き込まなくても、簡単に相手を倒すことができる。これが二天一流の奥義だと教えてくださいました。
実家が町工場だったせいか、職人が好きなんです。だから、武道家も職人として書きたいと思ったんですが、職人なら技が上達したことが端的にわかった方がいいですよね。文章では伝えづらいんですが、太田先生のおっしゃった「引き付ける」ということなら、技量としてイメージしやすい。それを「飛刀の間」という言葉で表現したんです。また剣だけではなく、武蔵が絵の才能にも秀でていたという逸話を取り入れられたのもよかったと思います。
――最後に、この作品をどんな人に読んでほしいと思いますか?
木下 高校生直木賞をいただいたから言うわけではないですけど、若い人に読んでほしい。若い人たちがこの本を読んで喜んで、頑張ろうと思ってくれたらいいですね。それを意識して、専門用語もわかりやすいように書いたり、読み慣れた人にはわかる言葉でも少し説明を入れたり、地味な努力はしているんですよ(笑)。歴史小説はおじさんの読みものみたいなイメージがありますが、もっと若い人に読んでほしいと強く思いますね。
木下昌輝(きのした・まさき)
1974年奈良県生まれ。2012年「宇喜多の捨て嫁」で第92回オール讀物新人賞を受賞し、『宇喜多の捨て嫁』で単行本デビュー。同作は直木賞候補となり、15年高校生直木賞、歴史時代作家クラブ賞新人賞、舟橋聖一文学賞を受賞。2作目の『人魚ノ肉』は山田風太郎賞の候補となる。近刊に『戦国24時 さいごの刻』。