【ハマるぞ!伊岡瞬】50万部は伊達じゃない!面白すぎて止まらない、衝撃の法廷サスペンス。――『代償』
レビュー
『代償』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
【ハマるぞ!伊岡瞬】50万部は伊達じゃない!面白すぎて止まらない、衝撃の法廷サスペンス。――『代償』
[レビュアー] 香山二三郎(コラムニスト)
『代償』(角川文庫・2016年)巻末に収録されている「解説」を特別公開!
伊岡瞬といえば、まずデビュー作の第二五回横溝正史ミステリ大賞受賞作(テレビ東京賞とのW受賞)『いつか、虹の向こうへ』(角川文庫)である。主人公は自分の家にワケありの男女を住まわせている元刑事。そこに新たな居候が現れるが、彼女は殺人事件の容疑者に。職も家族も失った中年男とは一見負け犬ヒーロー的で、いかにもハードボイルドなタッチを思わせるが、その実、疑似家族設定を活かした確かな人間ドラマ演出で読む者を感動させた。
その後の伊岡作品も題材は異なれど、弱者の再生譚を軸に確かなドラマ演出が読みどころになっていたが、作家デビューして一〇年目を迎えようとしたとき、ひと皮むけたというか、化けたと思わせる作品が登場した。本書『代償』である。
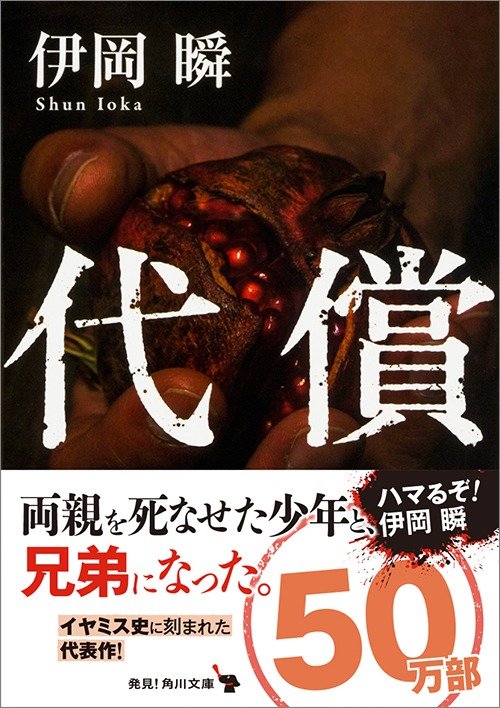
【ハマるぞ!伊岡瞬】50万部は伊達じゃない!面白すぎて止まらない、衝撃の法…
著者の長篇第四作に当たるこの作品は二〇一四年三月、KADOKAWAから書き下ろしで刊行された。今度の作品は今までとはちょっと違うぞと思わせるその第一のポイントは悪役の造形だ。
物語は一九九九年夏に始まる。ノストラダムスが予言したという世界の終末は訪れなかったが、東京・世田谷の団地に住む小学五年生の奥山圭輔の身辺では静かに崩壊が始まっていた。私鉄の線路を挟んだ反対側にある団地には母の遠縁に当たる浅沼家が住んでいた。奥山家と同様、両親と圭輔と同い年の息子の三人家族だったが、いつしか月にいちど、金の無心に母・道子が息子の達也をつれて訪れるようになっていた。内向的な圭輔に対して達也は大柄で敏捷、野性的な雰囲気を漂わせ、上辺は如才なかったが、その半面、下品で冷酷そうな一面も見せており、圭輔とはウマが合わなかった。家族キャンプに誘ったのをきっかけに達也は奥山家にひんぱんに出入りするようになるものの、金や物品の紛失が頻発し始めたことから一家は彼を遠ざける。しかし年末年始、浅沼夫妻が仕事の関係で東京を留守にする間、達也を預かることとなり、迎えた一二月二八日に悲劇が。
煙草による失火が原因か、突然の火事で両親と家をも失った圭輔。彼の面倒は後見人となった浅沼家が見ることになるのだが、その生活はというと、ひと言でいえば奴隷状態。食事から衣料品、入浴に至るまで最低限のことしか与えられず、薄汚れのネクラ少年と化した彼は、学校でも孤立していく。本書は二部構成になっているが、その第一部は圭輔の受難の少年時代が淡々と描かれていく。そしてそこから逆照射されるのが、浅沼道子と達也のモンスターぶりだ。奥山家の火事も、その後の一家の財産処分も、ウラで親子が関わっているであろうことは読者もうすうす気づかれるに違いない。
一家の乗っ取りといえば、二〇〇二年に北九州市で発覚した連続監禁殺人事件や、一二年に兵庫県尼崎市で発覚した連続殺人死体遺棄事件を思い起こされる向きもあろう。人の心をあやつり命までもてあそぶとは、カルト宗教も顔負けの所業。そう、そんなことを仕出かすのは集団ヒステリー的な熱狂に駆られた組織的なものでしかありえないと思いきや、近年は個人中心のあやつり犯罪も明るみに出るようになった。後味の悪い嫌なミステリー──通称〝嫌ミス〟人気の高い昨今の犯罪ミステリーシーンでも題材に取り上げられるケースが増えつつあり、本書もまたその典型というべきか。
ちなみに著者自身は本作の執筆動機について、次のように述べている。
「まず、今まで自分の書いたものを振り返ってみました。ミステリなので犯人・悪人が出てきますが、その人たちにも事情があって、弱さゆえに罪を犯したり道を踏み外したりする人が多かったんですね。今度はそうではなくて、全く人を顧みない、全く反省しない根っからの悪を書いてみたいと思い書き始めたのが『代償』です」集英社文芸単行本公式サイト『RENZABURO』インタビュー第25回
読みどころの第二は前述した二部構成に基づくプロットの妙。地球は生き延びたが自らの世界は崩壊してしまった圭輔だったが、幸い読書という趣味を通じて知り合った親友・諸田寿人とその親戚筋に当たる牛島肇・美佐緒夫妻の助力により、中学校の卒業を前に浅沼家を出、牛島家の庇護のもと進学して弁護士となる。後半の第二部は、二五歳になった彼が、実力派弁護士の白石慎次郎率いる法律事務所の若手弁護士として活躍しているところから始まる。そんなある日、彼を名指しで依頼してきた強盗致死事件の被疑者が現れる。親の離婚で浅沼から安藤姓になった達也であった。
達也たちとの関係を断ち切ったと思い込んでいた圭輔は再び過去に引きずり戻されていくが、第二部は一転して法廷劇──リーガルミステリーのスタイルで、圭輔と達也の戦いが繰り広げられるのだ。第一部で描かれた受難劇のあまりの痛々しさに心が折れそうになった読者も、今度は殺人事件の謎解きという新たな興味とともに読み進めていくことが出来よう。もちろん第二部を法廷劇にしたのは、悪い人間をいつまでも野放しにしてはいけないという因果応報的なメッセージもあろうか。
その点について著者は「凶悪犯罪ものの映画だと、このまま警察に捕まって終わりじゃ俺の気が済まないよ? って思いながら見るわけですよ。終盤までイライラしても、最後はスッキリ終わって欲しい。『代償』で最も大変だったのも、達也にどう代償を支払わせるのか、そのラストでした。ここまで悪いことをやっている人物だと、捕まる以上のことを予言した終わりじゃないといけないなぁと。今回は満足のいくラストにできました」(『RENZABURO』同インタビュー)との由。
一気にラストまで飛んでしまったが、読みどころの第三は、リーガルミステリーとしての妙だ。圭輔が達也の弁護を引き受ける羽目になるとは何とも皮肉な展開だが、その事件とは──四ヵ月前の夜、板橋区の運送会社が強盗に襲われ、社員のひとりが撲殺された。犯人は九三万円余を奪って逃走。遺留品はなかったが、内部事情に詳しい者の犯行との見方から、やがて一ヵ月前に勤務態度の不良を理由に解雇された達也が浮かび上がった。その後彼の自宅アパートのタンスの引き出しにあった一万円札から被害者の指紋が検出され、アパートの敷地内からも被害者の血痕の残る特殊警棒が発見された。他にも複数の理由から逮捕に至り、被告も犯行を認めたものの、直接証拠も決定的な自白もまだだった。圭輔はいったんは弁護を断るが、程なく達也本人から依頼状が届き、その中で、圭輔が秘密にしてきたかつての火事の夜の秘密を握っているようなことがほのめかされていた。彼は仕方なく接見に出向き、否応なく弁護を引き受ける羽目になる。
事案が殺人事件だから、行われるのは当然ながら裁判員裁判だ。圭輔のボス、白石慎次郎も「良くも悪くもテレビドラマっぽくなる」という裁判員裁判とは、特定の刑事裁判において一般市民から選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する裁判制度のことで、二〇〇九年五月に施行され、同年八月に初めての公判が行われた。この制度は「司法に関してずぶの素人に、数日の公判に臨んだだけで判断を強いる。しかもあえて、死刑も含めた重い量刑の犯罪に適用している。考えかたでは少し乱暴な制度だ」が、そのために公判前に「裁判官と検事、そして弁護人とときによって被告も同席して、お互いの手の内をさらす」公判前整理手続きが行われる。本作もそうした新たなシステムに則った演出が用意されている。公判前整理手続きが近づいたある日、事件の夜に達也と会っていたという女が現れるというのがそれで、そのシーンについては、著者自ら「以前にもこんな展開があったような気がしてきた。(中略)『情婦』という映画だ」と種明かしをしている。
ビリー・ワイルダー監督の『情婦』はアガサ・クリスティーの傑作『検察側の証人』の映画化作品で、第一部でも圭輔と親友・諸田寿人との出会いのシーンで言及されていたが、まさか第二部でそれが活かされようとは思いも寄らなかった。ミステリー読みのハートをがっつりとらえる演出で、クリスティーばりだがクリスティーとはひと味違うヒネリ技が繰り出されるであろう予告にもなっていよう。「本はもちろん、映画を見るのも好きなので、小説に絡めることがあります。書き終わってから思ったことですが、例えば達也の造形は、『時計じかけのオレンジ』(1971/イギリス)の、あのむき出しの暴力表現のエッセンスが入ってるかもしれません。借り物の表現にならないように気を付けていますが、今まで読んだり見たりした作品の影響は、かなり出ていますね」(『RENZABURO』同インタビュー)と著者は謙遜しているが、本作は裁判員裁判の特徴と映像的な演出、そしてミステリー的な展開が見事にマッチした作りになっているのだ。
ちなみに本作は二〇一四年の第五回山田風太郎賞の候補に推挙されている。惜しくも受賞は逃したものの、この年著者は本作以外にも『もしも俺たちが天使なら』(幻冬舎)と『乙霧村の七人』(双葉社)の二冊を上梓している。デビューして約九年、著作が『代償』までで六冊ということからすると寡作ともいえようが、翌一五年には『ひとりぼっちのあいつ』(文藝春秋)が出て、一六年四月の時点でも複数の作品が雑誌連載されている。作風が多彩になり、版元が分散していることからしても、一四年は著者にとってブレイクの年だったというべきだろう。
伊岡瞬は今が旬! ミステリーファンは見逃すな!
▼伊岡瞬『代償』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321511000303/



































