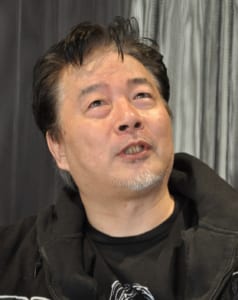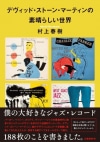『新マーケティング原論』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
よいアイデアを見つけるには、たくさんの「選択肢」を出し「優先順位」をつけることが有効
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
『新マーケティング原論 ──「売れる戦略」のシンプルな本質』(津田久資 著、ダイヤモンド社)の狙いは、“ふつうの読者が「たしかにね」と感じるであろう常識に基づいて、マーケティングの土台を整理すること”なのだそう。つまり、マーケティング原理の体系化を目指しているということです。
具体的には、マーケティングのツールとされているものの原理を解剖し、「そもそもなぜそうだといえるのか?」にまで遡って考えていこうとしているのです。なお著者は、冒頭で以下のような問いかけをしています。
QUESTION
「4Pはなぜ『4P』なのか?」
いまのあなたに最もしっくり来る回答を①〜④のなかから選んでみてください。
ANSWER
① 「なぜ『4P』なのか、きっちり説明できます!」
② 「説明する自信はないけど……4Pがなにかは知っています」
③ 「説明できなさそうだし、4つのPってなんだったっけ……」
④ 「え? 4P……ってなんですか? 初めて聞きました」
(「はじめに」より)
4Pとは、「Product(商品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販売促進)」の頭文字をとったものであり、マーケティング戦略を立案する際のもっとも有名なフレームワークのひとつ。
つまりこれは、「なぜ4Pというフレームワークでは『この4つのP』を考えることが推奨されているのか?」「なぜ『3つのP』や『5つのP』『別の4つ』ではダメなのか?」を問いかけたもので、②〜④を選んだ方に向け本書は書かれているわけです。
きょうはそのなかから、第1章「マーケティングの『定義』論」に焦点を当ててみたいと思います。
なぜ定義が必要なのか
「マーケティングの定義について考えましょう」といわれたとき、「定義なんて学んでも、実践では何の役にも立たない」と感じたとしたら、それは大きな誤解だと著者は述べています。
なぜなら、「定義=役立たないもの」という考え方は、定義の本来の役割が認識されていないために生まれる勘違いだから。
そこで、ここでは次のようなクエスチョンが投げかけられます。
QUESTION
自分なりに「マーケティング」を定義してみてください。
そのとき、どんなポイントを重視しますか?
(41ページより)
定義を考えるときには、たとえば「モノを売り込むための活動」など、なんらかのポイントを意識するはず。たしかに、マーケティングがなにかを「売り込む」ことに関係するものだということは間違いないでしょう。
とはいえそのあとで、「でも、モノだけではなくサービスも含めたほうがいいかな?」「これだと『セールス』の定義と同じになってしまうのでは?」などの疑問が浮かんでくるかもしれません。そのような思考に至るということは、各人が「いい定義」の条件を多少なりとも意識しているからだと著者は指摘しています。
まず、その名称が「マーケティング(Marketing)である以上、マーケティングは「行動」であるはずです。
だとすると、その定義もまた、「とるべき最適な行動」が決まるようにデザインされていることが望ましいでしょう。
逆に、よくない定義、ダメな定義があるとすれば、それは「最適な行動の決定」に寄与しないものだと言えます。
たとえば、上記の「マーケティング=モノを売り込むための活動」という定義が与えられても、おそらくほとんどのマーケターは、これをもとにして自分のとるべき行動を決定づけることができません。(42ページより)
マーケティングの定義が曖昧だということは、マーケターが自分の仕事を曖昧にしか理解できていないということ。そのため“やるべきことが明確になっていないマーケター”は、いつの間にか思い込みにとらわれたり、その場の思いつきで選んだ行動に手を出してしまいがちだというのです。(40ページより)
「発想量」が結果を決める
マーケターに要求されるのは、自らの頭を使って「とるべき行動」を考えること。そこでどれだけ「いい行動案」を発想できるかが勝負になってくるということです。
なお著者によれば、より質の高い行動案を発想するためには、以下の2段階のプロセスを踏むことが重要であるようです。
① 行動案を「できるかぎりたくさん」考える(発散)
② それらの行動に「優先順位」をつける(収束)
(43ページより)
まず①でいう行動案は、マイナスの結果をもたらさない行動のアイデアすべてを指すもの。行動案には「いかにも効果が生まれそうなもの」から「陳腐でいまひとつなもの」までの質的な差が生じるでしょうが、それでも行動案の「量(多様性)」が重要だというのです。
もちろん量が多くても、その種類が多様でなければ意味はありません。とはいえ案の数が多ければ多いほど、よりよい案が生まれてくる可能性が高まるわけです。
しかしマーケティングが企業活動のひとつである以上、すべての可能な行動を実行することは不可能。企業の資源(ヒト・モノ・カネ)には限りがあるからで、そのため複数の行動案のなかから最適なモノを選ぶ必要が出てくるのです。
そのときに避けて通れないのが②の「優先順位づけ」です。行動案のなかに順序をつけることで、まず手をつけるべき最適な行動(またはその組み合わせ)が決定するのです。(43ページより)
この2段階は、それぞれ先述の「①発散」と「②収束」に該当するもの。マーケティングに「考えること」が要求される以上、このようなプロセスと切っては切れないわけです。したがってマーケティングの定義も、「発散→収束」のプロセスを補助するものであることが理想的だということです。(43ページより)
著者は1万人以上を指導してきたというマーケティングのプロフェッショナル。そうした実績に基づいてフレームワークの「原理」から問いなおした本書は、“マーケティングの土台を整理する”ために役立ってくれるかもしれません。
Source: ダイヤモンド社