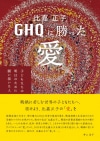『列』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『列』中村文則 著
[レビュアー] 横尾和博(文芸評論家)
◆不条理はらみ続く人生
不条理とは他者や世界との関わりが条理や道理にあわないこと。文学ではカミュ、カフカ、安部公房などが代表格である。たとえばベケットの『ゴドーを待ちながら』は、ふたりの男が一本の木の下でゴドーという人物を待ち続けるだけの話。なぜ待つのか。約束はあるのか。ゴドーとは誰か。なにも説明はなく意味もわからない。ゴドーとは「神」の比喩ではあるが、解釈は読者の自由に任される。
本書も不条理文学である。3部構成で第1部はただ列に並んでいるだけの男の話。列にいつから並び何のためか、理由や意味は一切語られない。列は複数存在するようだが、先頭は見えず最後尾も不明。第2部は猿の生態を研究する非常勤大学講師の男が、猿と人間とを比較し知性、悪、道徳をとおして生のあり方を考える。
第3部では再び列の話に戻り、猿研究者としての生き方を考える話。列とは男の白昼夢か。全編をとおして人間の理性、共感、道徳性の能力を問う。人間には知性がある。だがたとえば戦争だ。なぜ知性ある人間が同種同士で殺しあい、倫理に欠けた愚かな存在なのか。根源である知性や道徳はどこにいったのか。著者の素朴な疑問が胸に突き刺さる。
私たちは行列をつくる。それは欲望を満たすためだ。「行列ができる」を売り物に消費を煽(あお)る世の中。しかし本書で語られる列とは何か。それは人生の比喩である。長くて短いような人生だ。先は見えないが確実にやってくる死。列から外れドロップアウトは可能だ。長い人生の列では順番を待ちきれず、また待つことの虚(むな)しさに耐えられずエゴを剝(む)き出し、反目や小競り合いを繰り返す。だが自分は列を拒否しても、無意識にどこかの列に連なっているのかもしれない。
著者はこれまでも一貫して悪をテーマに作品を追ってきた。哲学的で重い主題は現代文学に欠けている。
人は条理だけでは生きてゆけない不思議な生き物だ。ドストエフスキーは『地下室の手記』でそう書いた。
(講談社・1540円)
1977年生まれ。作家。『逃亡者』など。中日文化賞受賞。
◆もう1冊
『砂の女』安部公房著(新潮文庫)。砂穴に落ち脱出できない男の話。