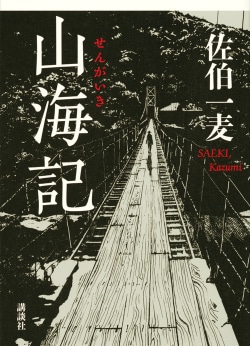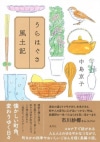『山海記』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
山海記(せんがいき) 佐伯一麦(かずみ)著
[レビュアー] 宇江敏勝(作家・林業家)
◆災害の記憶たずねる私小説
奈良県橿原(かしはら)市から和歌山県新宮市へ、紀伊半島百六十七キロを六時間余りかけて縦断する路線バスがある。そこでの見聞に絡ませて、震災や水害など大自然の脅威と人間の営みについて考察した創作である。
東日本大震災から五年後の二〇一六年一月と、その二年後。バスは曲がりくねった狭い山道を雪降りに難渋しながら進む。通過する十津川村(とつかわむら)は日本一面積の広い村で、昔から秘境と呼ばれている。一八八九年の大水害で壊滅的な打撃を蒙(こうむ)り、住民の二割が北海道へ移住して、そこが新十津川町になった。さらに東日本大震災と同じ二〇一一年には、紀伊半島大水害によって多くの犠牲者を出している。
著者は仙台市在住の作家で、さきの大震災を体験している。そこから発心して「水辺の災害の記憶を訪ねる旅」を続けているという。十津川は全村が重畳たる山国である。険しい急斜面に家をかまえ、畑を耕し、木材に関わる生業(なりわい)を続けてきた。大雨によって斜面が根こそぎ崩れるのを深層崩壊という。土砂は深い溪谷(けいこく)をせきとめて湖となり、あたかも津波のように逆流する。自然と関わる暮らしの営みが深いだけに、牙をむいた山河とじかに対峙(たいじ)しなければならない。自然のきびしさを知るうえで、十津川を選んだのは適切かとおもわれる。
生活用の吊(つ)り橋では日本一長いといわれる谷瀬(たにぜ)の吊り橋は名所なのだが、著者は時間をかけて吊り橋に頼る土地の暮らしや観光客、さらには水害の爪痕におもいを寄せる。行きずりの人々との会話の記録も生きいきとしている。
同時に、クラシックが好きだった友人の死をめぐる話も挿入している。吊り橋の薄い板は踏むたびにカタカタと音をたて、踏みぬいてしまいそうな不安を感じながら、ウィーン生まれのヴァイオリニスト・クライスラーの弾く詩曲が頭の中で鳴ったともいう。重厚な私小説といえよう。
それにしても、十津川村はさらに広い。支流の奥に分け入って、日常の暮らしの営みを描くことができたら、作品はもっとべつのものになったかも知れない。
(講談社・2160円)
1959年生まれ。作家。著書『鉄塔家族』『還れぬ家』など。
◆もう1冊
佐伯一麦著『麦の日記帖(ちょう)』(プレスアート)。東日本大震災の前後をつづる。