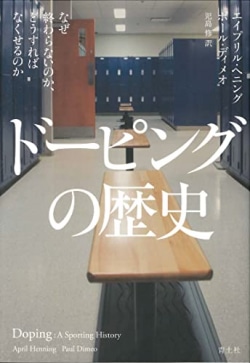『ドーピングの歴史』
- 著者
- エイプリル・ヘニング [著]/ポール・ディメオ [著]/児島修 [訳]
- 出版社
- 青土社
- ジャンル
- 社会科学/社会科学総記
- ISBN
- 9784791775606
- 発売日
- 2023/05/26
- 価格
- 2,860円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『ドーピングの歴史』エイプリル・ヘニング、ポール・ディメオ著、児島修訳
[レビュアー] 伊藤洋一(エコノミスト)
■選手交えた議論提言
いつだったか、テレビ番組で女性アスリートが「眠りについた夜中に、ドーピング検査で起こされたことがある」とこぼしていた。検査員が同性とはいえ監視されていることもあり、採尿に時間を要したとか。容赦ない抜き打ち検査が行われることに驚いた。
ドーピングとは、薬物を用いるなどで運動能力向上を図る行為。本書によると、各競技のランク上位選手らは世界反ドーピング機関(WADA)に検査対象として登録され、居場所情報を毎日届ける必要がある。その監視の厳しさは「有罪判決を受けた犯罪者ぐらい」だという。
本書はスコットランドの大学でスポーツ科学を研究する2人の著者が、1世紀以上にわたるドーピングの変遷をたどり、「WADAがアスリートをほとんど信用していない」との考えで進める論考。
薬物はすでに1904年セントルイス五輪のマラソンで使用された記録が残っている。88年ソウル五輪では、陸上男子100メートルで世界新記録を出したベン・ジョンソンが筋肉増強剤を使用していたことが発覚し、大騒動になった。近年はロシアによる国家ぐるみの隠蔽(いんぺい)工作があった。
なぜドーピングはだめなのか。かつては選手の健康が害されるからだと説明されたが、最近は公平ではないからという、いわゆるズルをした選手への感情的な嫌悪感からの批判も強いと著者はみる。
邦訳の副題「なぜ終わらないのか、どうすればなくせるのか」が示す通り、本書は国によって検査体制が異なり公平性が保たれていない点を指摘した上で、選手と議論しながら誰もが納得できる検査体制を構築するよう提言する。
禁止薬物入りと知らずにリップクリームを塗ったり、育毛剤を使ったりしたことで出場停止18カ月は厳しすぎると現行ルールを批判。薬物取締官が選手の自宅を前触れもなく訪問するのではなく、各地に検査センターを整備すべきだとも。ドーピングとされた行為が全て悪ではないという見方は一考に値する。(青土社・2860円)
評・伊藤洋一(文化部)