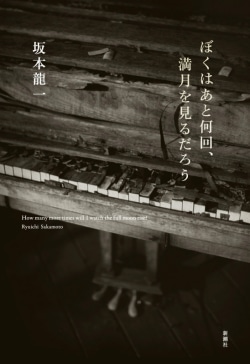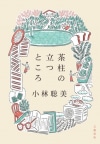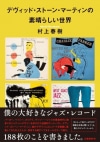『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
最後にゆっくり話せたのは、2015年夏。その時期、彼は……。
[レビュアー] ピーター・バラカン(ブロードキャスター)
坂本龍一を最初に「教授」と呼んだのが高橋幸宏だったことを、この本で初めて知りました。ぼくがYMOの事務所の社員になった1980年暮には関係者全員が彼を教授と呼んでいたのでぼくも最初からそれに倣っていましたし、今も「坂本さん」と書くと不自然に感じるのでここでも「教授」とさせていただきます。
彼の仕事を手伝ったのは1986年までだったので、『戦メリ』には全面的に関わっていましたが、『ラスト・エンペラー』もその後のことも直接の関わりはなく、本人が癌の再発以降を中心に語るこの晩年の聞き書きによる自伝で知ることがほとんどです。
際限ない知的好奇心の持ち主だったことは間違いないです。文中にさりげなく出てくる音楽、本、映画などを聴く、読む、見る時間がよくあったなと感心するほど、超人的なスケジュールをずっとこなしていたのです。ぼくが最後にゆっくり話せたのは2015年夏。自分が監修する「ライヴ・マジック」というフェスティヴァルのパンフレットに載せるための対談に応じてもらったのです。すでに癌の治療中で食事に気を配り、酒もやめていました。時間を割いてくれたことにもちろん感謝していたのですが、その時期に彼がどれだけ忙しかったか、本で読んで改めて驚きました。ちょうど『レヴェナント』の音楽を引き受け、守秘義務のために誰にもそれを伝えられずにいたのです。病み上がりなので果たして受けるべきか悩んでいたところ、パートナーに言われた言葉はこの本の中で特にぼくの印象に残っています。「いま世界中で、あのイニャリトゥ監督から直に音楽を頼まれるミュージシャンが何人いると思う? ガンが再発して死んでもいいからやりなさい」。
教授は特に海外では映画音楽の作曲家として知られています。本人も大島渚とベルナルド・ベルトルッチを恩人と考えていたようです。『戦メリ』と『ラスト・エンペラー』のお陰で様々な仕事の依頼が来るようになる中、U2のボノが訴えた最貧国の債務帳消運動の関係で、ブライアン・イーノから日本代表を頼まれることになります。これがきっかけで、元々社会的な事柄に対する問題意識を持っていた彼は公に声を上げるようになったとも語っています。しかも声だけでなく行動も伴っていたことは特に評価すべきだと思います。
亡くなる直前まで神宮外苑の再開発に反対した彼のそんな見識を無駄にしたくないです。