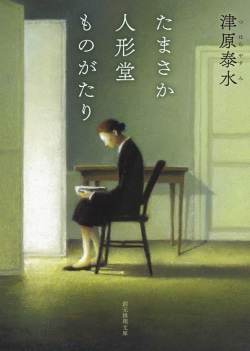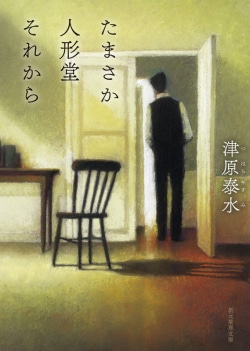天才が語る創作論に、私は喜びで胸が一杯に……イタリア在住の翻訳家が語った「津原泰水」と飲み明かしたTOKYOの夜【津原泰水さん追悼】
エッセイ・コラム
-
- たまさか人形堂ものがたり
- 価格:792円(税込)
小説家の津原泰水さんが、2022年10月2日、闘病の末に亡くなった。津原やすみとして少女小説でデビューし、1997年に“津原泰水”名義の長編ホラー『妖都』を発表。その後は、ミステリーやSF、青春小説、恋愛小説まで、ジャンルを超えて活躍した。
自伝的小説『ブラバン』はベストセラーになり、SFマガジン「2014オールタイム・ベストSF」国内短編部門第1位となった「五色の舟」を収録した短編集『11』は、読者が投票する第2回Twitter文学賞を受賞した。
玄人筋に評価される技巧的な書き手として評価されてきた津原さんの作品は、海外在住の翻訳家たちの応援によって、近年、海外で紹介が進んでいるところだった。Toshiya Kameiさんの翻訳による短編がアメリカの文芸誌に掲載されるほか、2021年に『たまさか人形堂物語』、2022年に『たまさか人形堂それから』(ともにリンダウ出版社)がイタリアで翻訳された。
『たまさか人形堂物語』はイタリア大手新聞社であるコリエーレ・デラ・セラに書評が掲載され、津原さんは出版社主催の読者とのオンライン交流会にも参加し、雛人形を見せながら人形文化について楽しく語り合った。その後、本作はコリエーレ・デラ・セラが編纂する25巻からなる日本文学全集「偉大なる日本文学」の一作として採用されている。
翻訳を手がけたイタリア在住の翻訳家・作家のマッシモ・スマレさんは、あるインタビューで「イタリア人の読者が日本文学の中に探すのは、アジアらしいエキゾチックなモチーフではなく、伝統を受け継いだ現代の日本らしさであり、それを表現する欧米の作品とは違う《物語》とその描き方でしょう」と述べた。そして、津原さんの〈たまさか人形堂シリーズ〉は、イタリアではあまり知られていない日本の人形文化を扱いながらも、登場人物の個性や場面描写の巧みさ、作品の持つ独特の雰囲気が愛されたのだという。
コリエーレ・デラ・セラの記者も、津原さんの訃報に対し、「日本の物語の伝承を受け継ぐ最後の作家たちのおひとりであり、言語による芸術を純粋に探究し続けた作家でした。津原泰水さんの作品との出会いやその記憶に感謝します」と追悼記事を書いた。
本稿では、数多く寄せられた追悼の中からマッシモ・スマレさんが訃報に寄せた文章を紹介する。
***

幻想小説やSF小説など多岐にわたる作品を残した作家の津原泰水さん
私が津原泰水さんを知ったのは、2004年。きっかけは、あるイタリアの出版社の幻想文学アンソロジー「ALIA」に、「約束」と「天使解体」という彼の短編を収録しようとしたことでした。
そのクオリティとオリジナリティに圧倒された私は、ぜひ翻訳させてほしいと連絡しました。彼は快諾してくれたばかりか、私が翻訳作業中に質問をするとすぐに的確な答えをくれました。それから20年近く、『たまさか人形堂物語』や『たまさか人形堂それから』が出版されるまで交流は続きました。
もちろん遠く離れた国に住んでいる私たちがずっと頻繁に連絡を取っていたわけではありません。でも、一度交流が再開すると、あたかも間奏はなかったかのように一瞬で消えてしまって、ここ数年はお互いによくメールをしていました。
津原さんの思い出というと、何年か前のある夜のことが思い浮かびます。私が東京に行ったとき、津原さんはイタリアの事務機器メーカーのオリベッティ社が制作した絵本『不思議の国のアリス』の絵を担当した画家の金子國義さん(1936-2015)を紹介してくれました。台風が訪れるなか、名のある芸術家と作家が誰にも邪魔されずに楽しめるように、私たちは東京の街を彷徨って、夜通し一緒に過ごしました。
朝4時にラーメンを食べて、夜が明けるまでいろいろな話をしました。外は雨でした。津原さんから溢れ出てくる芸術や文化についての知識、そして天才が語る創作論。私は喜びで胸が一杯になり、一分一秒を夢中で味わいました。忘れられない夜です。
彼の不在が日本文学に与える影響は大きいですが、彼の作品は残っています。私たちにとって幸いなことにそれらは永遠に消えることはないのです。
***
-
- たまさか人形堂それから
- 価格:792円(税込)
海外翻訳の現場でも、有名な文学賞を受賞した作家や大ベストセラー、映像作品の原作などが取り上げられることが多いなか、少しずつ評価が進んでいただけに、このたびの津原さんの急逝を惜しむ声は多い。しかし、津原さんは2020年に自身が担当する文章講座で、受講生を相手にこう言っていた。
「僕は、死んだ人と生きた人を区別して書かないんです。それは、死んだら終わりとは思っていないから。死んだあとにその人物に関する掘り下げが進むこともある。死人になったほうが存在感が強くなることもある。だから、死んでも物語から脱落しない。現実にも、金子國義は死んでいる、四谷シモンは生きている。でも、僕はこれを区別しない。会えなきゃいけない、とは思っていないんですよ」
生と死の境界を超えた世界を描き続けた幻想小説家。その唯一無二の才能がこれからもジャンルや時間や場所の境界を超えて、長く読まれ続けていくことを願ってやまない。
関連ニュース
-
「本屋大賞」過去の大賞作・関連作が文庫化で再注目 2020年『流浪の月』2017年『蜜蜂と遠雷』スピンオフがベストセラー
[ニュース](日本の小説・詩集/コミック)
2022/04/16 -
驚愕のデビュー作『屍人荘の殺人』の続編が文庫版で登場 二作目のほうが完成度が高い?![文庫ベストセラー]
[ニュース](日本の小説・詩集/歴史・時代小説/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)
2022/08/27 -
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』のブレイディみかこ 注目の新刊で愛すべき「おっさん」たちを描く
[ニュース](日本の小説・詩集/ライトノベル/歴史・時代小説/エッセー・随筆)
2020/06/20 -
世界で2900万部 中国発の超話題作『三体』 続編がベストセラーランキングに登場
[ニュース](日本の小説・詩集/海外の小説・詩集/歴史・時代小説/SF・ホラー・ファンタジー)
2020/06/27 -
「さっぽろ雪まつり」に最もふさわしい犯罪とは 佐々木譲 道警シリーズ最新作にかけた意気込みを語る[文庫ベストセラー]
[ニュース](日本の小説・詩集/歴史・時代小説)
2022/05/28