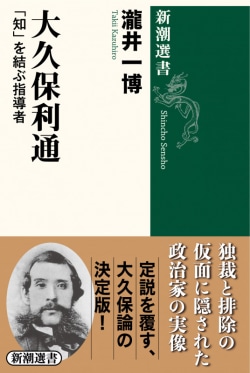-
- 大久保利通
- 価格:2,420円(税込)
旧君を裏切り、親友を見捨てた「冷酷なリアリスト」という評価は正当なのか? 富国強兵と殖産興業に突き進んだ強権的指導者像の裏には、人の才を見出して繋ぎ、地方からの国づくりを目指した、もう一つの素顔が隠されていた。膨大な史料を読み解き、「知の政治家」としての新たなイメージを浮かび上がらせる、大久保論の決定版。
ここでは第一章「理の人」から、薩摩藩の“バンカラ”の気風を享受した大久保の若き日々を描いた冒頭部分を公開する。
***
大久保利通は、文政一三年(一八三〇)八月一〇日、薩摩藩、すなわち現在の鹿児島県に生まれた。生地は鹿児島市内の高麗町であり、そこに生誕の碑が建っている。
だが、より堂々とした「大久保利通君誕生之地」と記された碑は、これより直線距離で約四〇〇メートル。同町を仕切る甲突(こうつき)川の向こう岸の加治屋町に残されている。幼少時に一家で同町に移った利通にとって、こちらのほうが生い立ちの場というにふさわしいということなのだろう。
実際、加治屋町は明治維新の源流地のひとつと呼んで差し支えない土地である。大久保と西郷隆盛が、近所同士で竹馬の交わりを結んだことは有名である。また、彼らのほかにも、税所(さいしょ)篤*、吉井友実、伊地知正治*ら同世代でやはり幕末の動乱をくぐり抜けた英傑や、大山巌、東郷平八郎、山本権兵衛のような維新後に明治国家の屋台骨を支えた歴史的人物がここで生まれ育っている。この小さな界隈で、新時代への革新のエネルギーを秘めた幾多の青年が、幼き時より互いに遊び興じ、切磋琢磨していたのである。そこからやがて、明治維新へのビッグバンが生じる――そう言いたくなる衝動に駆られる。
それはいささか講談めいた解釈だとしても、この狭い町内でともに学び、語り合い、時にぶつかり合って、進取の気性を鍛え上げていった彼らが、西南の地を踏み台に日本という新国家を作り出していった。それは紛れもない歴史の事実である。
そのように述べた時、しばしば薩摩藩で行われていた郷中(ごじゅう)教育が引き合いに出される。郷中とは数十戸を単位とした町内会のような地縁組織で、そのなかで青少年教育がなされていた。そこでは年長者が年少者を教え導くことが指針とされ、そのような密な人間関係のなかで、武士としての士風と道徳を鍛錬することが郷中教育のエッセンスだった。
このような郷中教育が、薩摩における人材養成のシステムであり、幕末における幾多の英傑を生み出した要訣と説明されることが多い。ただ、当の郷中教育は、この時期大きな曲がり角にきていた。嘉永四年(一八五一)に薩摩藩主となった島津斉彬は、その翌年五月に郷中の風紀や秩序の乱れを戒める訓令を出している。そこでは、郷中の体たらくが、例えば次のように指弾されている。
近年、諸士の風俗がよろしくない。ささいなことで争論に及び、竹木をもって打ち合い、郷中の集会などにおいても行儀がなっていない者もあるように聞いている。はなはだもってけしからぬことである。武士道を律儀にたしなめば、このようなことはあり得ないことで、争論に及ぶなどあるまじきことである[1]。
これによれば、近時の藩士の風俗は乱れ、暴力沙汰の争論も頻発していたとある。そしてその弊は郷中にも及んでおり、武士道に鑑みて頗(すこぶ)る問題があると訓示されている。このように旧来の郷中教育はいわば弛緩していて、明君の誉れ高い斉彬のもとで、その締め直しが要請されていたのである。
斉彬が襲封した時、すでに大久保は藩の仕事に就き、齢二十を数えていた。すなわち、大久保や西郷という維新の英傑とされる人は、むしろ郷中教育の弛緩期に人間形成を行ったというのが適当のようである。そもそも郷中教育の本来目指したところは、長幼の序に基づいた年長者による訓導体制であり、それを通じての封建的官僚養成だったとされる[2]。西郷も大久保も上意下達の官僚的分限関係に収まりきれる人間ではなかったし、また収まらなかった破格さに彼らの歴史的価値がある。そのことはこれからの行論で明らかとなっていくだろう。だとすると、むしろ郷中教育が窮屈化する前に、郷中が提供する同志的紐帯に支えられながら、“バンカラ”の気風を享受した世代として、彼らは位置づけられよう。
実際、大久保が残している最初の日記からは、そのように自由に青春を満喫するさまがうかがえる。現存する大久保利通日記の最も古い日付は、嘉永元年(一八四八)のものである。この時大久保は藩の記録所書役助として勤めていた。藩の文書を整理したり、その由緒を照合したりするアーキビストのようなものである。公務の傍らで、彼は記録奉行隈岡五助について和漢の学を学んだ[3]。
日記には、当時一八歳だった大久保の伸びやかな学びの様子が綴られている。学友たちと典籍の素読や会読を重ね、時に連れ立って雄大な鹿児島の情景に抱かれながら詩情を横溢させる青年の姿である。例えば、嘉永元年二月一〇日の日記は次のように書き出されている。
今日は日の出頃に起床。本日も好天で、もはや早春と相成り、すべての景色は改まり、天は茫々と青々しく、山はおぼろげに緑に色づき、春風が柳の枝を払い、池の水をかすかに波立たせている。まことにまことに言葉に尽くしがたく気分は自ずとのどかになってくる[4]。
春の訪れに胸の高鳴りを覚えている若人の心が髣髴される。次の日彼は、学友たちと浜辺に繰り出している。
海の気色は碧く、山々の色は緑にして、日差しは暖色を増している。足に任せて出歩き、御茶屋下に至る。
こゝろからひろくなりたるここちすれ
あおうなはらにふねてせしより
という古歌などを打ち吟じ、実に心も晴れ晴れとして、常世の模様は面白さ言葉に尽くしがたく、三人それぞれ談じ合い、笑い合うこと限りなし[5]。
春の陽気に呼応し、仲間たちと訳もなく笑い興じ、詩歌を吟唱する。鹿児島の広大な自然に抱かれ、大久保にも、このように闊達で愉快な青春の日々があったのである。続けて、彼らは歌作を競い合うのだが、大久保の作った歌と漢詩を披露しておこう[6]。
かきりなく春のけしきをとゝむるは
このあをうみの水の上なり
早春携杖出 暖日気氛氳
碧海曠無限 青山断水雲
このように仲間たちと和気藹々と交遊しながら瑞々しい覇気を育む一方で、この時期の日記からは日々孜々(しし)として勉学にいそしむ姿も浮かび上がってくる。その学びは、和漢両学に及んだ。「国学の会読あり。論語の素読もあり[7]」とあるように、論語のみならず国学の素読会読に励んでいる姿が書き留められている。和歌を詠み、詩を作ろうとするところにも、幅広い教養を求める様がうかがえる。
また、漢学といっても、単に四書五経の訓読に終始していたのではない。この年の正月二〇日の記載には、『理気鄙言(りきひげん)』の抄本やその他の書物を受領したとある。『理気鄙言』とは仙台藩の儒学者・桜田虎門が著した宋学の理気説の概説書である。その写本を友人から借り受け、いささか興奮の態がうかがえる。江戸期は遊学や写本といった手段で、文人たちのネットワークが築かれ、多様な知識の回流が行われていた。そのネットワークのもとで、日本の津々浦々にまで洋の東西を問わない多彩な学問がなされていた。大久保も自分の興味にあわせて様々な学問を学ぶ姿勢を見せているのである。
(続きは書籍でお楽しみください)
***
*税所篤(一八二七―一九一〇)薩摩藩士。誠忠組の一人として奄美遠島の西郷復帰に尽力。新政府では大阪府権判事、堺県令等を歴任。元老院議官を経て宮中顧問官。
*伊地知正治(一八二八―一八八六)薩摩藩士、誠忠組の一人。藩校造士館教授、軍役奉行などを経て、戊辰戦争では江戸、会津の攻略で指揮を執る。左院副議長、宮内省御用掛等を経て、宮中顧問官。西南戦争後は帰郷して薩摩復興に尽力。
[1]「幕府も別而憤発ニ而、長州征伐之再挙有之、大はつミ之由ニ被聞申候。是れ別而面白キ芝居ニ成り可申と楽ミ申候。大抵我思ふ図ニ参申候間、彼ハ彼れ我ハ我にて大決断策を用ひ不申候而ハ相済不申候間、必御気張可被成候」。慶応元年五月一二日付伊地知壮之丞宛大久保利通書簡、『大久保文書』I、三七六頁。
[2]『西郷隆盛全集』II、四〇頁。
[3]「いか様の事にても尽力可仕」。高橋『幕末維新の政治と天皇』、二八四頁。
[4]「議者或ハ曰ン。国是ノ勅問ハ甚タ不可ナリ。人心ノ異ナルハ其面ノ如ク、其議モ亦一ナラス。是ヲ以テ甲ノ議ハ之ヲ採リ、乙ノ議ハ採ラス。其採ラルヽモノハ満足ス可シト雖、否ラサル者ハ必ス不平ヲ抱カント。之ヲ如何セハ可ナラン。故ニ曰ク。朝廷先ツ幕府ト施政ノ大綱ヲ起案シ、聖意ヲ以テ確定シ、大樹之ヲ賛成ス。而ル後ニ諸藩主ニ下シテ答議ヲ上奏セシメント欲スルナリ」。『岩倉文書』I、一五八―一五九頁。
[5]「是レ然ラス。国是ヲ議定スルハ国家ノ安危ニ係リ、事最モ重大ナリ。天子一人ニテ決シテ之ヲ定ムヘカラス。何トナレハ、天下ハ祖宗ノ天下ナリ。君臣相共ニ是非得失ヲ審議シテ、以テ宸断ヲ下スヘキナリ」。同前。
[6]「弟〔木戸〕長之人にあらす。日本之人にあらす。天に登りて今日皇国を見るとき、実に天も未皇国を御見捨は無之事に而、〔中略〕天下に名医有之候て於于此天下安静永久之基本も相立、皇国富国強兵之策も今日より被相施、天下共に安楽之場合にも可立至と奉存候得共、天にも名医之御人選までは無之事に付、拙医之為皇国之病を治し候事出来不申」。『木戸文書』II、八九頁以下。
[7] 「長州も大と小との異なるのみにし而、今日之場合に至り候も元より偶然には無之。皇国之今日に至り候も同一徹と存申候。長州今日之場合に立至り〔候〕を名医よりしてうかがわせ候はゝ、千歳一時之機会にも可有之歟。左候て今日之長州も皇国之病を治し候にはよき道具と存申候」。同前。
株式会社新潮社のご案内
1896年(明治29年)創立。『斜陽』(太宰治)や『金閣寺』(三島由紀夫)、『さくらえび』(さくらももこ)、『1Q84』(村上春樹)、近年では『大家さんと僕』(矢部太郎)などのベストセラー作品を刊行している総合出版社。「新潮文庫の100冊」でお馴染みの新潮文庫や新潮新書、新潮クレスト・ブックス、とんぼの本などを刊行しているほか、「新潮」「芸術新潮」「週刊新潮」「ENGINE」「nicola」「月刊コミックバンチ」などの雑誌も手掛けている。
▼新潮社の平成ベストセラー100
https://www.shinchosha.co.jp/heisei100/
関連ニュース
-
2017年を書評で振り返る シャンシャン、藤井四段、北朝鮮ミサイル、元SMAP、カズオ・イシグロまで[後編]
[ニュース](日本の小説・詩集/政治/海外の小説・詩集/外交・国際関係/将棋・囲碁/世界史/図鑑・事典・年鑑/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド/社会学/妊娠・出産・子育て)
2017/12/28 -
「その時その場にいない人を悪者にしながらのりきっていこうじゃないか」ヨシタケシンスケの提案に寺島しのぶも共感
[ニュース](自己啓発/哲学・思想/タレント本/社会学/演劇・舞台)
2019/04/27 -
トイレと天気はOLの味方! 大久保佳代子が「分かる、分かるよ!」と共感する働く女性の日常とは
[ニュース](コミック)
2018/08/02 -
生きてるうちに、言えなかったこと――65年連れ添った妻を亡くした老学者の溜息と恋ごころ 『九十歳のラブレター』試し読み
[試し読み](エッセー・随筆)
2021/09/17 -
第18回小林秀雄賞と新潮ドキュメント賞が決定 平山周吉『江藤淳は甦える』、河合香織『選べなかった命』が受賞
[文学賞・賞](自伝・伝記/思想・社会/評論・文学研究/妊娠・出産・子育て)
2019/08/24