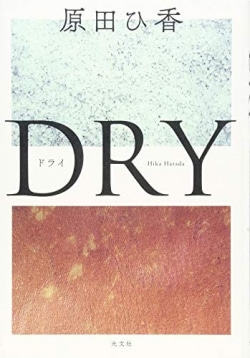「堕ちていく女の果ての果て」 『DRY(ドライ)』刊行記念インタビュー 原田ひ香
インタビュー
『DRY』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
「堕ちていく女の果ての果て」
[文] 吉田伸子(書評家)

原田ひ香さん
『ランチ酒』『三千円の使いかた』と今話題の作家・原田ひ香さんの最新作は、黒ハラダ全開、初のクライムノベル。
介護、年金、生活保護など、現代社会における問題を抱え行き詰まる女たちが、
負のスパイラルに陥っていくダークな世界を描いた作品について、熱く語っていただきました。
インタビュー・文
吉田伸子
***
――原田さんは『はじまらないティータイム』で2008年にデビューされたので、今年はデビュー10周年になります。
原田 去年あたりに、もうそろそろデビュー10年近くなるな、と思っていました。おかげさまで、なんとか10年保(も)ったな、と思っています。
――デビューは「すばる文学賞」という純文学の賞でしたが、『はじまらないティータイム』から3年後に出た『東京ロンダリング』は、いわゆる純文学ではないエンターテインメント系の作品でした。
原田『東京ロンダリング』を出すまでの3年間は、自分のなかでの迷いもあった時期でした。その間に、単行本にはなっていないのですが、「失踪クラブ」という物語を「すばる」に書きまして、ちょっとエンターテインメントっぽい作品だったんですね。それを読んだ集英社の編集の方が、そっち(エンターテインメント)でもいけるんじゃないか、とおっしゃってくださったことが、『東京ロンダリング』に繋がりました。
――その後は『人生オークション』、『母親ウエスタン』と続きます。そして、今年、節目の10年目に刊行されたのが『三千円の使いかた』と本書『DRY』です。本書は、原田さんファンの読者の方も「!」と思うようなインパクトのある作品になっているのですが、本書を書かれたきっかけはなんだったのでしょうか。
原田 担当編集者さんとは、ずっと次回作のことを話し合っていました。私からもいくつかストーリーの提案を出したりもして。そんな中、57歳の娘が、70代の実の母親を刺した事件をネットで知ったんです。深夜に酔っ払って帰って来たことを母親から咎められた娘が、カッとなって刺してしまった、と。でもまぁ、自分がその57歳の娘だとして、そんな歳になってまで母親にぐちゃぐちゃ言われたくない、という彼女の気持ちはわからなくもない、というようなことを担当さんに話しました。振り返ってみれば、それが最初のインパクトで、そのことを物語にしてみよう、というのがそもそもの始まりでした。そこから徐々に設定を詰めていくうちに、57歳の娘にも娘がいる、とか、実家は袋小路に立っている、とか細部が出来てきました。そして、実家の隣の家には、ずっと一人で家族の介護をしている「美代子」という女性がいて、そこに何か謎がある、ということにしよう、と。
――まさに「隣の美代ちゃん」!
原田 その美代ちゃんという設定が、私自身、以前からずっと気になっていた「ヤングケアラー」――孫が祖父母を、とか、子が祖父母の年齢のような親を、というように若者たちが家族の介護を担っている状況――の存在と重なったことも大きいですね。例えば20代で、社会人としての訓練を受けない状態で介護を担う生活に入ってしまうと、40代になって介護を終えた時に、その人のその後の人生はどうなっていくんだろう、と。そこが気になっていたことも、本書のきっかけでしょうか。最初は、美代子の“秘密”が明らかになるところで物語が終わるようにしようと思っていたのですが、途中から、もっと手前で“秘密”を明らかにしていくことで、深く描いていこう、と。
――本書のゲラをいただく時に、編集者さんが、「今回は黒ハラダです」とおっしゃっていました。
原田 わかっていただけましたか(笑)? しかも、かなり、黒です。とはいえ、自分では白ハラダ、黒ハラダを意識して書いているわけではないんです。私の場合、まず自分が描きたいものの企画をいくつか出します。最初から、こういう感じで、とリクエストいただく場合もありますが、その場合は、リクエストに応じた企画を何本か出します。連作短編などは、どちらかといえば明るい感じになりますね。担当編集者さんとは、『母親ウエスタン』からのお付き合いなので、私が書いたものをすごく厳しく読んでくださるのがありがたいです。彼女が担当なのだから、もっと、もっと(深く書かないと)、と自分にプレッシャーをかけていました。
『DRY』の真ん中にいるのは、夫と離婚し、かつかつの生活を送る藍(あい)だ。藍の母親が自分の母親(藍の祖母)を刺したことで、留置されているところから物語は始まる。祖母は入院中で、母親は留置場におり、否応無しに藍は祖母と母親のパイプ役を担わされることに。そんなこんなで、長いこと訪れていなかった実家を訪れたその日、藍は隣家に住む美代子と再会する。それが全ての始まりだった。やがて、藍は美代子の“秘密”を知るのだが、その時点で、藍は美代子とともに、その“秘密”を守らざるを得なくなっていた――。
――美代子の“秘密”に付随する描写もそうなのですが、原田さんの物語は細部がしっかりしています。例えば、物語の最初の方での藍の生活描写――節約のために茹で蕎麦は一度に半玉だけ食べる、とか、細かな家計のやりくり――がものすごくリアルです。
原田 作中の人物がどれくらいのお金で暮らしているのか、どんな仕事に就いてどれだけお給料をもらっているのか、そういった細部にまで入らないと、人物像を練り上げられない、というところが私にはあるんです。あと、基本的に細部を描くのが好きだ、ということもあります。
――その細部のリアルさが読み手を物語にぐっと引き込みます。
原田『ランチ酒』を書いて、その次に『三千円の使いかた』を書いたのですが、どちらも物語のトーンは明るい感じで、『三千円の使いかた』は、節約小説としての側面も評価していただけました。この先行する二作があったからこそ、本書がある、というのが私の実感です。とりわけ、『三千円の使いかた』は、家族とお金の話なんですが、本書もまた家族とお金の話でもあります。前者は明るく節約していく前向きな家族の話なんですが、それをひっくり返したら、年金とか生活保護とかの問題を抱える家族の話になると思うんです。
――本書を読んで思ったのは、原田さんが年金や生活保護のことを、他人事(ひとごと)だと距離を置くのではなく、自分のことに引きつけて考えている方なのだな、と。
原田 確かに本書は今までの著作とは毛色が違った作品ではあるんですが、逆に、今までの作品の延長線上にある、とも言えるんです。自分のことに引きつけて考える、とおっしゃってくださったんですが、私自身、自分が今、作家でもなく、結婚もしていなかったら、要するに、自分「だけ」になった時に、どんな仕事ができて、どれだけお金をもらえるのか、とよく考えるんです。小説を書く上で考えるのではなくて、自分の人生のこととして。本書の美代子のように、現在41~42歳の人というのは、就職が一番厳しかった時で、本来なら大きな企業に就職してもおかしくなかったような人たちが、今も(就職できずに)取り残されている。私は自分の小説で何かを訴えたいとか、そういう想いは特にはないのですが、その世代の人のことは、いつも考えていたい、と思っています。
――本書の234ページに「間違った選択は将棋倒しだ」という言葉が出てくるんですが、この言葉が強く響いてきます。藍や美代子に限ったことではなく、私たちの人生だって、一つの間違いが将棋倒しになって連鎖していくかもしれません。そういう連鎖が続いていく怖さも、その連鎖から抜け出せなくなる怖さもある。この言葉があるから、読み進めていくごとに、本書が徐々に切ない女たちの物語として迫ってきますし、現代社会が抱える女性たちの問題までもが浮かび上がってきます。藍も美代子も、そもそも選ぶことさえできなかった二人なんですよね。
原田 今の日本、という言い方は安易なんですが、そういう状況――選べない時代――なんですよね。そもそも美代子が“秘密”を抱えることになったのは、最初の“ずれ”のようなことが始まりだったわけで、物語のなかで彼女が「私はそれしか知らないのだからしょうがない」というのは、開き直りでもなんでもなくて、事実を言っているだけ。“秘密”を積み重ねていくことで、ますます雁字搦(がんじがら)めになっていくのだけど、じゃあ、最初にその“ずれ”がどうして起こったのか、という。
――何故その“ずれ”を修正しなかったのか? と思うのは、選択肢がある側にいるから思えることなんですよね。
原田 美代子が選んだのは、(選択肢がないなかで)ちょっとだけ安易な方向、であって、でもそこを選んでみたら、だぁ~っと下るだけになってしまった。その美代子と共に行動することが、藍はだんだん心地よくなっていく。いわば、共依存のような状態ではあるのですが、その二人で堕ちていく感じというのも、描きたかったところなんです。女性が変わっていくところを描きたかった。あと、私はシナリオからスタートしていて、深い心理が書けていないと、ずっと注意されてきていたんですが、本書でそこから少し抜け出せたかな、という手応えはあります。
――本書は、“間違った選択”をしてしまった人、間違ったことで負のスパイラルに陥っている人に届いて欲しい一冊でもあります。本書を読むだけでは抜け出せないかもしれませんが、少なくとも、自分が間違った選択をしている、そのことには気づけるんじゃないかと。
原田 そうなっていただけると嬉しいです。私は、テレビの特集番組とかで、凄惨な事件や酷い事件を知ると、本当にショックで、どうしたら事件が起こらずに済んだのか、と考えて、自分で解決方法を見つけないと寝付けなくなってしまうほどなんです。この時点で思い切って警察に相談していれば、とか、ここまでだったら、まだ引き返せた、とか。あと、私は生活保護をプラスに考えているんです。苦しい時には生活保護に頼って、そこからもう一度立ち直ればいい、と。そんなふうに、生活保護の受給に関して、多くの人がもう少しライトな意識を持てればいいのに、と思っています。