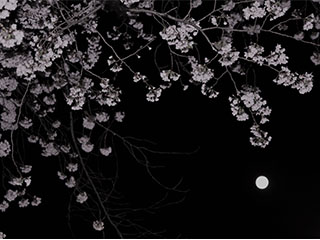『財政と金融の法的構造』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『財政と金融の法的構造』
[レビュアー] 渕圭吾(神戸大学大学院法学研究科教授)
はじめに
Kちゃん、あなたがうちの大学院に入ることになって、嬉しく思っています。もともと横浜育ちのあなたが神戸の大学を選んでくれた理由は、甲子園球場や宝塚大劇場が近いということだったのかもしれないけれど、この美しい山と海のある街が気に入ってそのままここに留まってくれるというのは本当によかった。近い将来に海外の大学院で勉強することになるとしても、それまでは、この落ち着いた環境で、租税法を含めた法学さらには社会科学全般の基礎的技法を身につけるべく、しっかり勉強して下さい。
さて、同封したのは、去年の3月に出版された、僕の学生時代の指導教授にあたる中里実先生の『財政と金融の法的構造』という本です。これから法学を本格的に勉強するKちゃんにとってきっと読んでためになる書物だし、僕もとても面白く読んだけれど、結構読み方が難しい本だと思う。下手をすると、やたらと外国語の古い文献を引用した衒学的な本に過ぎないということになりかねないし、別の見方では繰り返しの多い、思いつきを羅列した本ではないかと言われるかもしれない。それに加えて、僕が一番恐れているのは、あなたが、こんなに大量の外国語の文献を読まないと研究者として失格なのか、と怖気づいたり、あるいは、この本の中から学問分野間の競争意識みたいなものを感じ取って嫌気がさしたりすることだ。そこで、この手紙で、先生がこの本を通じて伝えたかったメッセージのうち僕にとってどれが大事だと思えたか、また、この本を完成させるまでに先生と僕にそれぞれどのような悩みがあったのか、ということを書いてみたい。
この本の内容
この本は、先生が1997年から2017年にかけて公表した13本の論文を集めて、それに「まえがき」、「あとがき」、「財政法の2つの側面」(第1章第1節)を加えて、出版された。中里先生は、1995年に一橋大学から東京大学に併任の形で移られて、1997年4月から東大の専任となったから、ちょうど東大在職中に書かれた論文を集めたと言えなくもない。しかし、先生自ら「まえがき」で赤裸々に書いておられるように、先生はこの20年で、その研究方法論につき、相当に悩まれ、その上で暫定的な見通しを立てられた。
本書の主張を僕なりに要約すると、次のようになる。国家と金銭(あるいは金銭債権)との関係が問題となる場面を法的に分析していこうではないか。その際、国家あるいはそれを構成する様々なアクターを特別視することなく、できるだけ、市場を構成する私人や企業と同様に取り扱おう。言い換えると、一方では、私法、とりわけ民法の論理がどこまで通用するかを見極めるべきだし、他方では、諸アクターが合理的に行動する主体であると仮定する経済学の考え方をかなりの程度適用することができるのではないか。
このような基本的なアイデアから、まず、国家が財産権の主体であることに着目して分析すべきである、との命題が出てくる。これまで、国家のこの側面についての分析が不足していた、というのが中里先生の見解である。本書においては、国家が「国庫」として私人に対して損害賠償責任を負ったり、もともと私人に帰属していた財産が国庫に帰属したりする例が、繰り返し登場する。次に、議会が国家に帰属する財産(基本的には、金銭ないし金銭債権)の出入りをコントロールするメカニズムが分析の対象となるべきである、との主張が出てくる。これはもともと「財政法」として理解されてきた領域なのだが、中里先生はこれを「国家活動の金融的側面」ととらえて、中央銀行に関わる問題など金銭に関するあらゆる問題を視野に入れるべきだというのだ。
以上のように要約できる本書の主張は、大変魅力的である。僕自身はそれを「財政法」と呼ぶか否かにはあまりこだわりはないが、様々な社会科学の道具を使って社会をめぐる制度の設計の最前線に立つ法学者が本格的な研究の対象とすべき問題領域がこんなに豊かに残っているというのは、確かである。藤谷武史や片桐直人をはじめとする僕と同世代の優秀な研究者がこの分野に果敢に切り込んでいるところであり、僕も彼らに続きたいと思っている。
中里先生と僕の悩み
もちろん、この書物にも、限界はある。まず、実質的なことを言うと、鍵となるべき概念が「金銭」なのかそれとも「金銭債権」なのかという肝腎な点がはっきりしない。中央銀行に対する法的コントロールの話は「金銭」概念を介してつながってくるのに対して、私法の考え方を基礎とすべきという話は「金銭債権」概念を介して出てくるようにも思える。この2つの概念についてもう少し踏み込んだ検討があってもよかったのではないだろうか。
形式的な面について言うと、最初にも書いたように、また先生自身も認めておられるように、重複が多い。そして、この点は、先生が、そして僕を含むその近くにいた研究者が経験した、21世紀最初の10年間におけるアイデンティティ・クライシスとその克服を反映している。
僕が、本郷三丁目の交差点付近で1年上の先輩(Kちゃんもよく知っている、憲法・情報法学者のSさんだ)に租税法の授業を勧められたのをきっかけに先生の授業を受講したのは、1997年の春のことだった。先生の授業は、基本的にはすでに公表された先生の論文(例えば、阿部泰隆先生の本への書評や「法人課税の再検討に関する覚書」、「法人課税の時空間(クロノトポス)」)をベースとしたもので(教材部で売られていた小冊子がレジュメになっていて、それに適宜メモを取っていくような感じ)、それまで受講していた法学部の授業とはかなり趣を異にするものだった。授業の最初には柔軟な発想の重要性が強調されたし、授業の中では「このテーマは修士論文や博士論文の素材となりうる」というようなコメントもあった。要するに、それまで受けていた授業の多くは比較的権威的にこれはこうなっていますという知識を伝授するものであったのに対して(もちろん、今となってはそういう授業の重要性もよくわかる)、先生の授業は今までなんとなくみんなが信じてきたことを新しい道具や手法を使って考え直す作業を実際にやってみるワークショップだった。
こうした先生の授業に感銘を受けて大学院を受験したことは前に話したので繰り返さない。だけれども、僕が1998年4月に助手として先生の指導を受けて勉強を開始して間もなく、今にして思えば、当時40代半ばの先生も研究方法論の面で悩みに直面していた。その背景は、いろいろある。
まず、租税法内部のことについて言えば、1960年代末から80年代にかけてアメリカで隆盛を極めた、所得概念を基礎とした租税実体法の分析が、ほぼやり尽くされたということがある。1990年代には、そこから派生した金融商品に対する課税についての高水準の研究が一斉を風靡したが、これについても中里先生の『金融取引と課税(有斐閣、1998年)』を含めて一応の成果が日本でも得られた。他方で、節税商品の普及とそれに関する争訟に直面し、租税法総論と呼ばれる分野の議論の練り直しが求められた(僕の研究関心のメインもここにある)。
先生にとってもっとインパクトが大きかったのは、先生の親友であり戦友でもあるマーク・ラムザイヤー先生からの率直な問題提起だ。ラムザイヤー先生は、恐らく、次のようなことを中里先生に言ったに違いない。事実やデータに裏づけられていない言明は、単に思いつきや感想に過ぎないのではないか、それで学問と言えるのか、と。他方で、先生の同僚である東大法学部の基礎法学・実定法の研究者の一部は、論文執筆に際してより厳密な歴史学の方法論の適用を主張していた。この両方向からの問題提起は極めて本質的であり、僕自身が研究を始めてから最初の10年間にほとんど論文を出すことができなかった理由の大きな部分はここにある。詳しくは書かないけれど、先生にとっても、悩みは深かったと思う。それまで、金子宏先生の業績を踏まえそれを乗り越えようという意欲に満ちた魅力的な論文を量産されてきた先生が、以上のような諸要因から、この時期、今後の租税法研究(あるいは法学研究一般)のあり方について、迷いを持たれていた。
この本の読み方
しかし、中里先生が立派だったのは、そのような深い悩みの中でも、論文を書き続けるのをやめなかったことだ。東大法学部の『研究・教育年報』を見ればわかるけれど、先生はコンスタントに論文を書き続けられた。悩みや迷いがありながら、とにかく「書く」。そして、批判を仰いでさらに書く。本書においては、論文は緩やかな体系性に従って並び替えられているけれど、Kちゃんがこの本を読むときは、「初出一覧」と照らし合わせて、先生の思考の発展・変遷の過程を追うといい。先生自身は「クリスタライゼイション」と言っているけれども、僕も長年研究をしていて、別々に考えていた複数の問題がつながっていることに気がついて、はっとすることがある。まさに、研究の醍醐味だよ。この本を読むことを通じて、先生がたどった過程自体を追体験することは難しいかもしれないけれど、先生のような一流の研究者でもこのように悩んだり迷ったりした末にやっと一応の答えを見出している、ということはよくわかると思う。それは、これから研究を本格的に始めようとするKちゃんにとってのエールになるのじゃないかな。
だから、この本を読む際に、租税法の権威である東大教授が財政と金融の法的構造について何か結論めいたものを示しているに違いない、と期待すると、がっかりすることになる。この書物は、そのような結論を求めて読むべき本ではなく、むしろ、この本を読んだところから自分の頭で考えてその先に進むためのものだろう。あまり図式的な読み方はお薦めしないけれども、例えば、165頁(第4章第1節)にある「国家活動の概念図」などを参考に自分で考えてみると、面白いアイデアが浮かんでくるかもしれないね。
これから法学の研究を始める人に
僕にとってKちゃんは初めて指導する研究者コースの大学院生だから、あまり偉そうなことは言えないけれど、僕からあなたに一つだけアドバイスするとすれば、中里先生が僕に常々言ってくれて、それ以上に自ら実践して背中で語ってくれた、とにかく「書く」ということだ。僕はなかなかこれができなくて、ある時期までは本当に辛かった。それでも、継続的に書くことができるようになって、まずはとにかく手を動かす・書くということから何か新しいものが出てくるのだ、ということがわかってきた。あなたも読んでいた、東村アキコ『かくかくしかじか』(集英社、2012~15年)で描かれていたけど、これは本当に大事なことだし、頭でわかっていてもなかなか実践できないのだよね。
うちの大学には優れた学生劇団が2つあって、その一方のオリジナルの芝居で優しさたっぷりに描かれていた傑出した師匠とその不肖の弟子とそのまた弟子の話が頭から離れず、こんな手紙を書かせてもらった。それでは、I君とMちゃん、いやご両親に、くれぐれもよろしく。