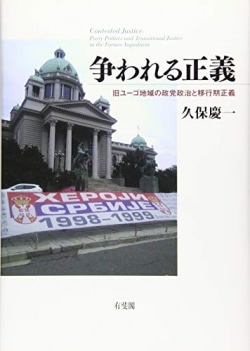『争われる正義』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
正義の追求は和解をもたらすのか――旧ユーゴ地域の「過去と向き合う」取り組みを探る
[レビュアー] 久保慶一(早稲田大学教授)
1 はじめに
拙著『争われる正義――旧ユーゴ地域の政党政治と移行期正義』(有斐閣、2019年)は、1990年代の凄惨な民族紛争が終結し、民主化が実現した2000年代以降の旧ユーゴスラビア(以下、旧ユーゴと略記する)地域において、紛争中の戦争犯罪行為に関する真相究明や責任者の訴追・裁判といった「移行期正義」の取り組みがどこまで進み、それが現地の人々に何をもたらしたのかを明らかにすることを試みた研究である。このエッセイでは、本書の執筆の背景や意図など、本書の本文やあとがきでは書ききれなかった点について、僭越ながら少しばかり語らせていただきたいと思う。
2 執筆の背景
まずは執筆の背景から振り返ってみたい。本書のあとがきでも紹介した「旧ユーゴの敗戦後論を書いてみませんか」という言葉を出版社に勤務する知人からかけていただいたのは、記憶が定かでないが、確か2012年頃のことである。その時まだ筆者は、本書の土台となる科研費の研究(基盤研究C、「旧ユーゴスラビア諸国における移行期正義と和解」)の申請を検討している段階であった。そのことを話した訳でもないのに、そのような言葉をかけていただいたことが、その後も印象に残っていた。筆者が開始しようとしていた研究の成果が、「今も戦争責任の問題が議論される日本において、一般読者にとっても重要な関心事たり得るかもしれない」という考えは、この時かけていただいた言葉から生まれたものであった。
有難いことに筆者の科研費申請は採択され、2015年度から研究に着手した。実際に日本語の書籍として刊行することを検討し始めたのは、2016年頃であった。一般書として刊行することも検討はしてみたが、本書のように地味なテーマの書籍を一般読者向けの本として刊行するのはあまりにも無謀であるという至極当たり前の結論に達して、専門書としての刊行に切り替えたことは、本書のあとがきでも書かせていただいた通りである。
当時の筆者の状況を振り返ると、専門的な単著の原稿を執筆しようという発想は無謀にも近いものがあったが、だからこそ書かなければならないという強い思いがあった。2年間の在外研究を終えて2016年春に帰国した筆者は、その年の秋から大学院の行政を担当することになった。筆者が海外に行っている間に大学院改革の話が議論されていたことを認識せずに、深く考えずに引き受けたのがいけなかった。仕事を始めてみると、すぐに大きな改革の議論に巻き込まれ、想像をはるかに超える仕事量に、こなすのが精一杯の日々であった。そうこうして1年ほど経って、ふと頭に浮かんだのは、学部時代からの指導教授である伊東孝之先生が、いつだったか筆者に語った言葉である。
「学内行政は後には残らない仕事だが、その中に身を置くと、毎日の仕事をこなすことで満足するようになりがちである。そうならないように、くれぐれも気をつけなさい。」
その時は、そんなこともあるものかなという程度の気持ちで受け取った言葉であった。しかし、これはまさに今の自分ではないか。このままでは研究者として失格ではないか。そうならないためには、書くしかない、という思いが生じたのである。
そうは言っても生来怠惰な自分である。書こうという気持ちだけで書けるとは思えない。その時にちょうど学内で櫻田會の出版助成の応募の案内があったので、それを自分への圧力として使うことにした。応募には完成原稿の提出が必要で、その締め切りは2018年4月末。行政職の任期満了と重なるタイミングでの完成原稿提出はさすがに無理かと一時は諦めかけたものの、春休みの突貫工事でなんとか書き上げ、提出することができた。学術出版を取り巻く情勢が厳しい昨今、出版助成の存在がなければ原稿があったとしても出版は難しかっただろうが、筆者の場合には、このような状況であったので、出版助成の制度がなければそもそも原稿を書き上げることもできなかったのではないかと思う。そのような訳で、櫻田會の政治学術図書出版助成の制度には、二重の意味で深く感謝している。
3 本書の内容と特色
本書は、第2章と第3章においてクロアチア紛争、ボスニア紛争、コソヴォ紛争という旧ユーゴ地域の3つの主要な紛争の実態とそれに対する移行期正義の進展状況を明らかにした後、 第4章以降はセルビアに絞って分析を進めている。3つの国において武装蜂起したセルビア系住民と、その背後にあったセルビア共和国は、全ての紛争において、戦争犯罪行為の責任をもっとも強く追及された紛争当事者であった。そのため、セルビアがどのように戦争犯罪容疑者の拘束や引き渡しを進め、国際社会によって進められた戦争犯罪の裁判がセルビア国内のマスメディアや世論にどのような影響を与え、セルビア政府の要人による謝罪が近隣の諸民族にどのように受け取られているかを考察することが重要だと考えたのである。
筆者は、旧ユーゴ地域の民主化と民族問題の関連について考察した最初の仕事(『引き裂かれた国家――旧ユーゴ地域の民主化と民族問題』有信堂高文社、2003年)の末尾で、以下のように記していた。
「ドイツとフランスがそうであったように、明日の繁栄は昨日の敵とともに将来を築くことによってしか達成できないと旧ユーゴ地域の人々が考えるようになる日が来ることを、祈ってやまない。では、いかにしてそうした民族間の和解は可能となるのか――今、この問いは、筆者にとっての新たな研究テーマの一つとなっている。」
本書は、この時からずっと筆者が抱いていた問題意識を出発点として書かれたものである。この意味で、本書は、2003年の書籍の続編という位置付けの仕事とも言える。もし本書と2003年の書籍をセットでお読みいただければ、大変ありがたく思う。
本書の特色は何か、一つ挙げよと問われれば、分析手法の多様性だと答えたい。本書のテーマについて筆者独自の分析を展開しているのは第5章から第8章までの四つの章であるが、そこでは、現地語資料を用いた定性的な比較分析(第5章・第6章)、セルビアにおける主要3紙の14年分の新聞記事(合計1万3000件以上)を体系的に収集して行った計量テキスト分析(第7章)、筆者が現地の研究者と共同で実施した世論調査のデータに基づく分析(第8章)と、筆者が現時点で用いることのできる分析道具を全て用いて、多面的に考察することを試みた。
定量と定性の手法を併用する比較政治学の研究は数多いが、定量では多国・多期間をサンプルとする分析、定性では特定の国や地域の事例研究という使い分けをしているものが多い。本書のように、特定の国や地域に焦点を維持しながら、多様な分析手法を適用する形で分析を行った研究は欧米でもまだそれほど多くないと思う。定量的な手法を、地域研究と対立するものと捉えるのではなく、特定の地域をより深く広く理解するために役に立つ道具と捉えて、定性的な手法と併用して研究テーマに接近することで、「地域研究」に一つの新たな形を提示することを模索したつもりである。
4 アジアとの比較の視座
本書を日本語の書籍として刊行した意図の一つは、日本を含めたアジアとの比較の視座を提供することであった。筆者自身は、日本人としての当事者性はもちろんあるが、東アジアの事例を研究対象とするわけではないので、自ら旧ユーゴ地域と東アジアとの比較の議論を学問的に展開することはできない。しかし、本書が示した旧ユーゴ地域の事例は、一つの比較の視座として、有益なのではないかと考える。
本書で明らかにしたように、旧ユーゴ地域で紛争中の戦争犯罪行為の真相究明のために現地の研究者やNGOが費やしてきた労力は並々ならぬものがある。その結果、ボスニアとコソヴォについては紛争の犠牲者に関する個票のデータベースがほぼ完成しており、死者数がかなり正確に把握されるに至っている。こうした成果は、旧ユーゴ地域において、紛争の死者数を過大や過小に見積もることによる責任追及や責任回避の不毛な論争をなくしていくことに貢献しているように思われる。この点について旧ユーゴ地域で行われてきたことは、我々にとっても見習うべき点が多々あるのではないだろうか。
第5章・第6章では、過去の戦争犯罪の責任に関する政府・公職者の発言や政策は、党派性によって、また同じ党派でも内向き(自国民、自らの支持者向け)か外向き(国際社会、近隣諸国向け)かによって、変わることを示した。加藤典洋が『敗戦後論』において問題視したのも、政府や公職者の態度や発言の一貫性の欠如(彼の言葉を用いれば、「分裂」と「ねじれ」)であった。本書の第5章・第6章の分析は、そうした問題が決して日本だけのものではないことを示している。むしろ、このような一貫性の欠如が生じるのは、言論と思想、結社の自由が存在する民主主義体制の宿命とも言えるかもしれない。本書の分析は、そうした状況において移行期正義と和解を追求していくことがいかに困難であるかを示すものだと筆者は考えている。
世論調査データを用いた第8章では、戦争犯罪に関する公的謝罪をめぐって自民族(内集団)と他民族(外集団)で評価のズレが生じることを指摘した。この点についてはより詳細な分析、研究が不可欠だが、公的謝罪を経て和解を達成することの難しさを示しているように筆者には思われる。
5 本書の限界と今後の研究
現時点で筆者にできる限りの分析を行って執筆した本書だが、限界が多々あることは言うまでもない。特に定量的な分析については、計量テキスト分析についても、世論調査データの分析についても、適切に因果推論を行うために、より詳細な分析を行うことが必要不可欠である。今後しばらくは、本書の土台となった研究をさらに発展させるために、定量的なデータのより詳細な分析を進め、海外の査読誌の論文として研究成果を発信することに専念していきたいと考えている。