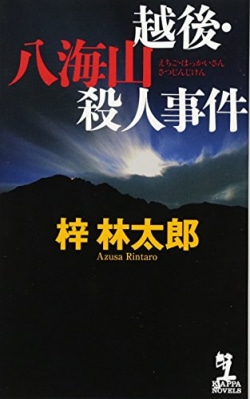『越後・八海山殺人事件』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
実話――『越後・八海山殺人事件』刊行エッセイ 梓林太郎
[レビュアー] 梓林太郎
小学五年生のとき、私は清水市(現・静岡市)にいた。父は魚釣針をつくる会社に勤めていたが、作業中の怪我で両手の親指の先端を失った。真っ白い包帯が痛いたしかった。障害者となった父をまわりの人たちは、「銃に弾込(たまこめ)できないので、兵隊に取られることはない」といっていた。父は怪我をする前から、「いま戦争を始めたら日本は滅びる」などという言葉を口にしていた。
両手から包帯がとれない父に赤紙(召集令状)が届いた。私は母とともに、両親の故郷である信州伊那谷(しんしゆういなだに)の村へ移住した。
兵隊の父は、満州、シンガポール、スマトラ、ジャワへと転戦し、敗戦により捕虜になった。そして終戦から一年あまりのちに、痩せゴボウのような手足をして故郷へ帰ってきた。ようやく働けるからだになったころ、父と同年ぐらいの知人男性が訪ねてきた。二人は懐かしそうに戦地での思い出を語り合っていた。その知人の口からは鹿児島の地名が何度も出ていた。それを私は憶えていたのだから、二人の会話をじっときいていたにちがいない。のちに私は、戦局が悪化したころの特攻隊の物語を読む機会があり、父の知人が話していた土地は、特攻隊の出撃基地だったのを知った。私が手にした物語では、出撃隊員に選ばれると、栄誉だといって、父母や兄弟に出撃が決まったことを手紙で報告していた。「国に奉公するために生まれてきて、国のために命をすてることのできる喜び」などと書き送って、死んでいったとも書かれていた。
それは、父の知人が語ったこととはまったくちがっていた。若い特攻隊員に出撃命令が下ると、泣きわめいたり、狂ったように転げまわったり、中には母親に助けを求める者もいた。出撃当日は、泣き叫ぶ若者をなだめて、攻撃機に搭乗させた、と知人は語っていたからだ。たまたま読んだ物語よりも、少年のある日にきいた父の知人の話のほうをよく憶えている。私がもし、志願して特攻隊員になったとしても、出撃命令を受けた瞬間、転げまわるか、血を吐くほどの声で泣きわめくと思う。
戦地へ送られた父だが、最前線にいたのではないらしく、敵と撃ち合ったという話をしたことはなかった。たびたび語ったのは、敗戦により捕虜となった南方の収容所での空腹の話だった。収容所では毎日、乾燥したトウモロコシの粒が捕虜たちに配られた。かつては銃を携えた軍人だった男たちは、手の平に配られた固い粒を、涙を流しながら口に入れた。父は日に一回支給される黄色の粒の数をノートに記録していた。それは二十か三十。
収容所は雑草が生えた原っぱだった。捕虜たちは草を分け、そこに棲むトカゲやカエルやバッタを血まなこになって追いまわした。戦争に勝った国の兵隊は、草の中の虫をさがしている捕虜の日本人を、嗤って眺めていたという。
父は私に、血と汗がにじんだ小さなノートを見せながら、「転校したころのおまえは、どうだった」ときいた。私には母にも話していないことがあった。それは、草ぶかい伊那谷の学校へ移ったその日からしばらくの間、身震いを堪(こら)えていた出来事だ。
下校時に、鉄道の上に架かる水道鉄管を渡れと、いきなり何人かから強要されたのもそのひとつだったが、教室で開いた弁当の中に異物を入れられていたときは、哀しかった。
ごく最近だが、東京駅舎内の駅弁売り場を見る機会があった。包装紙の絵柄に記憶のある駅弁がいくつか目についた。が、ひとつの駅弁の中身を目にした瞬間、小学五年生のある日が蘇って、つい口に手をあてた。