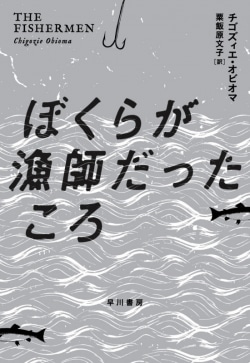『ぼくらが漁師だったころ』
- 著者
- チゴズィエ・オビオマ [著]/粟飯原 文子 [訳]
- 出版社
- 早川書房
- ジャンル
- 文学/外国文学小説
- ISBN
- 9784152097149
- 発売日
- 2017/09/21
- 価格
- 2,530円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
ナイジェリアの複雑な歴史と精神性を背景に描く悲劇
[レビュアー] 豊崎由美(書評家・ライター)
〈ぼくらは漁師だった〉〈オミ・アラは恐ろしい川だ〉〈父さんはワシだ〉〈イケンナはニシキヘビだ〉〈イケンナは変身しつつあった〉〈アブルは狂人だ〉〈母さんは鷹使いだ〉〈イナゴは前触れだ〉〈イケンナはスズメだ〉〈ボジャは菌だ〉〈蜘蛛は悲しみを背負う生き物だ〉〈オベンベは捜索犬だ〉〈憎しみは蛭だ〉〈だが、アブルはレヴィアタンだ〉〈希望はオタマジャクシだ〉〈兄さんとぼくは雄鶏だ〉〈ぼく、ベンジャミンは蛾だ〉〈デイヴィッドとンケムはシラサギだ〉
そんな印象的な一文から始まる18章から成る長篇小説が、ナイジェリア生まれの作家チゴズィエ・オビオマの『ぼくらが漁師だったころ』だ。語り手は6人兄弟妹の4番目に生まれた〈ぼく〉。29歳になった〈ぼく〉が回想するというスタイルで物語られるのは、20年前、1996年に端を発する悲劇なのである。
もうすぐ15歳になるイケンナ、その1歳下のボジャ、11歳のオベンベ、9歳の〈ぼく〉、3歳のデイヴィッド、1歳の妹ンケム。イケンナは愛する母さんと、銀行勤めで子供たちにはちゃんとした教育を受けさせたいと願う厳格な父さんの言いつけを守って、模範となるリーダーとして弟たちの面倒を見てきた。
愛と信頼と尊敬を礎にした理想的な子だくさん家族。それがアグウ家だったのだ。ところが、要である父親が転勤で遠くの僻地へ単身赴任して以降、少しずつ様子がおかしくなっていく。たががはずれた上の4兄弟は、行ってはいけない不吉な川で魚釣りに興じるようになり、そこで起きたある出来事をきっかけに、イケンナは自分の殻に閉じこもり、大好きな母さんにまで牙をむくようになってしまうのだ。ある出来事とは、町の有名な狂人による予言。イケンナはその言霊にからめとられ、ボジャをはじめとする弟たちの愛ある励ましもはねつけ、やがては――。
旧約聖書の有名なエピソードを変奏したかのような、アグウ家を見舞う悲劇の連鎖は、読んでいて、とても苦しい。予言を振りはらうことができないイケンナの肩を、「しっかりしろ」と揺さぶってやりたくなる。弟たちの気持ちを思うと泣きたくなる。でも、なぜ彼が正気に返れなかったのかは、アフリカ文学の碩学である訳者の「あとがき」を読めばわかるのだ。わたしたちが知らない複雑な歴史と精神性を持つナイジェリア。それがアグウ家の物語と交差していることを、「訳者あとがき」は示唆してくれる。小説本体に挑む前に一読をおすすめしたい。