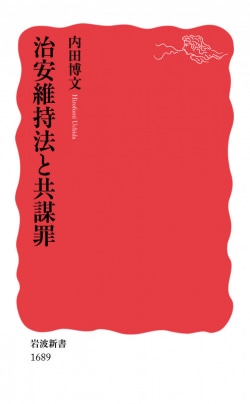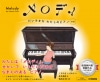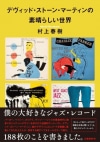『治安維持法と共謀罪』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
敗戦後も継続し、強化された「検察官司法」
[レビュアー] 図書新聞
去る3月12日、福岡高裁宮崎支部は、1979年に鹿児島で起きた大崎事件について三度目の再審開始決定を出した。本書で論じられている、共犯者の供述が冤罪の原因となる場合が多いという構造的問題のまさにモデルケースだ。共謀罪の場合、著者はこの共犯者の自白が有罪の中心となりうると警鐘を鳴らす。それは平成の治安維持法たる共謀罪の重大な危険性である。杜撰な事実認定はそれをもとに進められ、冤罪が横行しかねない。著者はこうした現在進行形の刑事法の変容を、市民刑法から治安刑法への転換の象徴としての治安維持法から捉え直す。事実認定を「公知の事実」とすりかえて空洞化し、量刑についても問答無用で処罰範囲をますます拡大していった歴史は重い負の教訓だ。しかも検察官主導の量刑が敗戦後も継続し、新憲法下でむしろ「検察官司法」を強化していった点を私たちは見逃すわけにはいかない。(12・20刊、二五六頁・本体八四〇円・岩波新書)