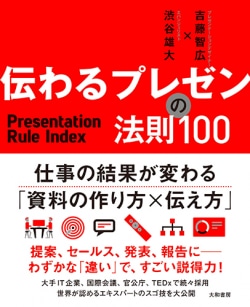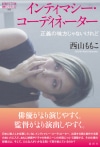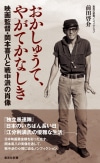「伝えたいこと」だけプレゼンするのは危険。聞き手に伝わる話し方
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
プレゼンしてみたものの、手応えが感じられなかったというような経験は誰にでもあるもの。
『伝わるプレゼンの法則100』(吉藤智広、渋谷雄大 著、大和書房)の著者は、「伝わっていない」ことがその原因だと指摘しています。
すばらしいアイデアや貴重な情報も、あるいは新たな発表も、「伝える」ことができなければ価値を持たないということ。
「伝える」は、単なる情報伝達ではなく、聞き手の行動や考え方に何らかの変化を与えること。
そしてこれを実現するための舞台装置とも言えるのが「プレゼンテーション」です。(「まえがき」より)
規模の大小に関わらず、「伝える」につながるすべてのことがプレゼンテーション。
だからこそ、現代社会でもっとも実践的なスキルである「伝える工夫」を知っておくことに、大きな意味があるというのです。
そこで本書においては、「つくるプロ」としてのプレゼンテーションデザイナー、そして「話すプロ」であるエバンジェリストが、普段の仕事で実際に使っている「伝える」テクニックを紹介しているのです。
Part 1「ストーリーを作る」のなかから、いくつかの基本的なポイントを抜き出してみましょう。
プレゼンは聞き手への贈り物
プレゼンを「嫌なもの」だと感じたり、苦手意識を持ってしまう人は少なくありません。
その原因は、目線がいつの間にか自分に向かってしまっていることなのだそうです。
しかしプレゼンには、必ず聞き手がいます。そして、せっかくプレゼンをするなら、聞き手が喜ぶようなプレゼンをしたいものでもあります。
だとすればそのためには、「どうしたら聞き手が喜ぶか」を考えることが必要になってくるでしょう。
著者によれば、それはプレゼント(贈り物)と同じ。つまり、聞き手が喜ぶ顔を想像し、自分もワクワクしながら贈り物を考えることが重要だということ。
まずはそんな気持ちからスタートすれば、プレゼンは苦痛なものではなくなるというのです。
[自分目線の気持ち]
「緊張する」
「誰か代わってくれないかな」
「怖いな」
「失敗したらどうしよう」
「なにを話したらいいんだろう」
「ああ、準備が進まない」
↓
[相手目線の気持ち]
「なにを話したら、相手に喜んでもらえるかな」
「これを話したら喜んでくれるかな」
「聞いてよかったと思ってもらえるかな」
「また聞きたいと思ってもらえるかな」
「どんな反応をしてもらえるかな」
「ドキドキするけど、楽しみだな」
このように「自分目線」を「相手目線」にすれば、いろいろなことが見えてくるというわけです。(16ページより)
目的は「ココロ」を動かすこと
プレゼンを考えるときは、情報を伝えることにばかり気をとられがち。しかしプレゼンのゴールは、「情報をわかりやすく伝え、理解してもらう」ことではないと著者は主張しています。
あくまでもプレゼンのゴールは、プレゼンを聞いた人に「行動を起こしてもらう」こと。
そのためには情報を理解してもらうだけでは不十分で、以下のような「理想のプレゼンを目指すうえで重要な3つのポイント」を押さえておくべき。
1.話を聞くとワクワクする
2.行動を超したくなる
3. 誰かに伝えたくなる
プレゼンを考えるにあたっては、この3つの要素が含まれているかどうかを必ず確認することが重要だということ。
聞き手が心まで動かされ、すぐに行動を起こしたくなること、それが理想のプレゼンだという考え方です。(18ページより)
情報紹介だけのプレゼンから抜け出す
「今回のプレゼンでは、会社の説明と新商品の紹介とおすすめ商品の提案をしたい」というように、自分が伝えたいことを詰め込んだプレゼンは危険。
なぜなら多くの場合、聞き手にとっては情報過多になってしまうからです。
ですから情報を詰め込めば詰め込むほど、「なにが言いたいのかわからない」プレゼンになってしまうことに。
重要なポイントは、プレゼンの主役は聞き手だということ。
そこで、常に聞き手を中心にして「伝えるべきこと」を考え、必要なトピックだけを厳選する必要があるわけです。
最初のとっかかりとしては、必要最低限の要素でシナリオを構成していくといいそうです。そのうえで、伝えきれない部分があれば補足情報を追加していくという流れ。
そのときにも、できる限りシンプルにしていくことが大切なのです。
例:会社の事業を紹介する場合
[「自分の伝えたいこと」がベースのシナリオ]
・ 自分の紹介がしたい:自己紹介
・ 創業時の苦労を話したい:会社創業のきっかけ
・ メンバーを知ってほしい:立ち上げメンバー紹介
・ 会社を知ってほしい:会社概要(売上・従業員数)
・ 過去の実績を知ってほしい:受賞歴
・ 事業内容を知ってほしい:事業内容詳細
・ 設備を知ってほしい:会社設備紹介
・ 他との違いを知ってほしい:他者比較
↓
[「相手が主役」のシナリオ]
・ どんな取り組みの会社だろう?:会社を代表する取り組み
・ どんなお客様がいるんだろう?:特徴的なお客様の例
・ どんなビジョンがあるんだろう?:会社が大事にしている考え方
・ どんな会社と協業したいんだろう?:協業を考える企業の方向性
このようにシンプルに、そして具体性を盛り込んでいけば、より伝わりやすくなるということ。(20ページより)
どのページからでも読むことができる見開き完結型なので、必要な部分を効果的に活用することが可能。
プレゼンテーションのクオリティを高めたいという方に、大きく役立ちそうです。
Photo: 印南敦史
Source: 大和書房