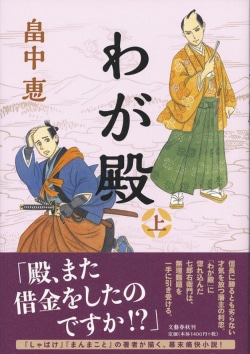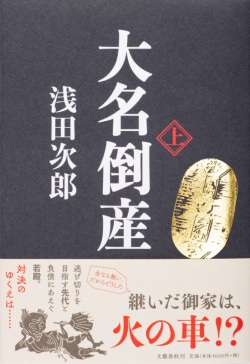【ニューエンタメ書評】宮本紀子『妹の縁談 小間もの丸藤看板姉妹(二)』、柴田よしき『お勝手のあん』ほか
レビュー
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
エンタメ書評
[レビュアー] 末國善己(文芸評論家)
新年おめでとうございます。どんなお正月をお過ごしですか? 貴重なお休み中にぜひ読書をどうぞ。今年もジャンル問わず、さまざまな名作をご紹介します。
***
二〇二〇年が始まったが、まだ冬休み中の方も多いと思うので、まずはじっくり読みたい大作から始めたい。
畠中恵『わが殿』(上下巻・文藝春秋)は、大野藩七代藩主・土井利忠と側近の内山七郎右衛門を主人公にしている。
八歳で家督を継いだ利忠は、天保の飢饉が終息した二十七歳の時、莫大な借金を抱える藩の財政再建に着手する。この大役を任されたのが、四歳下の利忠の器量と才覚に惚れ込んだ七郎右衛門だった。七郎右衛門は、ハイリスク、ハイリターンの銅山の新鉱脈開発に着手するなど新たな財源確保に奔走するが、利忠は藩の発展のため、藩校の開設、天然痘予防の実施といった金のかかる新事業を次々と打ち出していく。
本書は、著者が初めて実在の人物を取り上げた歴史小説だが、魅力的な登場人物やユーモラスな展開といった持ち味が活かされているので、〈しゃばけ〉〈まんまこと〉シリーズのファンは、戸惑うことなく物語に入っていけるはずだ。
利忠と七郎右衛門は、無駄な支出は反対派が多くても削減する一方で、未来の希望を作る事業であれば苦労をしてでも財源を作って、財政再建と領民の幸福を両立させようとする。七郎右衛門たちの奮闘を読むと、同じく赤字財政の現代日本に足りないのが、“選択と集中”だということがよく分かる。
浅田次郎『大名倒産』(上下巻・文藝春秋)は架空の小藩の財政再建を描いており、『わが殿』と同じ時期に、同じ版元から、同じ題材の作品が刊行されたのは、偶然だろうが興味深い。
丹生山松平家十二代目が隠居し、妾腹の四男・小四郎が家督を継いだ。丹生山松平家は返済困難な借金を抱えており、御隠居は、今の財産を温存したまま倒産(借金の踏み倒し)を宣言、小四郎に詰め腹を切らせ、自分は悠々自適な老後を送る陰謀を進めていた。それとは知らず膨大な借金に驚いた小四郎は、かつて某家の勘定役だった比留間伝蔵らと協力し財政再建を始める。御隠居と小四郎の暗闘には、貧乏神(本物)や七福神(本物)もからみ、大騒動に発展していく。
著者は、江戸時代は長く平和が続いたが、それゆえに合理化の必要がなく、どうでもよい制度や習慣ばかりを積み上げ、為政者の武士は金は不浄という「奇妙な道義」を作って財政再建に背を向けたとする。この構図は戦後日本社会の戯画であり、他人を不幸にしてでも自分の財産は死守しようとした御隠居は拝金主義に走った日本人への痛烈な皮肉に思えた。
〈新宿鮫〉シリーズ八年ぶりの新作となる大沢在昌『暗約領域』(光文社)は、恋人の晶と別れ、よき理解者だった桃井を失った鮫島が、新たな環境で難事件に挑むことになる。
北新宿のヤミ民泊を監視していた鮫島が、その一室でアジア系の男の射殺死体を発見する。折しも新宿署には、桃井の後任として叩き上げの女性警視・阿坂が異動してきた。基本を守る、ルールを曲げないが信条の阿坂は、鮫島の単独行動を認めず、若手刑事の矢崎と組むよう命じる。ヤミ民泊の殺人が公安案件になった後も鮫島は事件を追うが、その周辺では敵味方不明の幾つもの組織が怪しい動きをし始める。
殺人事件が、現実の東アジア情勢とリンクする壮大な陰謀に繋がるスピーディーでスリリングな展開は圧巻で、シリーズの新刊を待ちわびたファンの渇きを潤してくれるだろう。
鮫島は、警察の保守性やセクショナリズムを打破し、真っ当な警官が報われるようにするため一人で戦ってきた。本書では、鮫島と同じ理想をルールを遵守することで実現しようと考える阿坂を登場させることで、シリーズ第一作からテーマになってきた組織と個人の関係はどのようにあるべきかを再構築しており、原点回帰した部分もうかがえた。
『沸点桜 ボイルドフラワー』で第二十一回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞した北原真理の受賞後第一作『紅子』(光文社)は、馬賊小説の伝統を受け継いだ作品だ。
一九四四年の満州。小さな村の医師・吉永紅子は、関東軍の偵察機を盗み、多額の報酬で黄尚炎を首領とする馬賊に話をつけると、攫われた子供たちの救出へ向かう。同じ頃、偵察機を盗まれた黒磯少佐は、紅子の追跡を始めていた。
ここから紅子と黒磯少佐の追走劇になると思いきや、満州国の重鎮・甘粕正彦に、敗戦後に必要な金の輸送を頼まれた黒磯少佐が、紆余曲折を経て紅子たちと行動を共にする意外な展開になる。檀一雄の馬賊小説の古典『夕日と拳銃』が満州をアメリカ西部に重ねた西部劇ならば、野生動物や戦車とも戦う派手なアクションが連続する本書はマカロニウエスタンといえる。大金持ちで海軍士官を父に持つ紅子が、財力と権力を使ってトラブルを解決する場面が散見され、これが緊迫感を削いでいるのは否めない。ただ活劇と謀略に、金の争奪戦、紅子と周辺にいる男たちとのロマンスの行方、周到な伏線を回収した先に待ち受けるどんでん返しなどが加わる息つく暇もない物語が、マイナスを十分に補っていた。
第二次大戦末期、ハンガリーの首都ブダペシュトから、没収したユダヤ人の財産と避難民を乗せた通称・黄金列車が出発し、オーストリアに入った。佐藤亜紀『黄金列車』(KADOKAWA)は、この史実を基にしている。
ハンガリー王国大蔵省からユダヤ資産管理委員会に派遣されたバログは、没収した財産を管理するため黄金列車に乗り込んだ。官僚的な前例主義、書類重視の姿勢を貫くバログが、列車を予定通りに走らせるため鉄道員に物資を渡したり、財産を狙うドイツ、オーストリアの官僚や軍人と渡り合う展開は、シリアスながらユーモアを感じるかもしれない。
物語が進むにつれ、ハンガリーはユダヤ人が多かったが、一九三〇年代後半に極右の矢十字党が台頭、ナチスドイツの支援で政権を取るとユダヤ人を弾圧した歴史が浮かび上がってくる。バログは、ユダヤ系の友人ヴァイスラーと家族ぐるみで付き合っていたが、弾圧が強まると、ヴァイスラーは財産の移転と子供たちの国外脱出を考えるようになる。
著者は、バログの現在と過去をシームレスにして物語を進めているが、これは見えにくい時代の変化に注意していないと、当時のハンガリーと同じように、いつの間にかよき隣人を敵として攻撃するようになるかもしれないという警鐘のように思えた。現代の日本が大国アメリカの意向に沿って動き、東アジア情勢の緊迫が、特定の国への憎悪をかき立てていることを踏まえれば、なおさらである。バログが黄金列車に乗った動機が明かされるラストには、こうした時代とどのように向き合うべきかのヒントもあるだけに、感動も深い。
高野史緒の長編は『カラマーゾフの妹』から次作『翼竜館の宝石商人』まで六年かかったが、それから約一年で『大天使はミモザの香り』(講談社)が出たのは喜ばしい限りだ。
ヨーロッパの小国ラ・ルーシェ公国の大公が、ヴァイオリンの名器《ミモザ》を持って来日した。レセプションで《ミモザ》が披露されることになったが、厳重に警備され隠し場所がなく、大公しか解除法を知らない電子錠がかかったケースという二重の密室から《ミモザ》が消えた。この謎を、《ミモザ》と共演予定だったアマチュア・オーケストラの団員──天才的なセンスを持つ高校生の小林拓人と、四十二歳独身、ヴァイオリン歴三十年だが華がない音羽光子が追う。
ヴァイオリンの歴史、名器はどこが違うのか、過去と現代のヴァイオリン職人の差、さらに架空の小国を実際の歴史や国際情勢と矛盾なく作る(このあたりは、『架空の王国』を彷彿させる)など、ライトでユーモラスな物語の中に、これでもかというほどの情報量を詰め込み、それらすべてを謎解きの伏線として利用する緻密な構成には驚かされるだろう。
アマチュアの音楽家は、お金がもらえないどころか、多額の負担をして楽器を買い、練習している。ある意味で中途半端な立ち位置に悩む光子に、趣味で楽器を演奏したり、同人誌を出したりしている人は、共感を覚えるのではないか。
宮本紀子『妹の縁談』(ハルキ文庫)は、幼い頃は病弱で叔母の家で療養していた里久と、伊勢町小町と呼ばれる妹の桃が、小間ものの大店である実家「丸藤」を盛り立てていく〈小間もの丸藤看板姉妹〉シリーズの第二弾である。
今回、里久は、藪入りなのに里帰りしない長吉、お客の好みよりも「丸藤」の格と自分の審美眼を優先する手代頭の惣介、「丸藤」の娘らしく美しくあろうとしてきた桃の縁談が巻き起こす騒動に直面する。三つのエピソードは、いつの時代も変わらない、家族との関係、仕事への取り組み方、恋愛と結婚における個人と家(家族)のあり方を問い掛けており、登場人物たちの言葉と決断が胸に迫る。
最後に、新春らしく新シリーズを二作紹介したい。
柴田よしきの初の時代小説『お勝手のあん』(ハルキ文庫)は、口入れ屋が男の子と間違えて神奈川宿の宿屋に送った少女おやすが、老舗宿屋「紅屋」の主人・吉次郎に類い稀な嗅覚を見込まれ、品川宿で働き始めるなど、モンゴメリの名作『赤毛のアン』へのオマージュになっている。
料理ものの時代小説は、主人公がすぐに卓越した腕を見せる作品が多いが、おやすはまだ下働きで、料理人の政一、厳しくも優しい女中頭のおしげらと過ごしながら、料理の基礎と働く意義を学んでいる段階である。それだけに息の長いシリーズになりそうで、女性料理人への偏見が根強い幕末を生きるおやすが、どのように成長するかが楽しみでならない。
父の祖国フランスで育ったマリーが、外遊した乾隆帝の第十七皇子・永璘に連れられ母の祖国である清に渡り、永璘お抱え料理人の見習いになりパティシエールを目指す篠原悠希『親王殿下のパティシエール』(ハルキ文庫)は、国際色豊かな料理時代小説である。マリーが、フランスと清の食材、調理器具の違いを創意工夫で乗り越え美味しいお菓子を作る料理もの、メダリヨンの中から指輪が消えた謎を追うミステリ、慣れない環境の中で成長する青春小説の要素もあるので、どのジャンルが好きでも楽しめる。こちらも続編が待ち遠しい。