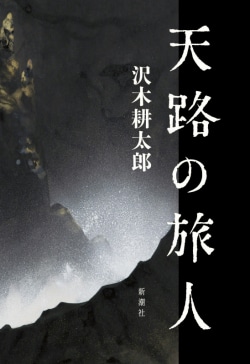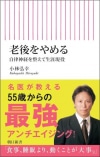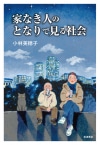『天路の旅人』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『天路(てんろ)の旅人』沢木耕太郎 著
[レビュアー] 平山周吉(雑文家)
◆無心無欲の人生たどる
長編『天路の旅人』の主人公・西川一三(かずみ)を、沢木耕太郎は「旅の達人」「人生の達人」と呼ぶ。ロングセラーの長編紀行『深夜特急』を書いた沢木が言うのだから、最大級の褒め言葉である。
西川は戦中戦後の旅を大部な記録『秘境西域八年の潜行』に書き、その後は東北の片隅で一商店主として生きた。元日以外は毎日九時から五時まで働き、帰りには居酒屋でお銚子二本の酒を愉(たの)しむ。判で押したような日々を生き、八十九年の人生を全うした。
沢木が西川に接触したのは四半世紀前、西川はすでに八十歳近かったが、颯爽(さっそう)とし、「背筋の通った壮年の風格」があった。沢木は毎週末に盛岡まで通い、西川行きつけの居酒屋で話を聞き続ける。そんな取材を一年余も重ね、西川をどう描くかが発見できず、そのままになってしまう。『天路の旅人』はその西川の旅を沢木自身の筆で辿(たど)り直す。西川という「希有(けう)な旅人」の人生を沢木が考えるという方法で、西川一三が蘇生する。
西川と沢木の年の差は約三十年で、親子ほど違う。共通点は二人の旅が二十六歳の時に始まったことだった(ただし、西川は数え、沢木は満年齢)。
西川の身分は大使館調査員という肩書の「密偵」であり、六千円という当時としては大金を渡されての「御国のため」の仕事だった。沢木の旅にはそうした義務はなかった。西川の出発二年後に、日本が敗れ、それからの西川の旅は沢木に近づく。
三十年の時差がある二人の旅の足跡は、インドでは重なることがあった。カルカッタで、釈迦(しゃか)の聖地ブッダガヤで。ブッダガヤの菩提(ぼだい)樹の下で太鼓を叩(たた)いていた盲目の老人について、沢木が話すと、西川が反応する。「いたなあ」。その盲目の老人は同一人物だったのか、どうか。
西川の旅は「無一物」「無心」「無欲」の旅だった。「無」は「自由」につながっていく。西川の人生は、沢木が初期の『人の砂漠』以来、関心を持続させている「無名」という人生をも体現していた。沢木の旅の総決算が本書だろう。
(新潮社・2620円)
1947年生まれ。ノンフィクション作家。著書『テロルの決算』『一瞬の夏』など。
◆もう1冊
藤原新也著『メメント・モリ』(朝日新聞出版)。もう一人の「旅の達人」の思索と視覚の記録。