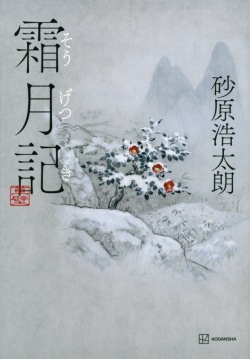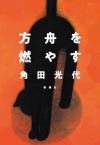『霜月記』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
小藩を舞台に綴られる永劫不変の複雑な父子の情
[レビュアー] 田口幹人(書店人)
日本海沿いにあると思しき架空の小藩を舞台とした神山藩シリーズの三作目である。
郡方を務める高瀬庄左衛門を主人公に、下級武士の哀歓を描いた『高瀬庄左衛門御留書』(講談社)、藩の筆頭家老を務める黛家の三男・新三郎が、二転三転するお家騒動に巻き込まれる様や、しみじみとした人間模様を描いた『黛家の兄弟』(同)は、いずれも流れるような落ち着いた文体で綴られており、激しく揺れ動く物語とは裏腹に、静かで、凛とした印象を与えてくれ、再読するたびにその印象をさらに深化させてくれる作品だった。
『霜月記』は、18歳にして町奉行となった草壁総次郎が、名判官と言われた祖父・左太夫や古参与力の小宮山喜兵衛、友垣の日野武四郎らと共に、父・藤右衛門の失踪の理由を追う過程で、その裏にある藩を揺るがす事件が立ち現れる物語である。
神山藩の成立以来、町奉行は草壁家の家職であったが、心構えもないまま突然の父の失踪によりその職に就かざるを得なくなった総次郎が、左太夫を頼る場面からはじまる。久方ぶりに会う孫に対し、「そなたが町奉行になるしかあるまいよ」と伝えることしかできなかった左太夫は、ある自責の念に駆られるのだった。それは、孫に対してのみならず、息子に対する想いからでもある。
著者の作品は、父子関係の複雑さが特徴的なテーマの一つとなっているのだが、子どもが父に対して持つ複雑な感情、さらに世間から優れているとされる父への敬意と嫌悪の念は、時代を超えて今の世でも同じであろう。父もまた、そんな感情を持つ息子との距離感を掴めず、物理的な距離以上に心に隔たりが生じることがある。作中、ほとんどの者は半端な決断を積みかさね、どうにか日々をしのいでいるという一節がある。左太夫と藤右衛門親子が、互いの半端さをどのように受け入れたのかは、本書の読みどころの一つである。さらには、読み手の感覚に訴える多彩な色合い、空気の匂いや日差しや温度、舌の味わいまでも呼び起こすような季節のさりげない描写にも酔いしれていただきたい。
同じ架空の藩を舞台としているものの、時代も登場人物も異なり、物語の連続性もないので、本書から読んでもよいが、シリーズを通して、真夏を経ても消えぬ雪の冠を被る山なみや、北前船が立ち寄る湊を有する神山藩の輪郭を連想するのもまた一興だろう。