『ウミガメみたいに飛んでみな』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『おっぱいエール』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
近親者が死ぬことは特別じゃない。日常は続いていく
[文] 光文社/DARTHREIDER(ダースレイダー)(ヒップホップ・ミュージシャン)
二〇一七年五月、第11回小説宝石新人賞を同時受賞したふたり。
約二年半の月日を経て、デビュー単行本が同時刊行された。
『ウミガメみたいに飛んでみな』は受賞作を含む、
家族と青春がモチーフの短編小説集。
『おっぱいエール』は乳がん患者三人の、それぞれに苦悩しつつも、
前向きに過ごしてゆく日々を伸びやかに描いた長編小説。
デビュー作への思い、そして戦友の作品について、語りあった。
***

死ぬところだけが、闘病だけが、私たちの人生ではない
――第11回小説宝石新人賞の受賞から二年半が経ちました。どんな二年半でしたか?
木村 大変でした(笑)。受賞する前は、自己満足で書いていましたが、商品としてのジャッジをされるわけですから。その戸惑いがありました。いっぱいボツになりましたし。
――デビューされてから、変わったことは? できるようになったこととか。
木村 逆にできなくなったことのほうが多い気がします。「計算して書こう」と思うようになりまして、それまでは感覚で書いていたものを、なぜそう書くのか、自分に説明しなければいけなくなったんです。書くスピードが遅くなりました。勢いで書くことができなくなったことが、いちばん大きく変わったことかもしれません。
本山 私は、新人賞受賞の連絡をいただいて喜んでいたその十日後に人生二度目のがん宣告を受けました。受賞できた、うれしい、今までの苦労が報われた、と思ったところだったので、大混乱でした……。喜びと、不安と恐怖で、毎日気分が上がったり下がったりして、自分の気持ちを落ち着けるのに時間がかかって。
受賞作が掲載された「小説宝石」の二〇一七年六月号の発売日の翌日が手術の日だったんです。編集部に行って見本を受け取って、そのあとすぐ入院しました。手術した後、しばらくは全然動けなかったんですが、母が「小説宝石」を窓辺に立てて、見えるように飾ってくれていたので、一晩中「小説宝石」を見つめていました。その夜は私にとって、忘れられないものになりました。
受賞したときに編集長から、次の短編の締め切りを言っていただいていたので、「それだけは絶対に書きたい!」と思えたのが大きな希望になりました。
でも、木村さんと同じで、書くスピードが落ちました。書くのが怖くなったり、「これは本当に面白いのだろうか」と考え込んでしまったり。どこまで書けば、自分に満足のいく作品になるのか、わからなくなったこともあります。悩みつつ、体のことも気になりつつ、あっという間の二年半だったと思います。
――短編の新人賞は、受賞されても、それですぐ本が出るわけではありませんものね。
木村 新人賞をいただいて、商業誌に作品を掲載しているわけですから、その意味では自分はプロなのですが、単行本を出していないと、物書きの世界では、「まだプロではない」とも言えるのだと思います。社会との繋がりや自分の立ち位置に悩みました。プロでもアマチュアでもない、「半プロ」ですので。
本山 ある意味恵まれていて、幸せな時間だったなとも思います。自分の作品が、本という形になっていなかったので、どこか安全な場所で守られているような感覚がありました。担当編集さんからいただく感想だけが、唯一、外と繋がれる光でした。
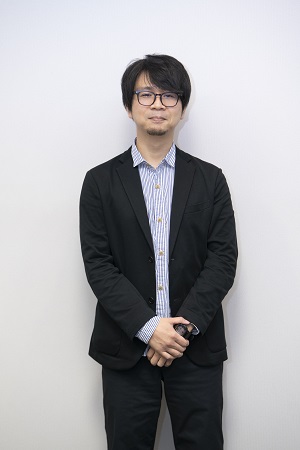
※
――そうした濃密な時間を経て、刊行されるデビュー単行本。お互いの作品を、どう読まれました?
本山 この対談のために、木村さんの作品のゲラをお送りいただいたんですが、それが、とても重くて。私が試行錯誤しながら書いてきた二年半、木村さんも同じように書いてこられたんだな、ということを実感して、なんだか泣きそうになってしまいました。
木村 そのことについてメールいただいたんですけれど、本山さんのゲラ、僕はPDFでもらっちゃったんですよね……(笑)。だから、うまく反応できなくて。あ、でも、僕もファイル容量の大きさで実感しましたよ(笑)。
本山 一編をのぞいて「小説宝石」に掲載された作品だったので、内容はわかっていたんですが、あらためて読んで、とても面白かったです。それ以上に、一緒に受賞した同期として、嬉しかったです。作家はもちろん個人事業主なので、ひとりひとりが頑張るしかないんですけど。
お父さんと亡くなったお母さん、実家にいる妹との関係だったり、父親と息子の関係だったり、お祖母ちゃんと孫の関係だったり、どの作品でも、家族がテーマとして浮きあがってくるので、誰でもきっと、「自分の家族と似ているな」と感じることができるのではと思いました。「この世界のどこかに存在する家族の物語」のような気がして、情が湧くお話だなと。
私、いちばん好きなのが「その金色を刈り取るもの」という作品で、中学生の男の子二人とそれぞれのお兄ちゃんが出てくるんですが、多感な時期ならではの微笑(ほほえ)ましいエピソードがたくさんあって。
木村 単行本にまとめることを想定して、「家族」というテーマを意識していたので、バリエーションを考えていました。で、兄弟が書きたいな、と。
うちの中学がある地域は、当時、「少年マガジン」に出てきそうなヤンキーが結構いたんです。学校から出たら、外に短ランボンタンの人たちがズラッと待ち構えていたり、塾の駐輪場で半裸の男子生徒がチェーンを振り回していたり(笑)。僕は転校してその学校に入ったんですが、それまでの学校とのギャップにやられました。だから、どう振る舞えば、彼らに見つからずに生きていけるか、すごく考えたんです。そのときの雰囲気を書いてみたいと思っていたら、ああいうキャラクターが出来上がってきました。
本山 何げないシーンやエピソードを、どの作品でもうまく切り取っていて、登場人物にとって人生の転機になるような大事件ではなくても、成長の過程でこういうことあったよね、立ち止まって悩んだよね、と思わせてくれるような作品集だと思いました。
「家族」だけじゃなくて「死」も複数の作品に出て来ますよね。身近な人の死だったり、その死を周囲の人がどう受け入れていくかという、私たちの誰もが人生のどこかで経験することを扱っていて。
木村 子どもの頃から、すごく死ぬのが怖かったんですね。子どもって、まだ脳が未熟だから、幽霊っぽいものを見るっていう話を聞いたことがありますが、僕もそうだったのか、よく見ていたんです。渦巻きの中に人が吸い込まれていっちゃう様子とか、当時住んでいた家の寝室とお茶の間を隔てているのがレインボーのカーテンだったんですが、その上に人が乗っていたり、人影がいっぱい見えたりしていました。幽霊じゃないっていうのは、当時の自分にもわかっているんです。だけど、見えてはいる。それがすごく怖くて、自分はいつか、あの渦巻きに飲み込まれて死ぬんじゃないかって怯(おび)えていました。たぶん、想像して自分で作っちゃっていたんだと思うんですけどね。それと、金縛り体質でもありました。多いときは一晩に七回かかったこともあって。特に、数学の授業中に金縛りになったときは苦しかった……。
――授業中ってのは、それは、居眠りしてたからですか?
木村 そうです(笑)。授業中だから、先生が順番に当てていくんですよ。でもこっちは金縛り中だから、焦りました(笑)。心霊現象ではなかったとしても、そういう体験が死を恐れるきっかけになったのかもしれません。
他にも、十代の頃に母親が亡くなって、同時期に親戚の不幸が続いたことで、いつか自分も死ぬんだろうな、とよく考えるようになったのも、大きな理由でしょうね。未だに死に対する恐怖を抱えている部分があります。
本山 でも、作品の中の死は悲しいだけじゃなくて、次に進むためのきっかけになっていたりしますよね。家族の死をどう受け止めるか、とか。死を扱っているけれど、前向きな作品になっているのがすごいな、と思いました。
木村 読後感のいい話を書きたいと思っていたから、ということはあるんだと思うんですけど。大学時代に、ツルんでいた友だちと話していたら、僕の他にふたり、近親者を亡くした経験のある人がいて。そのときに、ああ、特別じゃないんだと思ったんですね。そういうこともあって当たり前で、日常は続いていくんだ、と。そうやって自分を慰め、納得させていただけかもしれませんが。
本山 木村さんの作品には、本筋のストーリーとは別に、謎解きとかミステリーのような趣向もありますよね。この人は結局白黒どっちなのかとか。テンポよく読める楽しみを作ってくれていて、やみつきになります。私にはそういう書き方ができないので、いつもすごいな、と思います。
木村 もともとミステリーは好きなんです。小説を読むようになったきっかけもミステリーですし。でも、何本か短編を書いた頃に、担当編集さんから「一回もミステリーっぽいもの出してこないよね」と言われまして。今回の本にミステリー小説そのものは含まれていないんですが、そうした引っかけや仕掛けがあるのは、ちょっと挑発されたからですね(笑)。

※
――木村さんは、『おっぱいエール』、どう読まれましたか?
木村 最初、担当編集さんからPDFをもらったとき、なんとなくタイトルを見て、「どんなビールなんだろう」と思いました。
本山 そっちですか!?(笑)
木村 いや、ちょうどビールの広告を見ていたタイミングでメールが届いたんですよ。でも、すぐ、「あ、エール違いだ」って。
――こんな名前のエールビールはないでしょう?(笑)
木村 もちろん、そうなんですけど。一瞬です、一瞬。多分、思う人、他にいないと思います(笑)。
で、すぐ読んだんですけど、この小説、僕はすごく好きです。
――どんなところが?
木村 いっぱいあるんですけど、病をとおしてその人の成長を、病と直接は関係ない問題も含めて、描いていて、人間ドラマとしてすごく面白い。あと、変な言い方なんですけど、読んでいて、「この人、すごく話聞いてくれそうだなあ」と思ったんですよ。
本山 え? 私がですか?
木村 そうです。そう感じたのは、とても包容力のある小説だからだと思うんです。みんなそれぞれ、問題抱えてるじゃないですか、病に限らず。それでどうしていいかわからなくなって、身動き取れなくなっている人に、響く小説のように感じました。
乳がんという、女性にとってとても大きなテーマを扱っていて、それって、僕ら男が想像する以上のものがあると思うんです。でも、この作品は、その病気に罹(かか)っていない人たちの悩みも、決して否定しないじゃないですか。ランドセルを誰が買うかとか、結婚式の受付を引き受けるかどうかとか……そういう悩みって生き死ににはかかわらないし、病気の悩みとは比べられないんだけど、「それはそれで大変なんだよね」と、ちゃんと掬(すく)い取ってくれている。登場人物たちがそれぞれの大変さに気づいていく過程の描き方が、とても好きでした。

――闘病経験のある本山さんが、あえて病気をモチーフにして、ノンフィクションではなく小説を書こうとしたのはなぜだったんでしょうか。
本山 「生きる小説を書いてみませんか」とチャンスをいただいたからです。私は今三十九歳なんですが、二十七歳の時に乳がんになって、当時既にライターの仕事をしていたので、「絶対にこの経験を、面白いエッセイにしてやる」と人生の目標を定めたんですね。小説を書き始める前のことです。でも、無名の一般人が闘病記を出したところで、著名な方もたくさん出していますし、何のメッセージ力も持たないかな、と。それで、実現しないままでいたんですが、今回長編を書くチャンスをいただいたときに、「よし、まずは生きることについての小説を書こう、全力でぶつかってみよう」と思ったんです。
でもやっぱり、当事者でもあるので自分の経験と小説の距離感をはかるのが難しかったです。エッセイを書くときのためのメモはたくさん取ってあったので、今回小説を書くときに使えるんじゃないかと考えていたんですが、書き進めても「なんか違う」という思いが抜けなくて。結局、私がエッセイに書きたかった自分の思いや体験談を、小説の中に無理矢理入れ込もうとしていたんです。それでうまく距離感がはかれなくて。このままこの小説を書き進めたら、私、「エッセイ寄りの小説」しか書けなくなってしまう、と思いました。
それで、同世代の乳がん患者の友人たちにアンケート用紙を送って、協力してもらいました。十枚ぐらいの長い、突っ込んだアンケートでした。返送された体験談をそのまま使うようなことはしなかったんですが、同じ乳がん患者と言っても、抱えてる思いや事情は違うところもあるので、参考になりました。それで、みんなの思いを胸にもう一度はじめからやり直してみよう、と。物語のなかの登場人物と、私自身を切り離すのに時間がかかったのは、未熟さゆえではあるんですけども。
木村 すると、書き始めたときとは、かなり変わっているんですか?
本山 第一章は、あとかたもないと思います(笑)。どうしても書けなかったので、第二章から書き進めて、第三章まで書いた後に第一章に戻って、書き直しました。もっと自分に力があったら、と思いつつ、今できるだけのものは出し切った、とも思っています。ある意味、まったく知らない世界をゼロから調べて書いた方が書きやすかったんじゃないかと思いました。
もっと早く書けるんじゃないかとも思っていたんですが、二年半、かかってしまいましたね。でも、すごい挑戦をさせていただいたと実感しています。これが書けたことで、今後は書き手の存在や思いが出過ぎないように意識していくことが少しはできるのではないかと思います。
若い世代の闘病を扱った小説や映画はたくさんあると思うのですが、ほとんどの作品が病を得てから、死ぬところがクライマックスというか、死ぬシーンが感動的に作られて、ワーッと泣いて、っていう。もちろん、それも命の尊さとか何でもない日常の大切さを教えてくれると思うんですけど、当事者からすると、「闘病だけが私たちの人生ではない」「死ぬところだけにスポットライトを当てないで」という思いもあって。病気と病人が一対一で向き合う話ではなくて、病気を抱えながらも、普通の毎日を過ごしていく人を描きたかったんです。
木村 作中で、がんの厄介さを犬の糞にたとえているところも、好きです。
本山 あれ、いつの間にか書いちゃって(笑)。自分がそう思っていたわけじゃないんですが、ありがたいことに明るいシーンになりました。
――全体的に、明るい小説ですよね。
本山 ホントですか!? とてもうれしいです!
木村 海外ドラマのような味わいがありますよね。物語後半で主人公たちが金沢のあたりを長距離ドライブするシーンがありますが、アメリカのハイウェイを走っているような開放感がありました。

※
――これから、どんな作品を書いていきたいですか?
木村 短編を千本ノックのように書き続けてみて、自分にも思っていたより引き出しがあるんだな、と思いました。本山さんが闘病体験を経て長編小説を書かれたように、自分のなかにも、「あるな」とも、気づいてきました。そういったものを、面白い小説として書きたいです。
本山 同じく、とにかく猛烈に面白いモノを書きたいです。今回の作品は面白くなるかはもちろん、そもそもモノになるのかもわからず、書きたいという気持ちだけで書いていたところがあるので、あらためて「こんな話が読みたかった」と言ってもらえるような作品を書いていきたいと思いました。
小説って書けば書くほどわからなくなるし、真っ白なパソコンの画面を見ながら、本当にここが文字で埋まるのか、ひと文字目、一枚目を書き始めるときの恐怖感があって、それは一冊書いても消えなくて。早く、小説を書いている自分に慣れたいです。何万枚書けば慣れるのか、わかりませんけれど。
木村 わかります。怖いですよね。その怖さと、面白いモノを書きたいということを意識できるようになったのが、お互いの二年半の収穫なのかもしれませんね。
***
木村椅子(きむら・いす)
北海道出身。2014年、『オボロメモリの星空を』でノベルジム大賞2014特別賞を受賞。2015年、『五月の桜はさよならの式日』で第4回ノベラボグランプリ最優秀賞を受賞。2017年、「ウミガメみたいに飛んでみな」で第11回小説宝石新人賞を受賞。
本山聖子(もとやま・せいこ)
鹿児島県出身、長崎育ち。東京女子大学文理学部日本文学科卒業後、児童書・雑誌の編集に従事。2007年結婚。翌年27歳のときに患った乳がんの闘病を機にフリーランスに転向。2017年「ユズとレモン、だけどライム」で、第11回小説宝石新人賞を受賞。



































