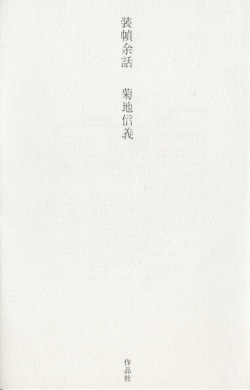『装幀余話』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『装幀(そうてい)余話』菊地信義 著
[レビュアー] 米田綱路(ジャーナリスト)
◆手にとられる瞬間に賭ける
昨年亡くなった菊地信義の語りや対談、単行本未収録の余話を、長年仕事で伴走した増子信一氏が編集し、弟子の水戸部功氏が装幀した一冊。それ自体が本づくりの仕事師たちの知と手わざの結晶である。菊地が装幀の理想とした製本サンプル「束見本(つかみほん)」のような佇(たたず)まいは、表裏と終始の無限を思わせる純粋さだ。ここには装幀論の裸形がある。
書店の棚や平台(ひらだい)で目を留め手にとってもらうのが装幀の仕事の一つだと菊地はいう。四十年以上にわたり一万五千点余の文芸書や人文書の形をつくり続けた装幀者の話は、商品でありながら、無形の心や思いを育て、言葉を届ける紙媒体の謎へと読者を誘う。
装幀を依頼されたテキストを読んで浮かぶイメージを解き放ち、本の形へと仕組んで内容を表す装いをつくる。タイポグラフィと素材の触感でテキストを表現する。視覚と触覚による重層的な作業だ。
読者はその感覚のあわいに謎をおぼえて手にとり、印刷された言葉を黙読や音読で味読し、紙とインクの匂いを感じながら版面をたどる。視覚と触覚に導かれつつ五感で読むのが、本の醍醐味(だいごみ)である。
菊地が装幀の勝負所を平台に見ていたのが興味深い。先頃閉店した八重洲ブックセンター本店二階の喫茶室から、吹き抜けの一階に並ぶ本を前にした客の動きを観察した。「いい本」と手にとられる瞬間に賭ける姿が目に浮かぶ。
知識産業において小説や詩を書く作者が一次産業とすれば、それを利用するコピーライターやイラストレーターが二次、装幀の仕事は三次だという捉え方も面白い。四十年余り前の古井由吉との対話のくだりだが、言語を生み出す一次産業が衰退し、二次的な作品が溢(あふ)れる状況を彼は肯(がえ)んじない。そして書店の平台に身をさらし、そこで作者と読者が出会って初めて成立する作物たる本をつくる、三次元の批評的な仕事を確立した。
画廊に通い骨董(こっとう)を愛する装幀者は「見る人」を自任したが、高村光太郎ばりの触覚の人、手の中で読まれる世界を夢見た言葉の人だった。本書は、その稀有(けう)なオブジェだ。
(作品社・2970円)
1943〜2022年。装幀の第一人者。著書『装幀百花』など。
◆もう1冊
『杉浦康平と写植の時代 光学技術と日本語のデザイン』阿部卓也著(慶応義塾大学出版会)