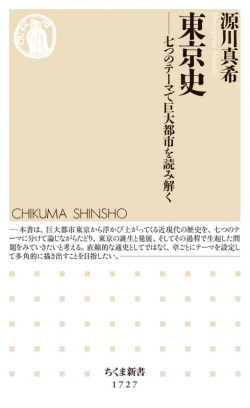『東京史』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『東京史 七つのテーマで巨大都市を読み解く』源川真希(みながわまさき) 著
[レビュアー] 荻原魚雷(エッセイスト)
◆「破壊と再生」繰り返し
かつて帝都と呼ばれた日本の首都は「破壊と再生」を繰り返しながら発展し、東西に拡大してきた。交通網や生活インフラの整備、水害、震災、空襲、戦後復興、高度成長、バブル経済……。激動の時代と重なり、世界最大級の都市空間も慌ただしく様変わりする。
著者は最新の都市史研究をもとに東京の形成過程を緻密に検証し、現状の課題を浮き上がらせる。
第5章「工業化と脱工業化のなかで」は、工業等制限法(一九五九年)により、都内の工業地区が減少し、工場の地方移転が進んだ時代を振り返る。そのころ、地方から上京し、工場で働いていた多くの労働者が新興の工業都市に移り住んだ。わたしの父もその一人なのだが、三重県生まれの自分は都市改造の影響をもろに受けていたわけだ。この章、脱工業化の流れからスマートシティ構想まで言及している。
政治経済文化が複雑に絡み合う東京の歴史は、日本の将来を考えるための手掛かりが無数にある。
(ちくま新書・990円)
1961年生まれ。都立大教授・日本近現代史。著書『首都改造』。
◆もう1冊
『国道16号線 「日本」を創った道』柳瀬博一著(新潮文庫)