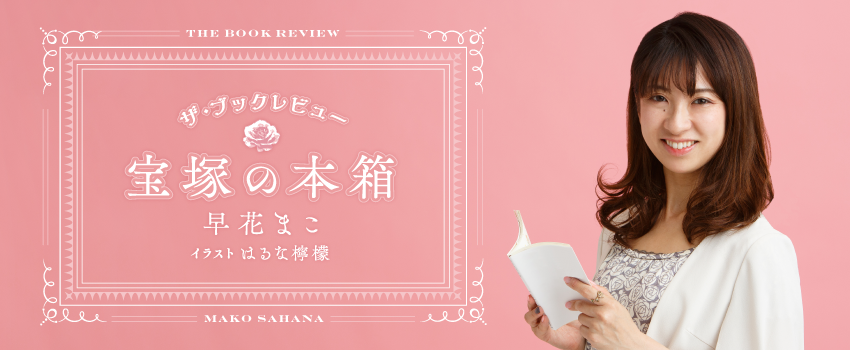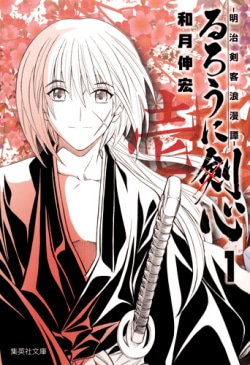大ヒット漫画『るろうに剣心』の主人公・剣心と斎藤一がなぜあれほど格好良く、人を惹きつけてやまないか、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた

2016年に雪組トップスター・早霧せいなさん主演で上演された『るろうに剣心』 イラスト:はるな檸檬
星組東京宝塚劇場公演千秋楽の本日、元宝塚雪組、早花まこさんによるブックレビューをお届けします。
今回取り上げるのは和月伸宏さんの大ヒット漫画『るろうに剣心』。宝塚では、2016年に雪組トップスター・早霧せいなさん主演で上演され、大好評を博しました。早花さんもご出演されていた本作ですが、今回は剣心と斎藤一、二人の生き様にスポットを当てました。はるな檸檬さんによる、躍動感みなぎるイラストにもご注目ください!
***
忘れられない剣客
〈時代を創(つく)るのは「刀」ではなく、それを扱う「人」でござる〉
「人を殺めない剣客」が語る言葉は、創作の中だけの綺麗事なのだろうか。それならば、この物語の主人公は、これほど読み手に愛されることはなかった。
『るろうに剣心―明治剣客浪漫譚―』は、和月伸宏さんによって描かれた漫画で、1994年から1999年まで「週刊少年ジャンプ」に連載された。
主人公・剣心は、幕末の混乱期に人斬り抜刀斎として飛天御剣流の刀を振るい、最強の人斬りと恐れられていた。だが、多くの人間を斬ってしまった後悔から、明治維新以後、もう二度と人を殺めない「不殺(ころさず)」の誓いを立てた彼は、刀を逆刃刀(刃の部分が通常と逆についているので、常に峰打ちとなる)に持ち替え、緋村剣心と名乗るようになった。
物語の中で、剣心は様々な敵と逆刃刀を交える。敵の中には、剣心の強さを利用するために、昔の人斬り抜刀斎に戻そうとけしかけてくる者もいる。だがその度に不殺を心に誓い直し、人を殺めることなく敵を退けてきた。仲間、師匠、大切な人、ある時は敵とも心を通わせながら、生きる道を模索する剣心の姿は世代を超えた幅広い読者層に支持され、アニメ化、映画化されるなど、大きな話題となった。私も、所属していた雪組で舞台化されると知った時は大変嬉しかった。
小池修一郎先生の脚本・演出により、雪組公演「るろうに剣心」が上演されたのは、2016年。人気のある漫画作品の舞台化とあって、読者にとっておなじみのキャラクターがどのように演じられるか、注目が集まった。
-
- るろうに剣心 1 ─明治剣客浪漫譚─
- 価格:754円(税込)
漫画の中の人物を演じる
緋村剣心を演じたのは、当時の雪組トップスター、早霧(さぎり)せいなさん。赤い着物と頬の十字傷、飄々としたふるまいや優しさを秘めた笑顔は、漫画から抜け出てきたようであった。
「伝説の人斬り」の剣術を身に付ける人物を演じることは、舞台化にあたり、最も難しいところであった。だが、早霧さんの殺陣の見事さはまさしく剣心そのものだった。逆刃刀を握りしめる手つき一つで、剣心の不殺の覚悟を表現していらした。流れ者の可笑しみを醸し出していた剣心は、逆刃刀を手に戦闘を始めた途端、鋭い目線で相手を射抜く。逆刃刀を鞘に収めるひと握りにも、「目の前の命を守る」決意が表れていた。一方、コミカルな場面では剣心の口癖である「おろ」を連発、憎めない人柄で観客の笑みを誘った。
剣心を取り巻く人物たちも、原作の愛読者でも納得の描かれようであった。子役が出演できない宝塚歌劇の舞台では、子供役をリアルに演じることは難しい。「るろうに剣心」の重要キャラクターとして欠かせない弥彦もまた、「童(わっぱ)」と呼ばれるに相応しい人物が演じなくてはならなかった。
弥彦は、生意気だが弱者を救う正義感を持った、まっすぐな少年である。原作では、次世代の平和を築く者として、剣心から未来を託されるという大切な役割を担う。
彩(いろどり)みちるさんは、可憐な娘役でありながら、宝塚では難易度の高いはずの弥彦を思い切りよく演じ、「るろうに剣心」の舞台を大いに盛り上げていた。漫画的な表現ではなく、声や動きに活発さを加えることで、自然な少年の演技を完成させていた。
宝塚版「るろ剣」の楽しみ方
宝塚ならではのオリジナル場面は、西洋風の館「プチ・ガルニエ」でのパーティーだ。日本髪を結った着物姿の人々は、見たこともない食べ物やドレスに驚く。慣れない洋装でダンスを踊る様子は、華やかな上にコミカルで、殺伐とした斬り合いの場面とはうってかわって楽しげであった。
西洋の文化や思想をいち早く持ち帰り、明治の日本を成長させた要人の一人である、井上馨。その夫人・武子を演じていた私は、当時の日本でどんな服飾が最先端であったか調べてみた。当時の写真を見て、ドレスや髪形を知ることができた。アクセサリーについてはなかなか資料に辿り着けず、わかったことは、イヤリングの輸入は指輪やネックレスよりも遅かったということ。漫画作品であっても時代のリアリティーにこだわって、娘役たちはイヤリングをつける人つけない人の区別をつけていた。
明治時代の女性の写真を見ては研究を重ね、日本髪をハイカラにしたヘアースタイルで雰囲気作りに励んでいた娘役たちは、勇壮な少年漫画の世界に歌劇らしい華やかさを融合させていた。
壬生の狼
「るろうに剣心」には様々な魅力的なキャラクターが登場するが、私が熱を入れて紹介したいのが、剣心と敵対しながらも共に闘う孤高の狼、斎藤一だ。あまりにも知られたことではあるが、幕末、新撰組三番隊隊長であった斎藤は、己の腕一本だけで動乱の時代を生き抜いた男だ。明治維新後は「藤田五郎」と名乗り、警察で働いている。
原作での初登場は、薬売りに扮して剣心の動向を探りにやってくるのだが、ここからもうただならぬ凄みが溢れ出ている。剣心の仲間・相楽左之助にたやすく重傷を負わせ、出だしからぎらぎらした壬生の狼らしさ全開であった。
藤田として新政府に仕える斎藤は、他者から「誇りを失った男」と思われることもあるが、ここに、鋼のような心の強さがある。彼が掲げる「悪・即・斬」という信念は、他人にどう思われても決して損なわれるものではないからだ。「悪・即・斬」こそ彼という人間の、唯一の基準である。
そんな斎藤が持つ絶対の必殺技である牙突には、四つの型がある。主に使われるのは「壱式」だが、剣心との戦闘では幾つかを応用して繰り出している。つまり、剣心ほどの剣客を相手にする時以外、ほとんど基本の牙突だけで充分に相手を殺傷できるのだ。
舞台で斎藤一を演じたのは、現在の雪組トップスター・彩風咲奈(あやかぜさきな)さんだ。ダイナミックなダンスと抜群のスタイルに恵まれた彩風さんは、漫画そのままのビジュアルを作るところから「斎藤一」を表現していた。
牙突を極める
ミュージカル化されたとはいえ、牙突には実際の戦闘で使えるリアリティーが必要だ。左手の肘を引く際に左足をしっかりと踏み込み、刀を水平に上げる。足元は広いスタンスを取り、切っ先を定めなくてはならない。彩風さんは長い手足に頼るだけではなく、肘の角度、爪先の向きなど、極めて安定した正確な体勢で技を繰り出していた。腰を落としてもスタンスを広く保てるのは、足の長さと体勢の研究が活かされたからだろう。腕の長さと筋力によって、切っ先がわずかに上を向いているのが、いかにも斎藤らしい。
長時間に及ぶ、敵と互いに技を掛け合う複雑な殺陣の最中でも、平常心を保って確実に牙突の構えに入る……恐らく斎藤も戦闘においてそうであっただろう、そう思わせる彩風さんの技術であった。
また、原作の絵の中で、斎藤を特徴づけるものの一つが、細い目である。初めて会った左之助に「ずいぶん細い目してんなあ」と言われるほどの特徴だが、その瞳は感情を読み取らせない底無しの闇である。幕末の修羅を生き抜いた男は、不気味な瞳の中を決して覗かせない。
彩風さんは舞台化粧の工夫にとどまらず、細やかな表情で斎藤の人となりを表していた。「表情が動かない人物」は、舞台で表現するのが難しいと言えるだろう。客席から見れば、「ただの無表情な人」になりかねない。彩風さんは、場面ごとに見せる表情にメリハリをつけることで、斎藤らしさを醸し出していた。口元を歪めるように笑ったり、息遣いに苛立ちを滲ませたり。表情の読めない斎藤は、決して無表情なわけではないのだと、彩風さんの演技によって気付かされた。口数の少ない場面でも、客席に背中を見せて剣心の言葉を受ける後ろ姿に、思慮深さが滲んでいた。
それぞれの正義に生きる
剣心は幕末の動乱を生き抜き、新たな時代にどう生きていくべきか模索していく。一方で、斎藤という男は変わらない。いかに時代が変化しようと、唯一の信念を決して曲げないのだ。
〈半端な強さなど無いに等しい〉
もう人を殺めないと語る剣心に、斎藤は言い放つ。斎藤が認める強さとは「完全な最強」のことなので、ほとんどの人は無ということになる。己の中途半端さを全否定されているようで、読むたびにがっくりと落ち込む言葉だ。
これからの日本は、人を活かすことで輝く。そう信じる剣心は、自分と違う思想を持つ相手をも認め、共存していこうと試行錯誤する。
一方で、斎藤は誰にも共感を求めない。媚びない。人情に流され、心揺らぐこともない。彼の前では、悪いものはただ悪い。どのような事情があろうと、即刻斬り捨てるだけだ。
悪・即・斬と、不殺。同じ境遇を生きた二人の男は、正反対の正義を胸に闘い続ける。同じ理念を抱いて幕末を生き抜いたはずなのに、こんなにもかけ離れてしまった剣心を見て、斎藤は憤る。
〈来い お前の全てを否定してやる〉
舞台で闘う斎藤を観るたびに、私はいつも妄想していた。もし斎藤と闘うとしたら……少しでも迷いを抱いたまま斬り込めば、一瞬で殺されることは明白だ。この男に全否定されるのなら、その胸に飛び込み、届きもしないと知りつつも精一杯刃を突き立ててみたい。つまらない敵だったと、斎藤は笑うだろう。殺陣の場面に雑魚キャラとして参加できれば志願してみたかったが、残念なことにそのチャンスはなかった。
「るろ剣」から学ぶもの
自らの過去を振り返る剣心の脳裏に、救えなかった命が浮かぶ。悔恨は消えることはなく、舞台の終盤、剣心は叫ぶように歌う。
〈この刀は不殺の誓いの証し この傷は不殺の誓いの印〉
歌い上げる声に秘められた、強さ。果てしない道に足跡を刻みつけるように、早霧さんは歌った。
緋村剣心と人斬り抜刀斎は、二つの人格ではない。一人の青年が併せ持つ両極端な顔であり、どちらも平和を願う心から生まれている。人間であれば誰でも、自分の中の自分と闘うことがある。私の心を動かすのは、彼の天才的な剣技ではなく、己の心と闘い続ける剣心の生き様だ。
剣心には飛天御剣流と「不殺」が、斎藤には牙突と「悪・即・斬」があった。相対する彼らだが、どちらも己の正義を信じ新しい時代を生き抜く覚悟がある。もし彼らとともに生きていたなら、私が掲げる正義とはどのような技で、どんな言葉になるだろう。遠い昔を舞台にした虚構の世界から、私は確かに人生を学んでいる。
連載記事
- 「金のために人を斬る」 浅田次郎の傑作小説『壬生義士伝』の主人公の凄みと哀しみを、元タカラジェンヌが熱く語る 2022/12/25
- 「友情とは相手が生きているあいだに発揮するもの」 元タカラジェンヌが熱く語る、不朽の名作『グレート・ギャツビー』の古びない人生哲学 2022/07/22
- 「父を殺し母を后に」 悲劇のフルコース『オイディプス王』に、元タカラジェンヌがささやかな希望を見い出してみた 2022/06/12
- 「弱い人たちは、かなわない夢を見る」 元タカラジェンヌが熱く語る、少女漫画の金字塔『ポーの一族』の素晴らしさ 2022/04/18
- 大地真央も演じた巨匠スタンダールの名作の主人公、恋に生きたその人生について、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2022/02/26
- 「美」至上主義の宝塚で「醜」を描く「ファントム」 ありのままの自分を愛して欲しかったエリックの「こじらせ」について、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2022/01/02
- 傑作時代小説『銀二貫』から、人生の幸せの意味を元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/11/03
- 人はなぜ、戦うのか――若きリーダーの死闘から、愛と死について元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/09/18
- 三島由紀夫が書いた「禁じられた恋の行末」について、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/08/15
- 復讐するのは憎しみゆえか、愛ゆえか――塩野七生の傑作小説から元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/06/15