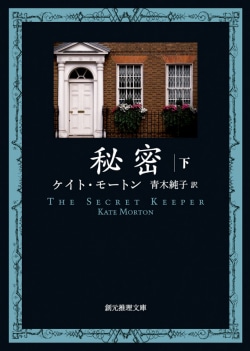書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
人生の終末期に蘇る豊かで華やかな日々「靄の向こうの記憶」
[レビュアー] 北村浩子(フリーアナウンサー・ライター)
七十代と六十代の独身姉妹、満州美と千里は九十七歳になる母・初音さんが生活する老人ホームに足繁く通っている。初音さんは常にうつらうつらしており娘すら認識できない状態だが、脳内では「かつての自分」を訪れる旅をしていた――村田喜代子『エリザベスの友達』は認知症の老女が蘇らせる「靄の向こうの記憶」を描いて、人の心から消え去らない、離れないものは何かを問いかける。
二つの世界大戦に挟まれた時代、二十代の初音さんは天津の日本租界で暮らしていた。駐在員の妻たちと交流し外国の文化を享受する、豊かで華やかな日々。浮かび上がってくるのは、若い初音さんにマナーやふるまいを教えてくれた美しい友人の鞠子さんの顔だ。初音さんは彼女にこう言われたことがあったのだった。
〈忘れないで。一生の間にほんの束の間、この租界でわたしたち日本女性が自由だったことを〉〈もしあなたが日本へ帰っても、女性の自負は持ち続けてちょうだい〉
真っ白い陽射しに照らされていたような若き日の母を娘たちは知らない。「あたくしは……エリザベス」という唐突な言葉の理由も分からない。しかし母の意識が「行きたいどこか」へ行っていることは分かる。誰もが「表」には出さない追憶の風景を携えてこの世から去ってゆく、その事実になぜか心が安らかになる。
初老の娘と母の過去、と言えばケイト・モートン『秘密』(青木純子訳 上下巻 創元推理文庫)も傑作だ。病床の母の「大変なことをしてしまった」「あれしか思いつかなかった」という告白の意味を探る娘が知った事実とは―ラストの驚きもさることながら、子が親を見送るまでの物語としても秀逸。
中島京子『長いお別れ』(文春文庫)は、認知症と診断された七十代の昇平と家族の約十年が綴られた連作短編集。どこにいても「帰りたい」と口にする昇平に、孫が「おじいちゃんの言ってる家は、家のことじゃないの?」と問う場面が印象的だ。人が人生の終末期に「帰る」場所は、自分の過去なのかもしれない。