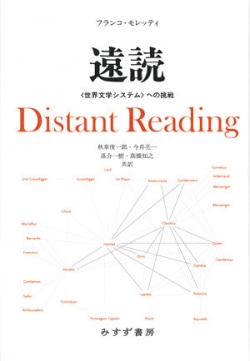『遠読』
- 著者
- フランコ・モレッティ [著]/秋草俊一郎 [訳]/今井亮一 [訳]/落合一樹 [訳]/高橋知之 [訳]
- 出版社
- みすず書房
- ジャンル
- 文学/外国文学、その他
- ISBN
- 9784622079729
- 発売日
- 2016/06/11
- 価格
- 5,060円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
デジタル時代のピカレスク 武田将明
[レビュアー] 武田将明(東京大学准教授・評論家)
フランコ・モレッティは一九五〇年にイタリアで生まれ、七二年にローマ大学で博士号を取得している。一九八三年には、初の英語で書かれた書物『奇跡のしるし——文学的形態の社会学をめぐる論集』(邦訳は『ドラキュラ・ホームズ・ジョイス——文学と社会』植松みどり他訳、新評論、一九九二)を刊行した。この論集における、作品の形式や構造への関心と、社会科学的(しばしばマルクス主義的)な視点を取り入れた分析は、その後のモレッティを予告している。同時に、巧妙なレトリックを駆使したこの書物は、著者の豊かな批評的天分を示している。彼は一九九〇年ごろから活動の中心をアメリカに移し、現在はスタンフォード大学で教鞭を執っている。
二〇〇一年から二〇〇三年まで、モレッティはイタリア語による全五巻の論集『小説』を編集している。二〇〇六年には二巻本の英語版も刊行されたが、これはヨーロッパに限らず世界中のあらゆる小説に関する論考を集積した、まさに小説研究の百科全書である。関心の拡大と呼応して、モレッティは「反文芸批評」ともいうべき、巨視的で能率的な文学研究の手法を模索する。その成果である『グラフ、地図、樹——文学史の抽象モデル』(二〇〇五)は、あまりに非文学的なタイトルそのままに、日本やアフリカも含む世界文学を観測するためのさまざまな図表を収めている。この小さい本は、批評理論に関心のある文学研究者に衝撃をあたえた。彼ほど天分に恵まれた学者が、どうしてこのようにエキセントリックな研究を始めたのか? その経緯と展望を示すのが、一九九一年から二〇一一年までに執筆された十本の論考を年代順に収めた本書『遠読』(原著二〇一三)である。
本書の中核をなす「世界文学への試論」において、モレッティはふたつの重要な主張をしている。ひとつは、世界文学を研究するには、新批評(ニュー・クリティシズム)から脱構築(ディコンストラクション)に至る二十世紀の文学研究を支えてきた精読(クロース・リーディング)の伝統をスッパリ切り捨て、細部ではなく作品全体、さらには特定の作品群を俯瞰する遠読(ディスタント・リーディング)をこそ実践しなければならない、ということ。この方法は、批評理論を細々と適用して論文を生産してきた研究者には受け容れがたいだろう。もうひとつの主張は、「西ヨーロッパのパターンと地域の現実の妥協として」世界各地で小説が勃興したが、この妥協の難しさが西ヨーロッパ以外の地域の文学に形式上の「ひび」を生んだということ。たしかに近代以降の世界文学にはそのような面があるものの、批評理論があれほど警戒した西欧中心主義にあまりに無自覚な推論にも思われる。
「文学の屠場」、「プラネット・ハリウッド」、「スタイル株式会社」は、いずれも遠読の実践例である。「文学の屠場」は、シャーロック・ホームズ物と同時代の探偵小説との差異を分析、「プラネット・ハリウッド」はアメリカ映画の他地域への影響を分野別のデータに基づいて考察、「スタイル株式会社」は一七四〇年から一八五〇年の英国小説のタイトルがいかに変遷したかを研究している。どれも文学研究を刷新する視点を示しているが、遠読の問題点も露呈している。たとえば「文学の屠場」が示す、一五八作の短篇ミステリーにおける「手がかり」の示し方を分類した樹形図は、物語論(ナラトロジー)から見ればあまりに単純だし、大枠でもホームズ物の優位という常識を追認するものでしかない。これに比べて「スタイル株式会社」は、タイトルの変遷という意外な切り口から七千冊の小説を見事に分類している。しかしこれでもまだ、遠読として不十分かもしれない。いまや誰でも、Google Ngram Viewerを用いれば、一五〇〇年から現代までの書物に登場するキーワードの出現頻度を調べることができる。現実のテクノロジーは、さらに遠くまで「遠読」を進めることを可能にし、ミステリーとは何か、小説とは何か、という問題にまったく新しい視点を提供してくれるはずである。
他方、「小説」、「ネットワーク理論、プロット分析」の二篇では、中国の白話小説がヨーロッパの近代小説の比較可能なオルタナティブとして分析されている。中国文学に関する知識の不足を露わにしつつも(ちなみに、著者の誤解については、丁寧な訳注が施されている)、ここでは小説というジャンルの多義性・相対性が問われている点が刺激的である。たとえば「小説」という論文には、近代ヨーロッパにおける消費社会の誕生が、真剣な解釈ではない、気晴らしとしての読書を可能にしたために、他ではなくこの地域を中心に近代小説が勃興したという記述がある。この推論を厳密に論証するのは難しいものの、ここでモレッティは、限られた「正典」をまじめに精読するという文学研究の伝統が、そもそも近代小説の本質を取り逃がしていたことを暗示している。
「さらなる試論」と「始まりの終わり」は、遠読的な研究手法への批判に対する応答である。全体的に見れば、モレッティの反論は歯切れがよいとはいえない。遠読だけではなく精読も必要だと譲歩しているが、そこには「世界文学への試論」に横溢していた挑発的な高揚感は見られない。また、モレッティのデータへの扱いは、結局のところ既存の現実を確認しているだけではないか、という批判に対しては、十分に反駁できていないように思える。ならばモレッティは、マルキシストというよりデジタル化されたヘーゲリアン——「現実的なものは理性的である」——なのか?
だが、このようにまとめてしまう書評家こそが、始まりを終わりにすり替える悪しきヘーゲリアンなのではあるまいか。そもそも本書は結果の書物ではない。モレッティがこれらの論考を発表し始めたころには、「世界文学」を研究するという発想自体がまだ珍しかったのを忘れてはならない。これはあくまでも過程の書物、それもなにかが始まる過程を示すセミドキュメンタリーなのだ。
本書について、これ自体が「悪漢小説(ピカレスク)」なのだ、という指摘もある。イタリアで様々な知識と言語を習得し、アメリカの学会で成功を収めるという、現代の教養小説の主人公が(モレッティには教養小説に関する優れた業績もある)、実はさまざまな地域を着の身着のままで旅しながら、珍しいものや怪しい話に手を出しては少し痛い目に遭うピカロとしての一面も持つというのは、なかなか魅力的な物語ではなかろうか。モレッティほどの研究者が、あえてこのような研究に挑戦していることの意義を過小評価してはならない。デジタル時代に批評を志す者ならば、一度は手に取らないといけない書物である。