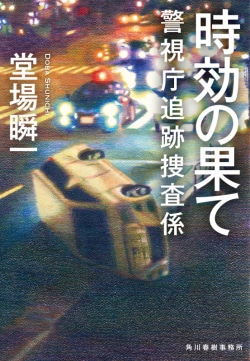少しずつ暖かくなる今日このごろ、これからやってくる花の季節に思いを馳せつつ、読書をしましょう! ニューエンタメ書評!
レビュー
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
ニューエンタメ書評
[レビュアー] 細谷正充(文芸評論家)
こんな時期だからこそ、自分のとっておきの一冊が見つかるかもしれません。
今回はミステリー小説をはじめ8作品をご紹介します。
***
正月が明けたと思ったら、関東の一都三県に緊急事態宣言が発動された(その後、拡大)。埼玉在住の私も不要不急の外出を控えているが、家に籠るのは苦にならない。せっかく時間ができたのだからと、買ったまま積んである翻訳ミステリーを読んでいた。マイケル・ギルバートの『ケイティ殺人事件』や、アントニー・ギルバートの『つきまとう死』など、面白い作品を発見できて満足である。
その一方で、日本のミステリーも当然のように読んでいる。斬新な設定に感心したのが、佐藤青南の『お電話かわりました名探偵です』(角川文庫)だ。主な舞台は、Z県警の通信指令課。110番通報を受ける部署である。そこに配属されている、語り手の早乙女廉は、イケボ(美声)で、なぜか奇妙な通報に遭遇しやすい。その通報の謎を、万里眼の異名を持つ同僚の君野いぶきが、鮮やかに解決する。要は安楽椅子探偵なのだが、警察小説でそれを成立させたところがミソだろう。よく思いついたものである。
さらに話の内容もいい。五篇が収録されているが、特に優れているのが冒頭の「家を盗まれた女」だ。買い物から帰ってきたら家が跡形もなく消えていたという不可能興味満点の通報が、いぶきの推理により、意外な地点に着地する。なるほど、そうだったのかと感心しきり。ユニークな警察小説の誕生を喜びたい。
第七回角川春樹小説賞特別賞を受賞した『明治剣狼伝 西郷暗殺指令』から、時代小説を書き続けてきた新美健だが、『カブ探』(徳間文庫)で初めて現代を舞台にした作品に挑んだ。主人公は地元の地方都市で私立探偵をしている、中年男の南原圭吾。妻とは離婚し、大学生の娘の梨奈とふたり暮らし。本田技研工業の小排気量オートバイ──いわゆるカブの愛好家で、日常的に乗り回している。
本書は連作長篇といっていいだろう。昔馴染みのヤクザ・荒俣雄二の依頼で、盗まれた組の車を捜すうちに、バイク窃盗団にぶち当たり、これを壊滅する。私立探偵という職業はさて措き、娘に弱い常識人に見える圭吾。だが彼は、暴力が必要だと思えば躊躇しない。敵や邪魔者には、手も足も出す。まるで六〇年代の通俗ハードボイルドのようだ。それだけで私は、ご機嫌になってしまう。
しかも本書は、カブに淫した物語でもある。自身もバイク乗りで、カブを愛好している作者だ。全世界で数十年にわたり愛されているカブの魅力が、これでもかと描かれている(レースもあるよ)。幾つもの騒動を経てたどり着く、粋なラストまで、大いに堪能した。
昨年の暮れに仕事で、堂場瞬一さんにインタビューをした。そのときに現在刊行中の警察小説のシリーズ三作をクロスさせた、コラボ作品を刊行するといっていた。『時効の果て 警視庁追跡捜査係』(ハルキ文庫)は、その第一弾だ。捜査が長引いて「冷えて」しまった事件を再調査する、追跡捜査係所属の西川大和と沖田大輝の主人公コンビについては、あらためて説明する必要はないだろう。ただし今回、沖田は出張中。週刊誌のスクープを切っかけに注目を集めた、三十一年前のバラバラ殺人事件の調査(時効なので捜査ではない)をするのは西川と、「ラストライン」シリーズのベテラン刑事・岩倉剛だ。こういうコラボで来たかと、最初から興味津々でページを捲ることになった。
似たようなタイプだが、違った部分もある。そんな西川と岩倉が、ぶつかり合いながら、過去の事件の真相を追う。ある騒動が起こると、物語のギアが一段上がり、ラストまで一気に読ませる。作者の豪腕は相変わらずだ。刑事としての一線からはみ出してまで、時効事件の犯人に鉄槌を下す、岩倉のデカ魂もよかった。
なお、コラボ企画の第二弾『骨を追え ラストライン4』は三月、第三弾『警視庁犯罪被害者支援課8』は八月に刊行する予定。今年も堂場作品を、たっぷりと楽しめそうだ。
この調子で書いていると、ミステリーばかりになるので、他のジャンルにも目を向けよう。仁木英之の『我、過てり』(角川春樹事務所)は、四人の戦国武将のしくじりと、そこから人生をいかに挽回しようとしたかを描いた短篇集だ。主に芸能人が、自身のしくじり体験を語る「しくじり先生 俺みたいになるな!!」というテレビ番組があるが、その戦国武将版である。武田晴信(信玄)の侵攻を三度退けながら、敗者になってしまった信濃の雄・村上義清の生き方。豊臣秀吉の惣無事令を軽んじてしまった、伊達政宗の必死の行動。大坂の陣で光の当たる武将になりながら、大失敗をした岩見重太郎の選んだ道。秀吉への忠義により、本来の義を見失った立花宗茂の悟り。戦国小説の好きな人ならご存じの武将たちの人生が、独自の視点で表現されている。
現代の若者たちは、自分が失敗することを、極端に恐れているという。しかし生きていれば、一度や二度は、大きなしくじりをするものだ。ならば、しくじりをした後の、人生のリカバリーを考えることは無駄にはなるまい。四人のしくじり先生から、学べることは多いのだ。
朝松健の『血と炎の京 私本・応仁の乱』(文春文庫)は、室町伝奇小説を書き続けてきた作者の、現時点での総決算である。すでに新聞の書評で取り上げているが、行数の関係で書き切れない部分があったので、こちらでも言及したい。
近江の堅田衆の若長だった通武は、西軍を率いる山名宗全に家族と一族を殺された。自身も額に犬と刻まれ、杭に括られて瀕死のところを、東軍を率いる細川勝元に助けられる。足軽豺狼組の一員になり、名を骨皮道賢と改めた通武は、宗全への復讐のため激しい戦いに身を投じる。だが新兵器の登場により、「戦さ」そのものが、大きく変わろうとしているのだった。
骨皮道賢は、応仁の乱で東軍の足軽頭を務めた実在人物である。といってもマイナーな存在であり、経歴や事跡に不明点が多い。だからこそ作者は、道賢を縦横無尽に使うことができたのだろう。復讐に燃える道賢が、異能の仲間と共に繰り広げる戦いが痛快だ。
その一方で、人類の戦いの分岐点を捉えていることにも留意したい。人と人による戦いが、いかにして兵器による大量殺戮へと変わったのか。作者は戦場に新兵器を投入し、その瞬間を活写したのだ。そしてこの戦争による大量殺戮は、第一次世界大戦の毒ガスや、第二次世界大戦の原子爆弾まで繋がっていく。人類の愚かな歴史と、重き業が、この物語に凝縮されているのである。
山口恵以子の『ライト・スタッフ』(潮出版社)は、映画が娯楽の王様だった昭和三〇年代に、映画会社の照明係になった男の一代記だ。太平洋映画会社の助監督試験に落ちた五堂顕。大学の同期で、女性としては初の脚本部に採用された浜尾杉子に誘われ、撮影所に行った彼は、なりゆきで照明部に採用される。助監督として採用された、植草一や長内浩を気にかけながら顕は、照明の仕事にのめり込んでいくのだった。
周囲をプロに囲まれ、仕事の面白さに目覚めていく顕。毎日がお祭りみたいな撮影所で、どんどん成長していく彼の姿が、気持ちのいい読みどころだ。女優のしたたかな立ち回りや監督の傲慢、女性軽視など、花形産業の光だけでなく、陰の部分もきっちり描かれている。その上で、好きな仕事に邁進した男の人生を、愛情をもって見つめているのである。いい作品だ。
そうそう、本書のちょっと後に出た、『みんなのナポリタン 食堂のおばちゃん9』も、相変わらずの面白さ。山口恵以子、絶好調である。
坂井希久子の『花は散っても』(中央公論新社)は、現代パートと過去パートが交互に描かれている。現代パートは、妊活がうまくいかず、優柔不断な夫と別居中の磯貝美佐が主人公。ある日、銘仙と謎の美少女の写真、そして祖母・咲子のノートを見つける。過去パートは、そのノートに書かれた咲子の半生だ。川端家の養子になり、義姉となった龍子と共にミッション・スクールに通う咲子。楽しき日々を過ごすふたりだが、戦中戦後の混乱の中で、彼女たちの楽園は崩壊する。龍子は美しいものしか見ず、咲子は義姉を守るために修羅の道を選択するのだった。
昔の少女小説のような感じで始まる過去パートは、やがて息詰まるような人間ドラマへと変貌する。その中から立ち現れる、咲子の悲しくもしたたかな生き方に圧倒された。しかし本書の読み味は、苦いだけではない。祖母の過去を知った美佐が、自分の結婚生活を見直し、新たな道へと踏み出すのだ。どんな絶望があろうと、生きていれば人の歴史が繋がり、いつかは希望が生まれる。そのような作者のメッセージを、強く感じた。
最後は、新井久幸の『書きたい人のためのミステリ入門』(新潮新書)を取り上げよう。新潮社の編集者である著者が、自身の編集者経験を踏まえて執筆したミステリー小説の執筆入門書である。読み始めて、あまりにも初歩の初歩から懇切丁寧に書かれていて、ちょっと驚いた。だが、これで正解。私も各種新人賞の下読みをしており、ミステリーの応募作も大量に目を通している。その中の少なくない作品が、ミステリーという約束事の多いジャンルに対する理解が乏しいと感じられる内容になっているのだ。ミステリーを応募しているが、一次予選も通過しない人は、ぜひとも本書を参考にしてほしい。下読みとしての、切実なお願いである。
なお著者は、あの京大ミステリ研出身とのこと。本書の中で、幾つもプロの作品が挙げられているが、妙にマニアックなのが紛れ込んでいるのはそのせいか。ということで、小説を書く気がなくても、ミステリー好きなら楽しめる一冊である。