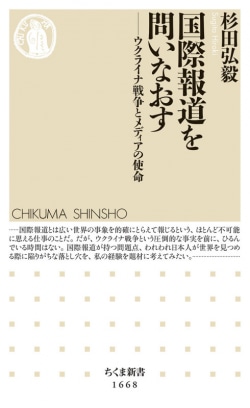『国際報道を問いなおす』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
<書評>『国際報道を問いなおす −ウクライナ戦争とメディアの使命』杉田弘毅 著
[レビュアー] 内田誠(ジャーナリスト)
◆「何でも見る」の姿勢こそ
ロシアによるウクライナ侵攻を予想できなかったことから、日本の国際報道が抱える欠陥を検証しようとしている。著者は共同通信の記者としてテヘランやニューヨーク、ワシントンで勤務し、長く国際報道に携わり、現在も特別編集委員兼論説委員の立場にある。その人が「国際報道を問い直す」と言うのだから穏やかではない。
著者によれば、これまでの日本の国際報道は、米国メディアの記事を翻訳し「横のモノ(外国語)を縦(日本語)にする」だけで「自分で取材して自分で判断」してこなかったと断罪している。だが、少なくとも「戦争の行方」の予測に関しては、冷戦後の世界秩序が流動化する中でいっそう困難になっており、合理的とは思えない判断を行う権力者が勢いを増す世界では、そもそも期待されているかどうかも分からない。
著者も「国際報道に長く携わってきた私も、核兵器大国のロシアが隣国にあれほど残酷に侵攻するとは予想できなかった」というが、プーチン氏には侵攻する理由も、侵攻しない理由もあったはずで、絶対に侵攻しないとは著者を含め、誰も思っていなかっただろう。
著者が言いたいことはもっと別のことなのかもしれない。本書は第一章を「先駆者たち」と題し、戦後日本のジャーナリズムの綺羅星(きらぼし)のような担い手について多くの紙幅を割いて紹介している。登場するのは、作家の開高健、村松剛、日野啓三とジャーナリストの岡村昭彦、大森実、田英夫、本多勝一ら。彼らに共通する点として強調されているのは「何でも見てやろう」という世界に対する好奇心と徹底した「現場主義」のようだ(なぜか『何でも見てやろう』の小田実には言及がない)。
実際「現場主義」から生まれたベトナム戦争に関する優れたリポートなどは、さまざまな方向に社会を揺さぶり、人々の生き方に影響を与えた。フェイクやプロパガンダが横行する世界で「何でも見てやろう」という姿勢を回復してほしいというのが、著者の切なる願いなのかもしれない。
(ちくま新書・968円)
1957年生まれ。共同通信特別編集委員兼論説委員。明治大特任教授。
◆もう1冊
宮嶋茂樹著『ウクライナ戦記 不肖・宮嶋 最後の戦場』(文芸春秋)